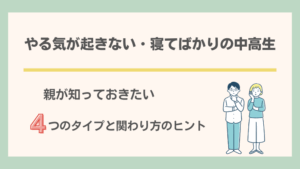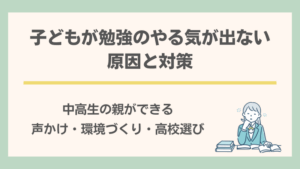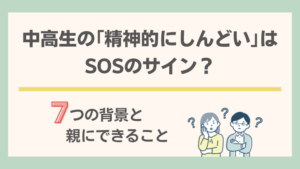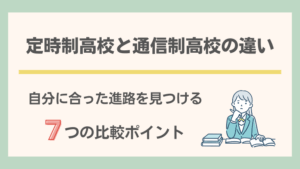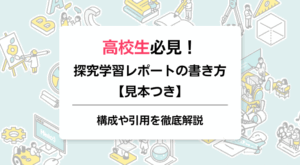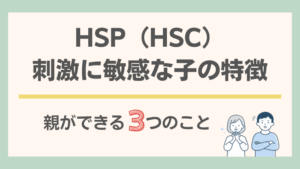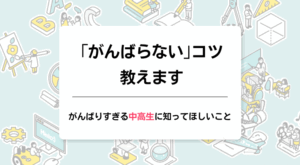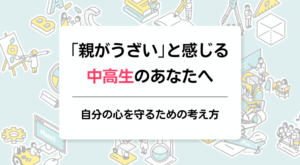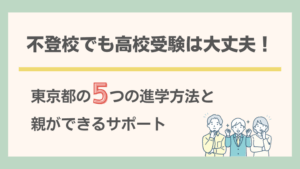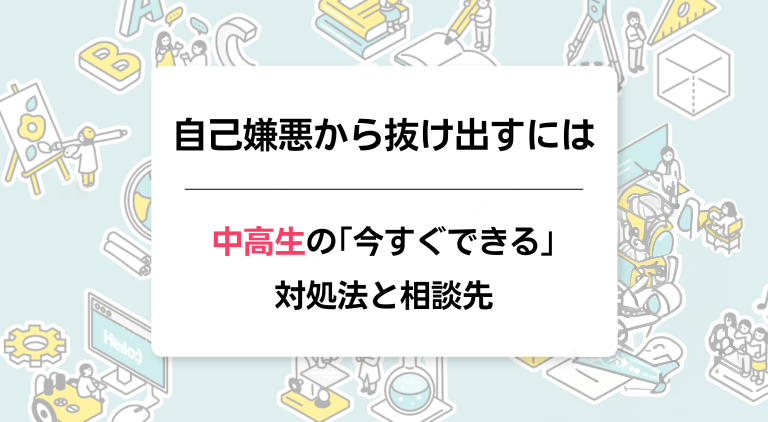

また失敗してしまった…



どうして自分はこんなにダメなんだろう
こんなふうに、自分を嫌いになってしまうことはありませんか?
思春期は人と比べる機会が増え、友達の姿やSNSで発信される情報と自分を比べて、落ち込むことも多いのではないでしょうか。
これは誰にでもある自然な感情ですが、強くなると毎日がしんどく感じてしまうことがあります。
自己嫌悪とは『自分を嫌う気持ち』のこと。
劣等感や罪悪感とは違い、自分そのものを責めてしまう状態です。
けれど、紙に書き出すなどの小さな工夫で、つらい気持ちは軽くできます。
この記事では、自己嫌悪の意味や似ている感情との違い、中高生が感じやすい場面や放置したときの影響、そして今日からできる5つの工夫を紹介します。
読んでいくうちに「自分だけじゃない」と安心できて、前に進むきっかけが見つかるはずです。



一人で抱え込まなくても大丈夫
一緒に、自分との向き合い方を考えていきましょう。
【この記事でわかること】
自己嫌悪とはどんな気持ちなのか
劣等感・罪悪感・自己否定との違い
中高生が自己嫌悪を感じやすい場面
自己嫌悪を放置するとどうなるのか
気持ちを軽くする5つの工夫と相談先
自己嫌悪ってどんな気持ち?


自己嫌悪とは、『自分を嫌い、自分を責めてしまう気持ち』のことです。
たとえば、テストで思うような点数が取れなかったとき。
最初は



悔しいな
と思うだけだったのに、だんだん



自分は勉強ができない人間だ
こんな自分が嫌い
という気持ちに変わっていく―これが自己嫌悪です。
でも、実はこの感情は特別なものではありません。
厚生労働省の調査でも、思春期は学校生活や人間関係の影響を受けやすく、気持ちが揺れやすい時期だと伝えられています。
(厚生労働省「令和6年版厚生労働白書-こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に-」)
成績や友達との比較、SNSの情報などが重なって、自己嫌悪を感じるのはごく自然なことなのです。
友達を見て「すごいな」と思う気持ちが、だんだん「それに比べて自分は…」に変わってしまうこともありますよね。
そんなふうに、自分を責めてしまう気持ちが強くなるのが自己嫌悪です。
自己嫌悪とよく似た言葉に『劣等感』『罪悪感』『自己否定』などがありますが、それぞれ少しずつ意味が違います。
違いを知ることで、自分の気持ちを整理しやすくなります。
ここからは、その違いを一緒に見ていきましょう。
劣等感とのちがい
自己嫌悪とよく混ざってしまう感情に『劣等感』があります。
劣等感=人と比べて落ち込む気持ち
例:友達よりテストの点数が低くて「自分は勉強が苦手だな」と落ち込む
自己嫌悪=落ち込んでいる自分のことを嫌いになる気持ち
例:点数が低くて落ち込んだあと、「こんな自分はダメだ」と自分そのものを責めてしまう
まとめると、次のような違いがあります。
| 感情 | 特徴 |
| 劣等感 | 他人との比較から生まれる気持ち |
| 自己嫌悪 | 自分自身を責めてしまう気持ち |
どちらも誰にでもある自然な心の反応です。
違いを知っておくことで、「今の自分はどちらの気持ちなんだろう?」と整理しやすくなります。
劣等感についてもっと詳しく知りたい人は、こちらの記事も読んでみてください。
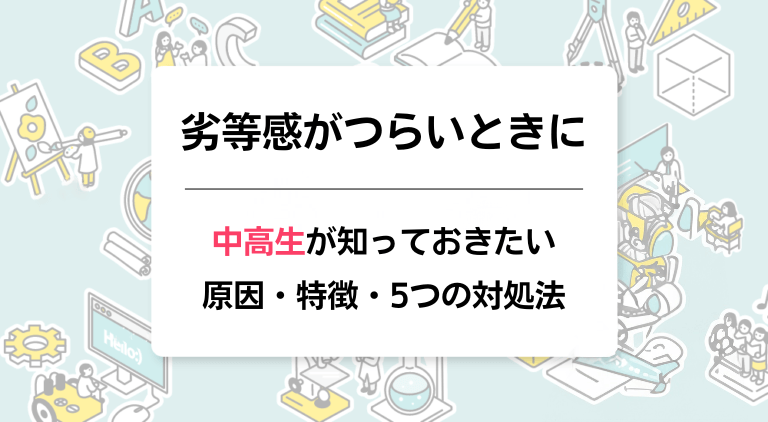
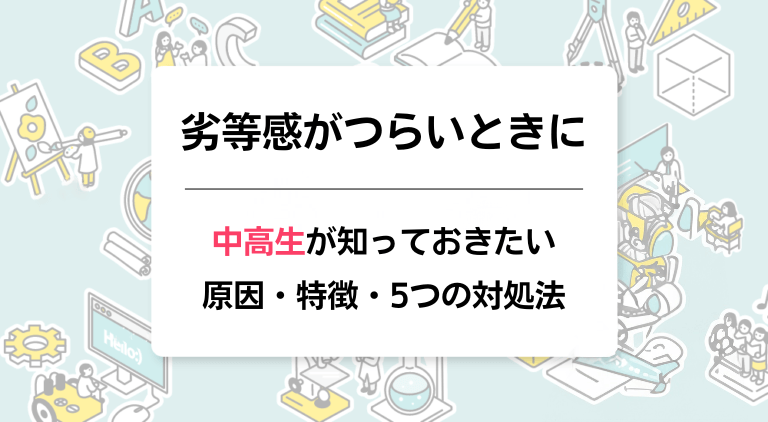
罪悪感とのちがい
自己嫌悪とよく似た気持ちに『罪悪感』があります。
罪悪感=人に迷惑をかけたり、ルールを破ったりしたときの「ごめんなさい」という気持ち
例:宿題を忘れて先生に迷惑をかけて「申し訳ないな」と感じる
自己嫌悪=行動ではなく、自分そのものを「ダメだ」と思う気持ち
例:宿題を忘れたあとに「そんな自分は最低だ」と思い込み、自分を責めてしまう
まとめると、次のような違いがあります。
| 感情 | 特徴 |
| 罪悪感 | 自分の行動が他人に迷惑をかけたときの「申し訳ない」気持ち |
| 自己嫌悪 | 自分そのものを「ダメだ」と感じる気持ち |
罪悪感は『行動』に向けられるもの、自己嫌悪は『自分自身』に向けられるもの。
違いを知っておくと、自分の気持ちを冷静に整理しやすくなります。
自己否定とのちがい
自己嫌悪と混ざりやすい言葉に『自己否定』があります。
自己否定=「自分には価値がない」と考える“思考”
例:テストでミスをしたときに「自分は何をやってもダメだ」と決めつける
自己嫌悪=「自分のことが嫌いだ」と感じる“感情”
例:ミスをしたあとに「こんな自分は嫌いだ」と気持ちが強く落ち込む
まとめると、次のような違いがあります。
| 感情 | 特徴 |
| 劣等感 | 他「自分には価値がない」と考える思考 |
| 自己嫌悪 | 「自分のことが嫌い」と感じる感情 |
思考と感情はつながっているので重なりやすいですが、『考え』と『気持ち』を分けて理解すると、心の整理や対処もしやすくなります。
自己嫌悪が強くなる4つの理由
自己嫌悪が強いと



自分の性格が弱いからだ



自分だけがおかしいんだ
と思ってしまうかもしれません。
けれど、そうではありません。


自己嫌悪が強くなるのは、性格のせいではなく、環境や考え方のクセが影響していることが多いのです。
たとえば
ちょっとしたミスを大きく捉えてしまう
人と比べる習慣が抜けない
思春期のゆらぎも重なって、気づかないうちに『自分を責めるクセ』が強くなることがあります。
ここでは、自己嫌悪が強くなる4つの理由を紹介します。
「あ、これは自分に当てはまるかも」と気づければ、そこから対策のきっかけを見つけることができます。
理由① 気にしすぎて、自分を追い込んでしまう



もっと頑張らなきゃ



100点じゃないと意味がない
こんなふうに考えてしまう人は、知らず知らずのうちに自分を追い込んでしまいます。
完璧を求めすぎると、小さなミスでも『失敗』と感じてしまい、強い自己嫌悪につながるのです。
たとえば
テストで90点を取っても「あと10点足りなかった」と落ち込み、「やっぱり自分はダメだ」と自分を責める
完璧主義の考え方から生まれる自己嫌悪の典型的なパターン
また、一度の失敗を大きくとらえてしまう『拡大解釈』もよくあるクセです。
たとえば
発表で言葉に詰まっただけで「自分は人前で話すのが下手だから、もう何をやっても無理だ」と思い込んでしまう
ほんの一場面の出来事を、自分のすべてに結びつけてしまい、どんどん自分を責める気持ちが強くなる



大切なのは、失敗やミスが『一度の出来事』であって『自分そのもの』ではないと意識することです
そう考えるだけでも、気持ちは少しラクになります。
理由② 比べグセが止まらない
学校の成績、部活での活躍、SNSのフォロワー数や『いいね』の数―中高生の生活には、比べるきっかけがたくさんあります。
最初は「友達ってすごいな」と思うだけだったのに、だんだん「それに比べて自分は…」となり、最終的には「どうせ自分なんてダメだ」という気持ちに変わってしまうことがあります。
たとえば
テストで自分より点数の高い友達を見ると、「自分は頭が悪いんだ」と思い込んでしまう
部活でレギュラーに選ばれなかったときに、「自分は役立たずだ」と決めつけてしまう
SNSでは、楽しそうな投稿や多くの『いいね』を見て、「自分は人気がない」と感じる
こうした繰り返しが、少しずつ自己嫌悪を強めていきます。
比べること自体は自然なことです。
でも、『比べグセ』が強くなると、結果や出来事ではなく『自分そのもの』を否定してしまいやすくなります。



大切なのは、比べて落ち込んでいる自分に気づくこと
そして『結果=自分の価値』ではないと意識するだけでも、気持ちは少しラクになります。
理由③ 自分の良いところが見えなくなる
自己嫌悪が強くなるとき、多くの場合、自分の“短所”ばかりに目が向いています。
テストでできなかった問題や、友達との会話でのちょっとした失敗など、うまくいかなかったことばかりが頭に残ってしまうのです。
一方で、できていることや自分の良いところには気づきにくくなります。
たとえば
授業で答えを間違えた』ことは覚えていても、『別の教科で先生に褒められた』ことはすぐに忘れてしまう
こんなふうに視野が狭くなると、「自分にはいいところなんてない」と思い込んで、自己嫌悪を深める
特に、周りから褒められる機会が少ないと、この傾向は強くなります。



でも実際には、あなたの中にはたくさんの小さな良さがあります
気づきにくいだけで、良さが『ない』わけではありません。
理由④ 思春期のゆらぎも関係している
中高生の時期は、心や体が大きく変化する『思春期』にあたります。
ホルモンバランスの影響で気分が揺れやすくなったり、ちょっとしたことで不安になったりするのは自然なことです。
さらに、学校生活や家庭でのプレッシャー、友達関係なども加わって



ちゃんとしなきゃ



みんなに合わせなきゃ
という思いが強くなりやすい時期でもあります。
その結果、うまくいかないことがあると「やっぱり自分はダメだ」と感じやすくなり、自己嫌悪が強まってしまうのです。
この時期の心の揺れは、決して“自分だけ”ではありません。
多くの人が同じように不安定さを経験しています。
思春期特有の変化と理解しておくだけでも、自分を責めすぎずに過ごせるようになります。
自己嫌悪を感じやすい人の特徴
自己嫌悪を感じやすい人には、いくつかの共通した傾向があります。
「自分ってこういうところがあるかも」と気づくことは、決して悪いことではありません。
むしろ、自分のクセを知ることで、気持ちを整理したり対策を考えたりするきっかけになります。
たとえば
完璧を求めすぎてしまう人
人の評価を強く気にしてしまう人
失敗ばかりに目がいってしまう人
いつも誰かと比べてしまう人
こうした特徴は、裏を返せば『向上心がある』『人の気持ちに敏感』『真面目でがんばり屋』といった強みでもあります。
ここでは、自己嫌悪を感じやすい人の特徴を4つ紹介します。
自分に当てはまる部分を見つけながら、『どう向き合えばいいのか』を考えるきっかけにしてくださいね。
完璧主義で自分に厳しい



100点じゃないと意味がない



少しでも失敗したらダメ
そんなふうに考えてしまう人は、自己嫌悪を感じやすい傾向があります。
テストで90点を取っても「100点じゃないから失敗」と考えてしまう
部活で全力で頑張っても「勝てなかったから意味がない」と思ってしまう
小さな成功や努力を認められず、「自分はダメだ」と感じやすくなる
完璧主義は努力家で真面目な性格の表れでもありますが、自分に厳しすぎると心を追い込んでしまうことがあります。
人の評価を気にしすぎる



周りにどう思われているかな



嫌われたらどうしよう
人からの評価を気にしすぎてしまう人も、自己嫌悪を感じやすいタイプです。
相手の反応を気にするあまり、自分の行動に自信が持てなくなってしまいます。
先生に少し注意されただけで「自分はダメな生徒だ」と落ち込む
友達の反応が薄いと「必要とされていないのかも」と不安になる
人からどう見られているかばかり気になり、「自分は価値のない存在だ」と自己嫌悪につながりやすくなる
気にしすぎるのは「人の気持ちに敏感」という強みの裏返しでもあります。



大切なのは、他人の評価だけで自分の価値を決めないことです
短所ばかりに目がいく
自己嫌悪を感じやすい人の中には、『できたこと』より『できなかったこと』にばかり意識が向いてしまうタイプの人もいます。
小さなミスや失敗を繰り返し思い出してしまい、自分を責める気持ちが強くなるのです。
授業で答えを間違えたことを何度も思い出してしまう
友達との会話での失敗を振り返って「やっぱり自分はダメだ」と考えてしまう
短所ばかりが頭に残り、「自分には良いところなんてない」と思い込みやすくなる
ただし、短所に気づけるということは「改善しよう」とする前向きさの表れでもあります。



大切なのは、短所だけでなく長所やできていることにも目を向けることです
人と比べるクセが強い
成績や部活での役割、SNSのフォロワー数や『いいね』の数など、私たちの身の回りには比べる材料がたくさんあります。
比べること自体は自然な行動ですが、それが強くなりすぎると自己嫌悪につながってしまいます。
テストの点数が友達より低いと「自分は頭が悪い」と決めつけてしまう
SNSで友達の投稿にたくさん『いいね』がつくと「自分は人気がない」と落ち込む
比べる相手が増えるほど「どうせ自分は劣っている」という気持ちが強くなり、自己嫌悪につながりやすくなる
比べる気持ちは『向上心がある』ことの裏返しでもあります。



他人との違いをそのまま『自分の価値』に結びつけないことが大切です
中高生が自己嫌悪を感じやすい場面とは?
自己嫌悪は、ちょっとした出来事や日常の中でも生まれる感情です。
特に中高生の時期は、学校生活や友達との関係、家庭でのやり取りなどで『比べる』『失敗する』ことが多く、それがきっかけで「自分はダメだ」と感じやすくなります。
たとえば
テストの点数や部活での成果を友達と比べて落ち込むとき
SNSで周りの楽しそうな投稿を見て「自分はつまらない人間だ」と思ってしまうとき
家族から比較されたり、ちょっとした失敗を責められて「役に立たない」と感じてしまうとき
ここでは、中高生が自己嫌悪を感じやすい3つの場面を紹介します。
読んでいて「これ、自分もそうかも」と思える部分があったら、それはあなただけでなく、多くの人が同じように悩んでいるサインです。
では、比較や失敗から自己嫌悪につながる具体的なパターンを一緒に見ていきましょう。
学校生活での比較と失敗
学校は、成績や順位がはっきり出る場所です。
そのため友達と比べて落ち込んだり、ちょっとした失敗を引きずったりしやすく、「自分はダメだ」と自己嫌悪につながりやすい場面でもあります。
パターン① 比較から自己嫌悪へ
比較する:「あの子はいつも成績がいいな…」
落ち込む:「自分はまた平均点以下だ…」
自己嫌悪:「やっぱり自分は勉強ができない人間なんだ」
このように、本来なら『点数が違った』というだけの事実なのに、それを『自分の価値』と結びつけてしまうと、強い自己嫌悪につながります。
パターン② 失敗から自己嫌悪へ
失敗する:「授業で答えを間違えちゃった…」
落ち込む:「クラスのみんなに笑われたかも…」
自己嫌悪:「自分なんて発表しない方がいい」
テストや発表での失敗は誰にでもあることです。
けれど、中高生は周囲の目を強く意識するため、その分ダメージも大きくなりがちです。
本来なら『たまたま答えを間違えた』だけの出来事なのに、それを「自分は無価値だ」という思い込みにつなげてしまうと、自己嫌悪が深まってしまいます。
友達関係やSNSでの比較と失敗
友達とのやり取りやSNSは楽しい反面、自己嫌悪につながりやすい場面でもあります。
ここでは、SNSや人間関係で起こりやすい流れを見ていきましょう。
パターン① 比較から自己嫌悪へ
比較する:「友達の投稿、いいねが100件もついてる…」
落ち込む:「自分の投稿は10件しかない…」
自己嫌悪:「やっぱり自分は人気がないんだ」
SNSは『いいね』やフォロワー数など数字で比べやすいため、劣等感や自己嫌悪が強まりやすい場所です。
本来なら『いいねの数が違う』だけのことなのに、それを『自分には価値がない』と結びつけてしまうと、気持ちがどんどんしんどくなってしまいます。
パターン② 失敗から自己嫌悪へ
失敗する:「DMの返事を忘れてしまった…」
落ち込む:「友達に嫌われたかも…」
自己嫌悪:「自分は人間関係をうまく作れない」
ほんの些細なやり取りの行き違いでも、「関係が壊れた」と不安に思いやすいのが思春期の特徴です。
本来なら『返事を忘れた』というだけのことなのに、『自分が悪いから嫌われる』と結びつけてしまうと、自己嫌悪が深まってしまいます。
友達関係やSNSのやり取りに不安を感じるときは、こちらも参考にしてください。
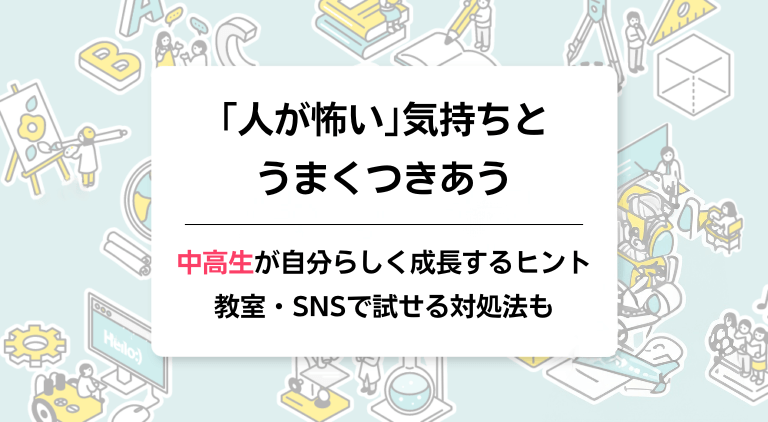
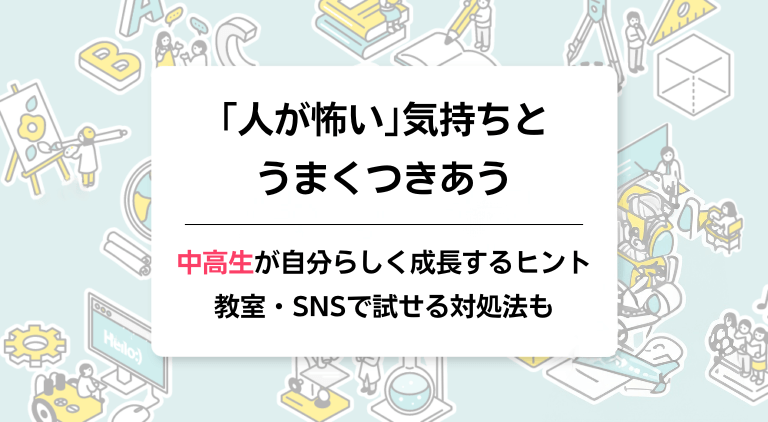
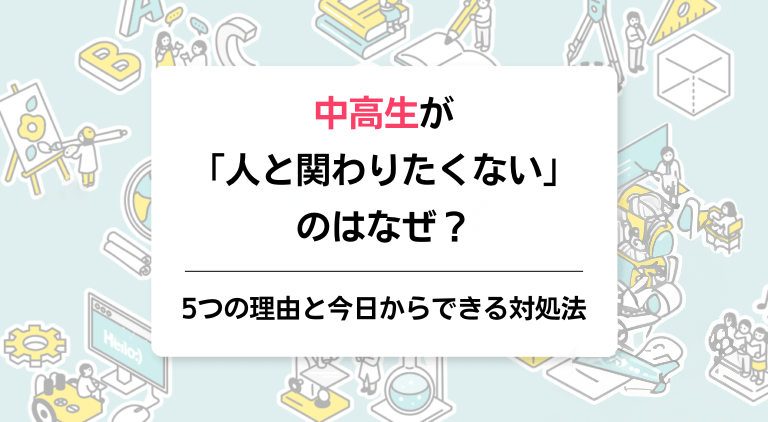
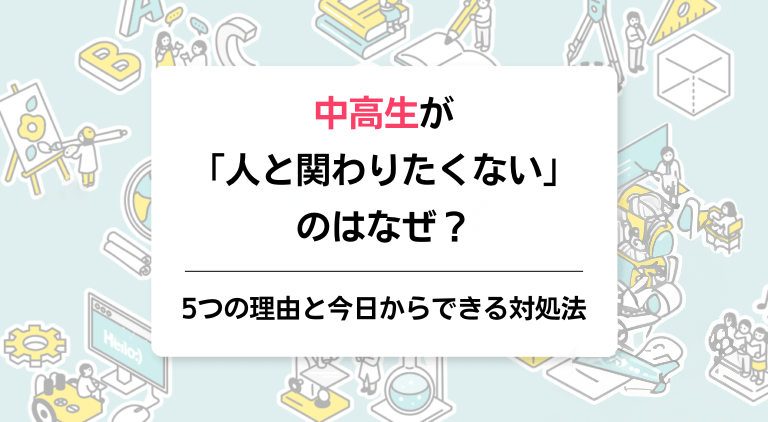
家庭での比較や失敗
家庭は安心できる場所である一方で、親や兄弟姉妹、親戚とのやり取りが自己嫌悪のきっかけになることもあります。
とくに『比べられる』『期待に応えられない』と感じると、自分の存在そのものを否定してしまいやすくなります。
パターン① 比較から自己嫌悪へ
比較される:「お兄ちゃんは優秀なのに」
落ち込む:「自分は全然ダメだって思われてる…」
自己嫌悪:「やっぱり自分には価値がないんだ」
家庭内や親戚からの比較は、本人の努力だけではどうにもならない部分が多いため、自己嫌悪につながりやすいのです。
『愛されない存在』と思い込んでしまうこともあり、気持ちのダメージが大きくなる傾向があります。
パターン② 失敗から自己嫌悪へ
失敗する:「今日も家の手伝いを忘れてしまった…」
落ち込む:「またお母さんを怒らせちゃった…」
自己嫌悪:「自分は役に立たない子だ」
家庭での小さな失敗も、繰り返すうちに『存在そのものがダメ』という感覚につながってしまうことがあります。
特に親からの期待が強いと、「応えられない自分はダメだ」と思い込み、自己嫌悪の悪循環に陥りやすくなります。
自己嫌悪をそのままにするとどうなる?



自己嫌悪なんて、時間が経てば自然に消えるでしょ



みんなも感じてることだから、大丈夫
そう思って、つらい気持ちをそのままにしていませんか?
確かに、自己嫌悪は誰にでもある自然な感情です。
一時的なものなら、時間とともに和らぐこともあります。
でも、つらい気持ちをそのままにしてしまうと、心や体、そして日常生活にも影響が出てきてしまいます。
最初は「ちょっと落ち込んだだけ」だったのに、いつの間にか学校に行くのがつらくなったり、友達と会うのが怖くなったり、将来のことを考えられなくなったり。



でも、自分の気持ちくらい自分でなんとかしなきゃ
と思うかもしれません。
しかし、一人で抱え込むことで、かえって状況が悪くなることもあります。
ここでは、自己嫌悪をそのままにするとどんなことが起こりやすいのかを具体的に見ていきます。
つらい気持ちは一人で抱え込まず、早めに向き合うことが大切です。
自分を責めすぎてしんどくなる
最初は「ちょっと反省しよう」と思っただけだったのに、気づけば自分を責める言葉が止まらない―そんなことはありませんか?
自己嫌悪をそのままにしていると、自分への攻撃がどんどんエスカレートしてしまいます。
最初は「なんでできないんだろう」くらいだったのが、「自分なんて全部ダメだ」「生きている意味がない」という極端な考えに変わってしまうこともあります。
テストでミス → 「次は頑張ろう」ではなく「やっぱり自分は頭が悪い」「勉強しても無駄」
部活で負ける → 「練習不足だった」ではなく「チームに迷惑をかける自分はいない方がいい」
友達とのトラブル → 「話し合えばいい」ではなく「自分は人と関われない欠陥人間だ」
こうして自分を必要以上に攻撃し続けると、心がどんどん疲れてしまいます。


その結果、勉強に集中できなくなったり、好きだったことも楽しめなくなったり、何をするにも「どうせ失敗する」と思うようになってしまいます。
気持ちのアップダウンが激しくなる
朝は「今日は頑張るぞ!」と思っていたのに、午後には急に涙が出てきたり、ちょっとしたことでイライラが爆発したり…そんな経験はありませんか?
自己嫌悪をそのままにしていると、感情のコントロールが難しくなり、気持ちの波が大きくなってしまいます。
些細なことで怒りっぽくなる→友達の何気ない一言にカチンときてしまう
急に涙が出やすくなる→授業中や電車の中で、理由もなく泣きそうになる
不安で落ち着かない→「嫌われたかも」「失敗したらどうしよう」と常に心配
極端に元気な時と落ち込む時の差が激しい
感情が不安定だと、友達や家族との関係もギクシャクしやすくなります。
その後に「なんであんなこと言っちゃったんだろう」と後悔して、また自己嫌悪につながってしまうこともあります。
やる気がなくなってしまう



どうせ自分なんか…



やっても意味ない…
そんな言葉が心に浮かんでしまうことはありませんか?
自己嫌悪をそのままにしていると、少しずつ気持ちのエネルギーが減ってしまい、何かをする気力もわかなくなることがあります。
最初は「今日は宿題やりたくないな」くらいの気持ちだったのに、だんだん「どうせできない」「頑張っても意味がない」と思うようになり、小さな挑戦すら避けるようになってしまいます。
宿題を始める前から「できない気がする」と机に向かわない
体育祭や文化祭に「出ても意味がない」と参加したがらない
新しいことに「失敗したら嫌だ」と挑戦しなくなる
友達からの誘いを「迷惑かけるかも」と断ってしまう


やる気がなくなると、『何もしない → 何もできない自分に見える → さらに自己嫌悪 → もっとやる気がなくなる』といった悪循環に陥りやすくなります。
特に気をつけたいのは、好きだったことまで楽しめなくなるとき。
ゲームも、音楽も、友達と遊ぶことも「どうでもいい」と感じるようになったら、それは心がかなり疲れているサインです。
無理に頑張らなくてもいいですが、放っておかずに、信頼できる人に気持ちを話してみることが大切です。
体や心に影響が出る



最近、なんだか体の調子がよくないな



眠れない日が続いている
そんなことはありませんか?
実は、自己嫌悪による心の疲れは、体にもいろいろなサインとして現れることがあります。
心と体はつながっているので、心が疲れると体も一緒に疲れてしまいます。
「気持ちの問題だから」と思っていても、体は正直にSOSを出してくれているのです。
なかなか眠れない、または眠りが浅い
食欲がわかない、または食べすぎてしまう
頭痛や腹痛が続く
朝起きるのがつらい
いつも体がだるい感じがする
集中力が続かない
楽しいことを想像できない
人と会うのがめんどうになる
ちょっとしたことで不安になる
(参考:厚生労働省「こころもメンテしよう~若者を支えるメンタルヘルスサイト~」)
これらは『気のせい』や『甘え』ではありません。
心が「少し休憩が必要だよ」と伝えてくれているメッセージです。
一人で我慢せず、保健室の先生や家族、信頼できる人に話してみましょう。
自分の価値を見失う



自分なんて何をやってもダメ



どうせ失敗する
そんな気持ちになったことはありませんか?
自己嫌悪が長く続くと、自分の存在そのものに価値を感じられなくなってしまうことがあります。
最初はちょっとした「自分はダメだな」という気持ちでも、それが続くと「自分には何も価値がない」と思い込んでしまい、これまでの努力や良いところが見えなくなってしまいます。
「どうせ何をやっても失敗する」と夢や目標を諦めてしまう
「自分なんかいない方がいい」と考えてしまう
「誰も自分のことなんて必要としていない」と思い込む
将来のことを考える気力がなくなる
こうした状態はとてもつらいものですし、放っておくと悩みが深刻になってしまいます。
もし「自分には価値がない」と感じたら、それは心が限界に近づいているサインです。
そんなときは一人で抱え込まず、信頼できる人や相談先を頼ってください。
自己嫌悪でしんどい気持ちを軽くする5つの工夫
ここまで、自己嫌悪がどんな気持ちなのか、そしてそのままにするとどんな影響があるのかを見てきました。



やっぱり自己嫌悪ってよくないんだ



自分もこのままじゃ危ないかも…
と不安に感じた人もいるかもしれません。
同時に



この苦しい気持ちから抜け出したい



自己嫌悪をなくしたい
と思った人もいるのではないでしょうか。
その気持ち、とてもよくわかります。
自分が嫌になると、毎日が本当にしんどいですよね。
でも、自己嫌悪の気持ちをすぐに消すことは、なかなか難しいのが実際のところです。
だからこそ、少しずつ気持ちを切り替える工夫をしていくことが大切です。
その小さな積み重ねが、心をだんだんと軽くしてくれます。
ここからは、しんどい気持ちをやわらげるための『5つの工夫』を紹介します。
全部やらなくても大丈夫。
まずは「何かやってみようかな」と思えた自分を、ぜひ褒めてあげてください。
そこから、できそうなことを一つ、自分のペースで試してみましょう。
① モヤモヤを紙に書き出してみる


自己嫌悪で頭の中がぐるぐるしているときは、その気持ちを『外に出す』方法があります。
アメリカの心理学者スティーブン・ヘイズ博士が提唱した『アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)』でも、頭の中にあるモヤモヤした気持ちを紙やスマホに書き出すだけで、心が少し楽になると考えられています。
(松川 昌憲「思考からの脱却 ─聞き分けよ、さらば驚かん」日本心理学会 心理学ワールド105号 2024年)
1. ノートやメモ用紙、またはスマホのメモアプリを用意する
2. 浮かんでくる気持ちや言葉を、そのまま短く書く
例:「失敗ばかり」「友達に嫌われそう」「勉強できない」
3. 思いついたことを止めずに、箇条書きでどんどん出す
時間は3分くらいで十分。長く考えすぎなくてOK
書いたあと、その横に「本当にそう?」「こんな一面もある」とひとこと加えてみる
例:「勉強できない」 → でも数学は少しずつ伸びてる」
「友達に嫌われそう」→「本当に?昨日は普通に話してた」
完璧にまとめる必要はなし。大事なのは「頭の中から外に出すこと」
頭の中だけで考えていると『ダメな自分』がどんどん大きく見えてしまいます。
でも、文字にして外に出すと「こんなことを考えていたんだ」と客観的に見られるようになり、自分を責める気持ちをやわらげやすくなります。
まずは、今頭に浮かんだネガティブな単語を1つだけ、スマホのメモ帳に書いてみましょう。
『しんどい』『ダメ』、それだけでも大きな一歩です。
② 小さな成長を探してみる
自己嫌悪が強いときは、『できなかったこと』ばかりに目がいってしまいがちです。


そんなときにおすすめなのが、『小さな成長』を探すこと。
ほんの少しでも『昨日より進んだ』と思えることを見つけると、自分を責める気持ちが和らぎます。
1. その日の終わりに『今日できたこと』を1つ思い出す
例:授業中に解いた問題が正解だった/昨日より早く宿題に取りかかれた
2. 思いついたことをノートやスマホにメモする
3. 前の日と比べて「少しでも進んだ」と思えたらOK
「できなかったこと」ではなく「できたこと」に焦点を当てる
成果は大きくなくてもいい(1問正解できた、1ページ読めた、友達に声をかけられたなど)
毎日書き出すと、「自分にもちゃんとできることがある」と実感できる
小さな成功を積み重ねていくことで、「どうせ自分はダメ」という思い込みから少しずつ抜け出すことができます。
③ 自分にやさしい言葉をかける
自己嫌悪が強いときは、「自分はダメだ」「最低だ」といった言葉を自分に向けてしまいがちです。
でも、人に同じことを言われたら、とてもつらいですよね。
アメリカの心理学者クリスティーン・ネフ博士は、落ち込んだときや失敗したときに『自分を責めるのではなく、自分に対して思いやりをもつ』という考え方を提唱しました。
これは『セルフ・コンパッション』と呼ばれていて、研究でも心を元気にする効果があることがわかっています。
(有光 興記『セルフ・コンパッションと「あるがまま」』日本心理学会 心理学ワールド87号 2019年)
1. 自分を責める言葉が浮かんだら、意識してやさしい言葉に置き換える
例:「自分はダメだ」→「今日は疲れてたけど、よく頑張った」
2. 過去に友達や先生から言われて嬉しかった言葉を、自分に向けて言ってみる
3. 声に出すのが恥ずかしければ、心の中やノートに書くだけでもOK
『友達を励ますつもりで』自分に声をかけると自然にできる
一度で考え方は変わらなくても、繰り返すうちに心がやわらいでいく
責める言葉を『禁止する』必要はなし。出てきたら『やさしい言葉に変える』で十分
小さなやさしさの積み重ねが、自己嫌悪のループを断ち切る一歩になります。
もしやさしい言葉が思いつかなければ、まずは深呼吸して、『大丈夫』『よく頑張ったよ』と心の中でつぶやいてください。
④ 気持ちを話せる相手を見つける


自己嫌悪でしんどいときに大切なのは、一人で抱え込まないことです。
「こんなこと話していいのかな」と思うかもしれませんが、誰かに気持ちを打ち明けるだけで心が軽くなることがあります。
1. 信頼できる家族・友達・先生などを思い浮かべ、話す相手を決める
2. いきなり全部を話さなくてもOK。小さなことから伝える
例:「最近ちょっと落ち込みやすいんだ」「授業で発表するとき緊張する」
3. 直接言いにくければ、SNSやメモで伝えるのもアリ
完璧に伝える必要はない。『少しだけ打ち明ける』でも十分
相談先を1人に絞らず、複数持っておくと安心
スクールカウンセラーや専門機関に話すのも立派な選択肢
友達にちょっとした不安を話すだけでも、「自分だけじゃない」と思えて気持ちが楽になることがあります。
先生やカウンセラーなら、具体的なアドバイスや支援につながることもあります。
一人で抱え込むより、少しでも人と分かち合うこと。
それが自己嫌悪の悪循環を断ち切るきっかけになります。
⑤ いつもとちょっと違う環境にしてみる


自己嫌悪で気持ちが重いときは、環境を少し変えることも役に立ちます。
いつもと同じ場所・同じ習慣のままだと、頭の中のぐるぐるから抜け出しにくいことがあります。
勉強する場所を変えてみる(リビング/図書館/カフェなど)
SNS通知をオフにする、スマホを別の部屋に置いておく
散歩に出る・好きな音楽を聴くなど、『環境+行動』をセットで変える
大きく変える必要はなし。『いつもとちょっと違う』だけでOK
無理に続けなくて大丈夫。『合わなければ戻す』くらいの柔軟さが大切
学校そのものがつらいときは、フリースクールや通信制高校など外の学び場を検討するのも選択肢の一つ
小さな変化でも、気持ちは意外と切り替わります。
「今日は図書館で勉強してみよう」「スマホを30分置いて散歩に行こう」など、すぐできる工夫から始めてみましょう。
もっと気持ちを切り替える方法を知りたい人は、こちらの記事も参考にしてください。
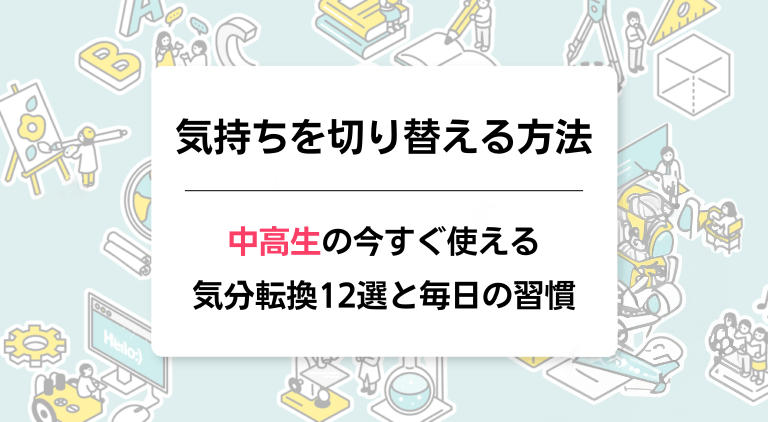
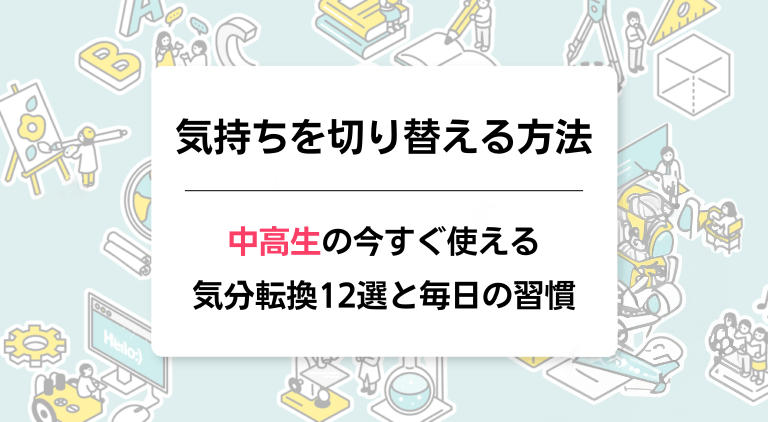
どうしてもつらいときは、ここに相談してみよう
自己嫌悪の気持ちが強くて「もう限界かもしれない」と感じたとき、ひとりで抱え込む必要はありません。
すぐに相談できる電話やチャットの窓口があります。
無理のない範囲で、少しだけでも話してみてください。
【24時間子どもSOSダイヤル】0120-0-78310
【チャイルドライン】0120-99-7777(チャット相談あり)
【子どもの人権110番】0120-007-110(LINE・メール相談あり)
【親子のための相談LINE】https://kodomoshien.cfa.go.jp/no-gyakutai/oyako-line/
【まもろうよ こころ】https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
Q&A|自己嫌悪についてよくある質問
- 自己嫌悪って、みんなもするもの?
-
はい。自己嫌悪は特別なことではなく、思春期の多くの人が経験します。
たとえば、テストで思うようにいかなかったときに「自分は勉強ができない」と思ってしまったり、友達のSNSを見て「自分は劣っている」と感じてしまうことは誰にでもあります。
大人になっても同じように悩む人は多いので、「自分だけおかしい」と考えなくても大丈夫です。
- 劣等感と自己嫌悪ってどう違うの?
-
劣等感は『人と比べて落ち込む気持ち』、自己嫌悪は『落ち込んでいる自分を嫌いになる気持ち』です。
たとえば、友達より点数が低くて「自分は勉強が苦手だな」と感じるのは劣等感です。
そのあと「そんな自分はダメだ」と責めてしまうのが自己嫌悪です。詳しくはこちらで解説しています。
劣等感とのちがい - 自己嫌悪に陥るのは悪いこと?
-
悪いことではありません。
むしろ「うまくやりたい」「成長したい」という前向きな気持ちの裏返しでもあります。
ただし、そのままにしておくと「どうせ自分はダメだ」と考えやすくなり、勉強や友達との関係に影響することがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
自己嫌悪をそのままにするとどうなる? - 気持ちを切り替えたいけど、どうしてもできないときは?
-
無理に「前向きにならなきゃ」と思わなくても大丈夫です。
「今はしんどいんだ」と気持ちを認めるだけでも心が少し楽になります。
それでも苦しいときは、信頼できる人に話したり、相談窓口を利用するなど、外の力を借りてみてください。気持ちを軽くする工夫はこちらで紹介しています。
自己嫌悪でしんどい気持ちを軽くする5つの工夫 - 自己嫌悪が長く続いたらどうなる?
-
自分を責め続けることで、勉強へのやる気がなくなったり、友達に会うのが怖くなったり、体調に不調が出ることもあります。
「ただの落ち込み」と思ってそのままにすると悪循環に陥ることがあるので、注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
自己嫌悪をそのままにするとどうなる? - 誰に相談したらいいの?友達?家族?先生?
-
誰でもOKです。それぞれに良さがあります。
友達:同じ目線で共感してくれる
家族:日常生活の中で支えてくれる
先生:学校生活の工夫や支援につながりやすい迷ったら『一番話しやすい人』からで大丈夫。
複数の相談先を持っておくとさらに安心です
まとめ|自己嫌悪とうまくつき合うために
自己嫌悪は、思春期の中高生なら誰もが経験する自然な心の反応です。
「自分だけダメなんだ」と思い込む必要はありません。
ただし、自己嫌悪をそのままにすると心や体、学校生活に影響してしまうことがあります。
だからこそ、少しずつ気持ちを軽くする工夫が大切です。
紙やスマホに気持ちを書き出す
小さな成長を探してみる
自分にやさしい言葉をかける
信頼できる人に話す
環境をちょっと変えてみる
どれも『すぐにできる小さな工夫』です。
一人で抱え込まず、まずはできそうなことから試してみてください。
そして、もしどうしてもつらいときは、地域の相談窓口や専門機関を利用するのも大切な選択肢です。
あなたの気持ちを理解して支えてくれる人は、必ずいます。
【ID学園】『自分で決める力』を支える夢教育
自己嫌悪が強いとき、「どうせ自分はダメだ」と思い込み、自分の意見や選択に迷ってしまうことがあります。
そんなときに大切なのが、『自分を理解して、自分で選ぶ力』 を育てること。
ID学園の『夢教育』では、先生との面談を通して、まずは自分の得意・好き・大切にしたいことを見つけるところから始まります。
そこから進路や挑戦を 『自分で決める経験』 を重ねていくことで、『比べられる』ではなく『自分で選ぶ』感覚を育てることができます。
これは、自己嫌悪に悩みやすい中高生にとって、自分らしく進む一歩につながります。
小さな自己決定の積み重ねは、自己否定ではなく『前向きに進む自分』へとつながっていきます。