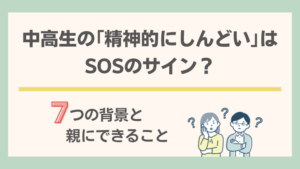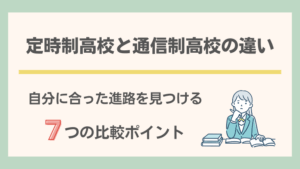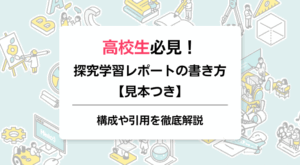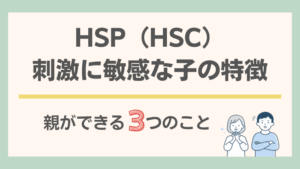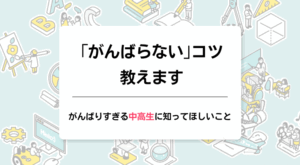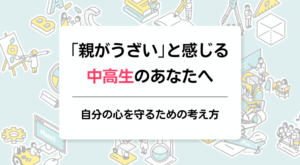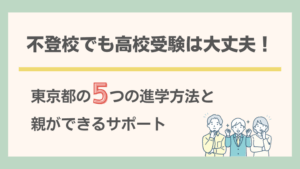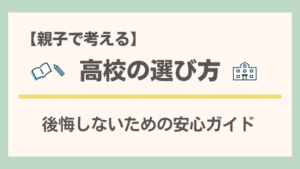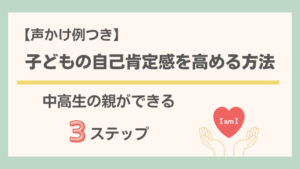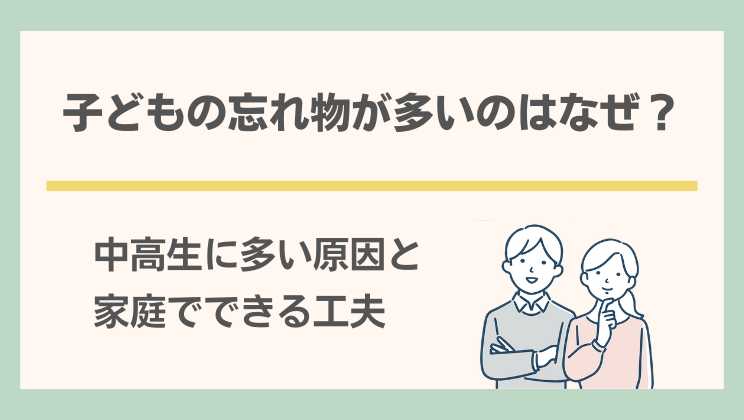
「毎日、何か忘れ物をしてしまう」
「何度注意しても直らなくて困ったな…」
こんなお子様の姿に、親としてどう対応すればいいのか悩んでいませんか。
特に中高生になると、提出物・教科書・体操服や部活動の道具など、持ち物はぐんと増えます。
忘れ物が続くと、成績や内申、進路にまで影響するのではと不安になる親御さんも少なくありません。
「もしかして私の育て方のせい?」「性格の問題?」とご自分を責めてしまうこともあるのではないでしょうか。
ですが、忘れ物は『怠け』や『しつけ不足』だけで説明できるものではなく、成長段階や環境によって誰にでも起こり得ることです。
忘れ物が多い背景には、成長段階にともなう脳の発達や生活習慣の乱れ、一時的な体調や心理的な影響、さらには発達特性(ADHDなど)といった要因が隠れていることもあります。
この記事では、中高生に多い『忘れ物の原因』と『家庭でできる工夫』をわかりやすく解説します。
お子様が自信を取り戻し、安心して学校生活を送るためのヒントを、一緒に見つけていきましょう。
忘れ物が多いのは『よくある困りごと』

また忘れ物をしてきたの?
そんなやりとりが日常になってしまい、親も子も疲れてしまうことは少なくありません。
実は、忘れ物は中高生に多く見られる『よくある困りごと』です。
中学校・高校では提出物や教科書、体操服、部活動の道具など持ち物の種類が一気に増えます。
授業や活動ごとに準備が必要になるため、大人が思う以上に子どもには大きな負担です。
忘れ物が続くと、授業の遅れや成績への影響、内申点の低下、さらには進路選択にまで影響が及ぶ可能性があります。
そのため、お子様だけでなく保護者も不安や悩みを抱えやすいのです。
宮城県が行った調査では、中学生の22.8%が「持ち物の忘れ物が多い」、22.9%が「宿題や課題ができていないことが多い」と答えています。
高校生でも17%前後が同じように回答しており、忘れ物は決して特別なことではなく、多くの子どもが直面する“よくある困りごと”だと分かります。
(宮城県保健福祉部「小学生・中高生の生活実態に関する アンケート調査報告書」令和5年3月)
忘れ物が多い原因とは?



どうしてうちの子はこんなに忘れ物が多いのだろう?
そう感じる親御さんは少なくありません。



性格の問題かな?
私の育て方のせい?
と考えてしまうこともあります。
しかし、忘れ物が多い背景には、いくつもの要因が複雑に関わっています。
たとえば
思春期特有の生活リズムの乱れ
脳の発達段階による集中力・記憶力の不安定さ
一時的な体調や心理的な影響
発達特性(ADHDなど)に関連する場合
つまり、忘れ物は性格や努力の不足で片づけられるものではなく、成長過程で自然に見られる現象でもあるのです。


一方で、忘れ物が何度も繰り返し続く場合には、発達特性が関わっている可能性も。
その場合は、環境やサポートの工夫が必要になることもあります。
ここからは、大きく分けて3つの視点について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 成長段階や生活習慣
② 注意力や記憶力の一時的な低下
③ 発達特性(ADHDなど)との関連
成長段階や生活習慣によるもの
思春期は、体や心の成長が大きく進むと同時に、脳もまだ発達途中です。
計画や整理に関わる脳の前頭前野という部分が大人に比べて未熟
→注意力や記憶のコントロールが不安定になりやすい
夜更かしやスマートフォンの長時間利用などで睡眠時間が不足
→翌日の集中力や記憶力が落ち、忘れ物が増えやすくなる
朝なかなか起きられない、朝食を抜いて登校する、といった習慣の乱れ
→注意力を低下させる原因
部活動や塾などで帰宅が遅くなり、疲れがたまる
→「明日の準備をする余裕がない」という状況も起こりがち
食事や運動のリズムが乱れる
→心身のエネルギーが不足し、整理整頓や持ち物管理といった日常の習慣が続きにくくなる



さらに、心理的な不安や緊張も忘れ物の原因になります
たとえば、テスト前の焦りや人間関係のストレスが強いと、注意が散漫になり『うっかり』につながることも少なくありません。
このように、生活習慣や心理的な要因そのものが『忘れ物をしやすい環境』をつくってしまうのです。
忘れ物が多いと『性格』や『だらしなさ』と誤解されやすいですが、実際には成長段階や生活リズムの乱れと深く関わっているケースが多く見られます。
注意力や記憶力の一時的な低下


中高生の脳はまだ発達の途中にあり、注意力や記憶力は大人ほど安定していません。
そこに生活習慣や心理的な要因が重なると、一時的に集中力が落ちたり、記憶が不安定になったりすることがあります。
久留米大学の内村直尚氏によると、睡眠不足や生活リズムの乱れは日中の集中力や学習に影響を与えるだけでなく、深い睡眠が減ることで記憶の定着や脳の休養にも支障が出るとされています。
(内村直尚「思春期の睡眠障害」小児保健研究 第80巻第3号 2021年)
たとえば、睡眠不足や体調不良で頭がぼんやりしているとき、課題をカバンに入れたかどうかを思い出せず、提出物を忘れてしまうことがあります。
試験前の緊張や友人関係の不安など、心の状態が影響することも少なくありません。
また、持ち物の数が多い日には「今日は体操服に加えて美術の道具も必要」というように、複数のことを同時に覚えておく必要があります。
思春期の子どもにとっては、この『注意の切り替え』や『短期記憶の維持』が負担となり、忘れ物につながるのです。
このような一時的な忘れ物は、誰にでも起こり得る一般的な現象です。
だからこそ、忘れ物が続いたときに『性格のせい』と決めつけず、生活リズムや心理的な要因にも目を向けることが大切です。
発達障がい(ADHDなど)との関連


忘れ物が『ときどき』ではなく『何度も続いている』ときには、発達特性が関係している場合もあります。
ADHD(注意欠如・多動症)の特性
『注意の切り替えが苦手』『短期記憶に弱さがある』といった特徴がよく見られる
そのため、提出物や持ち物を忘れてしまうことが続けて起こりやすくなる
(参考:国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所「こころの情報サイト」)
こうした忘れ物は、子どもや親の努力不足が原因ではありません。
脳の働き方による特性として表れているものであり、努力やしつけでは解決できない課題として理解する
また、診断を受けていなくても、傾向として表れることがあります。
「忘れ物が多いのは私のせい…」と自分を責めるのではなく、困っている状況を受け止め、家庭や学校で工夫を取り入れていくことが大切です。
発達障がいについては、こちらで詳しく解説しています。
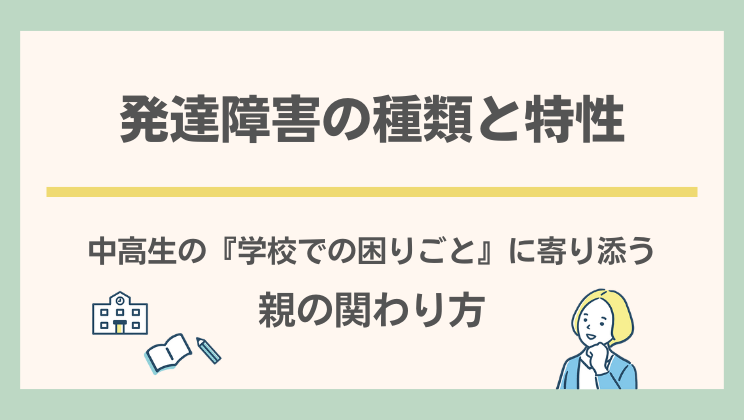
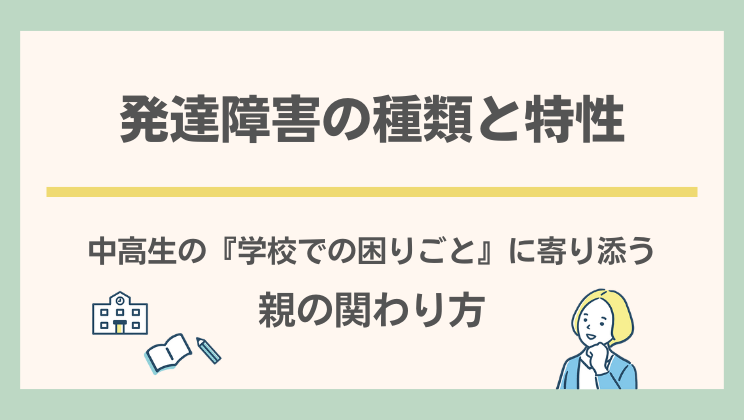
家庭でできる忘れ物対策|4つの工夫
お子様の忘れ物が多いとき、つい



どうしてちゃんとできないの?
と叱ってしまいがちです。
忘れ物が続くと、心配やイライラからつい強めに関わってしまうこともありますよね。
しかし、次のような対応はかえって逆効果になりやすいので注意が必要です。
① 親が先回りして準備する
子どもの自立の機会を奪ってしまう
② 感情的に叱り、人格を否定するような言葉をかける
解決につながらず、自己肯定感を下げてしまう
③ きょうだいや友達と比較する
「自分はできない」という劣等感を生みやすい
お子様の自己肯定感や劣等感については、こちらで詳しく説明しています。
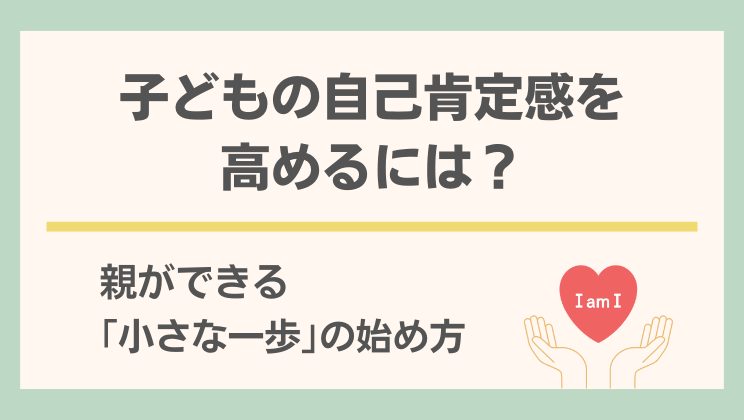
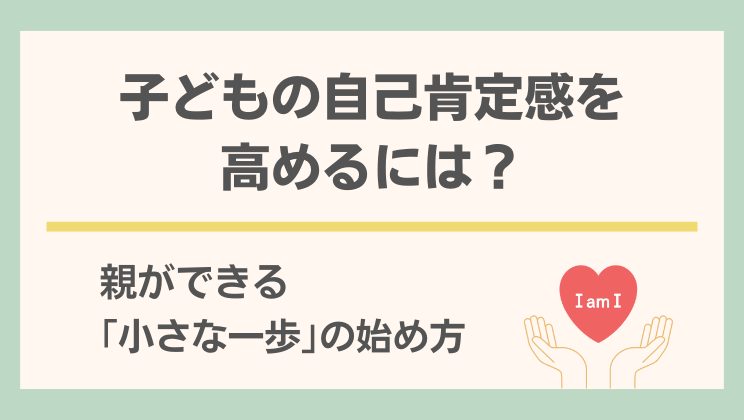
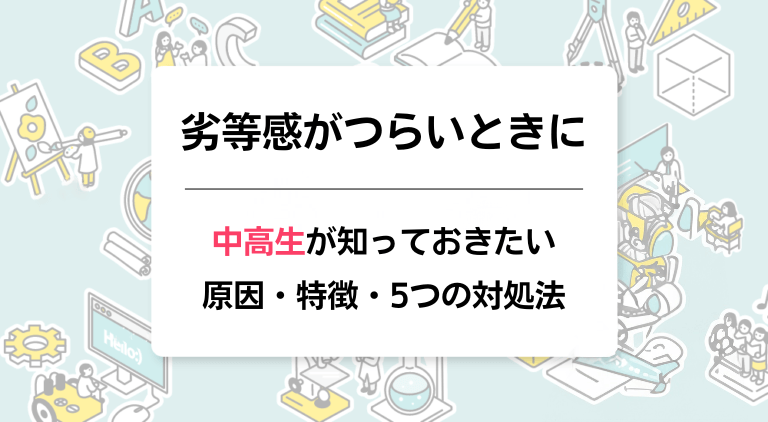
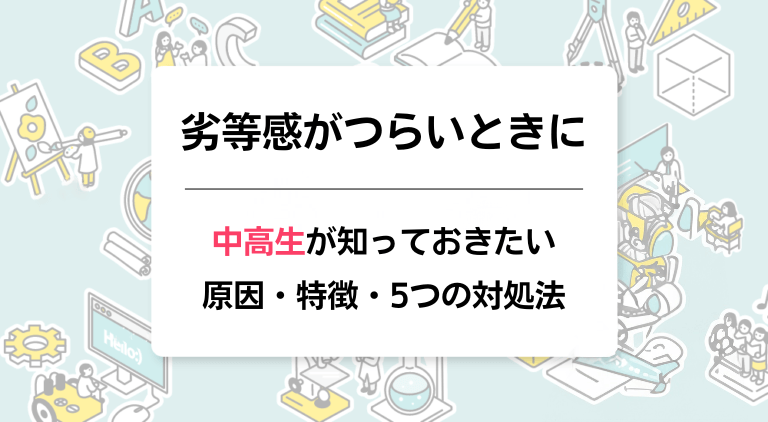



大切なのは、忘れ物を防ぐ仕組みや環境を整え、「自分でできた!」という小さな成功体験を積み重ねていくことです
そうした工夫によって自己肯定感が高まり、生活や学習への前向きさにもつながっていきます。
ここからは、家庭で取り入れやすい具体的な工夫を紹介します。
工夫① チェックリストと視覚的サポート


忘れ物対策の第一歩は、頭の中だけに頼らず 『目で確認できる仕組み』 をつくることです。
チェックリストを活用すると、持ち物を準備する行動が習慣になりやすくなります。
特にADHDなどの特性があるお子様にとって、視覚的に確認できる工夫は大きな助けになります。
玄関や机に『持ち物リスト』を貼る
玄関や机の横など、毎日必ず目に入る場所に持ち物リストを貼っておくと便利です。
「今日は何が必要かな?」と親御さんが声をかけながら一緒にチェックすると、確認が習慣化しやすくなります。
イラストや色分けで直感的に分かりやすくする
文字だけのリストではなく、イラストや色分けを取り入れると、直感的に分かりやすくなります。
たとえば、教科ごとに色を決めてラベルを貼ったり、体操服や美術道具の絵を描いておいたりすると、『パッと見てすぐわかる』仕組みになります。
工夫② 定位置を決める


忘れ物を減らすもう一つのポイントは、持ち物の『置き場所』を決めることです。
決まった場所に戻す習慣がつくと、「あれがない、どこに置いたっけ?」と探す時間が減り、準備がスムーズになります。
これはADHDなど特性に関わらず、どのお子様にとっても効果的な方法です。
教科書や提出物の置き場を決めて『使ったら戻す』を習慣化
教科書や提出物のために棚やファイルを用意し、『使ったら必ず元の場所に戻す』ルールをつくると、探し物が減り、忘れ物防止につながります。
慣れるまでは保護者が一緒に確認してサポートし、習慣がついたら徐々に子ども自身でできるよう促すのがコツです。
玄関に『持ち物置き場』をつくる
玄関の一角に『忘れ物防止ゾーン』をつくって、翌日の持ち物をまとめておきます。
外出前に必ず通る場所なので、出発前に自然と確認できます。
カゴやボックスを使って『ここに置いたら忘れない』という仕組みをつくると、安心して登校準備ができます。
工夫③ タイマーやスマホを活用


忘れ物対策には、デジタル機器をうまく取り入れるのも効果的です。
タイマーやスマホのアプリを使うと、親が毎回声をかけなくても、自動的に知らせてくれる“サポート役”になります。
お子様が自分で管理している感覚を持てるので、自立にもつながります。
スマホのリマインダー(通知機能)で提出物を通知
提出物や持ち物をあらかじめ登録しておき、指定の時間にアラームや通知で知らせるように設定します。
たとえば、『9時に明日の提出物チェック』とアラームを設定するだけで、忘れ物をかなり減らすことができます。
親御さんと共有カレンダーを使えば、『子どもが登録したリマインダー(通知機能)を親も確認できる』仕組みになり、安心です。
カメラで『提出物をカバンに入れた証拠』を撮る
「カバンにちゃんと入れたかな?」と不安になるお子様には、スマホのカメラで“証拠写真”を撮る方法もおすすめです。
提出物や必要な持ち物をカバンに入れたらパシャッと撮影し、それを後から見返せば『確かに入れた』という安心につながります。
視覚的に確認できるので、記憶だけに頼るよりも効果的です。
工夫④ 夜の準備を一緒にする
忘れ物の多くは、朝の慌ただしさが原因で起こります。
朝は時間が限られていて気持ちも焦りやすいため、必要なものを確認する余裕がなく、うっかり忘れてしまうことがあるのです。


有効なのが『夜のうちに準備をしておく』習慣です。
落ち着いた時間に確認できるので、忘れ物のリスクを大きく減らせます。
前日の夜に持ち物をそろえる習慣づけ
寝る前に、翌日の持ち物をすべてカバンに入れるルールをつくります。
朝は『最終チェック』だけにすれば、安心して1日をスタートできます。
この流れを繰り返すことで、準備そのものが自然と習慣化されていきます。
親と一緒に仕組み化する
最初からすべてをお子様に任せるのではなく、最初は親御さんも一緒にチェックしながら進めるのがおすすめです。
「ここに入れたね」「これで明日の準備はバッチリ」と声をかけることで安心感が生まれ、やる気も高まります。
慣れてきたら徐々にお子様に任せ、自分で準備できるようサポートしていきましょう。
学校との連携でできること
家庭で工夫をしても、忘れ物がなかなか減らないことがあります。
「どうしてできないのだろう…」と親御さんが悩みを抱え込んでしまうと、気持ちも疲れてしまいますよね。
そんなときは、学校と協力して取り組むことも大切です。
先生に相談することで、お子様の様子を共有でき、家庭だけでは気づかなかった工夫やサポートが得られることもあります。
「家庭だけでなんとかしなくては」と思う必要はありません。
「一緒にサポートしてくれる人がいる」と感じられるだけで、気持ちが少し軽くなるはずです。
先生に相談するときのポイント
『忘れ物が多い』と感じても、いざ学校に相談するとなると



こんなことで先生に言ってもいいのかな…
とためらう方も多いのではないでしょうか。
実際、先生に相談してもすぐに状況が改善するとは限りません。
けれども、今の困りごとを学校と共有すること自体が、支援につながる大切な一歩になります。
相談するときは、病名や診断名を伝えることが必要なのではなく、実際にどんな困りごとが起きているのかを具体的に伝えることがポイントです。
たとえば
「提出物は完成させているのですが、カバンに入れ忘れて机の上に置きっぱなしにしてしまいます」
「体操服を準備していても、朝になると持って行き忘れることがあります」
「ノートも教科書も机の上に揃えて置いているのに、カバンに入れるときにノートだけ入れ忘れます」
「持ち物は前日に準備できず、当日の朝に慌てて準備するので忘れてしまうことが多いです」
「部活動の道具を用意しても、玄関に置いたまま学校へ行ってしまうことがあります」



日常で起きていることをそのまま伝えるだけで十分です
診断の有無に関係なく、具体的な行動の情報は先生にとってもわかりやすく、役立ちます。
学校と状況を共有することで、先生も一緒に工夫を考えやすくなり、お子様の安心した学校生活につながっていきます。
学校でお願いできる配慮の例
学校に相談すると、先生に次のようなちょっとした工夫をお願いできることもあります。
提出物があると声かけしてもらう
「今日が提出日だよ」と一言声をかけてもらうだけで、忘れ物を防ぎやすくなります
板書のコピーやプリントを用意してもらう
→ ノートに書き写す途中で抜け落ちてしまうことがあっても、後から確認できる安心材料になります
ロッカーや机の中の整理を一緒に確認してもらう
→ どこに何を入れるかが整理されると、「入れたはずなのに見つからない」といった混乱を減らせます
先生に一度相談しておくだけでも『見てもらえている』という安心感につながり、お子様も忘れ物対策に前向きに取り組みやすくなります。
忘れ物が多い子どもと向き合う親が意識したいこと
忘れ物が続くと、親御さんは



また忘れてる…
どうして直らないの?
とイライラしてしまうこともありますよね。
でも、そのイライラは声のトーンや表情に出てしまい、お子様は敏感にそれを感じ取ります。


大人の感情が無意識のうちに子どもに伝わることを、心理学で『情動伝染』と呼びます。
たとえば
親が怒った口調になると…
お子様は「また叱られるかも」と緊張し、準備に集中できなくなる
親が「なんでできないの!」と苛立っていると…
「自分はダメなんだ」と感じて自己肯定感を下げてしまう
親の慌ただしい雰囲気に飲み込まれると…
さらに忘れ物が増えてしまう
逆に、親御さんが落ち着いた声で「今日はこれを持ったかな?」と確認すると、お子様も安心して準備に取り組めます。
親が安心していること自体が、お子様にとって大きな支えになります。
ここからは、そのために親御さんが心がけたい2つのポイントを見ていきましょう。
親の気持ちを守る
忘れ物が続くと



私の育て方が悪いのでは?



ちゃんとできないのは親の責任?
と、自分を責めてしまう保護者の方も少なくありません。
けれども、忘れ物は親のしつけや努力不足だけで起こるものではなく、成長段階や特性が大きく影響していることがあります。
まずは「これは私のせいではない」と区切りをつけることが大切です。
親が過度に自分を責めて気持ちが不安定になると、その不安は子どもに伝わり、さらに忘れ物が増えてしまうという悪循環に陥りやすくなります。
逆に、親御さん自身が落ち着いて「大丈夫、工夫していけばきっとできるようになる」と安心している姿を見せると、それだけでお子様にとっては心強い支えになります。


学校や専門機関など外のサポート資源を活用することも、弱さではなく前向きな行動です。
相談することで保護者の気持ちも軽くなり、結果的にお子様を支える力につながります。
相談するタイミングに気づく
忘れ物が続いて「家庭だけではもう工夫しきれない」と感じたときが、相談を考えるタイミング
たとえば
忘れ物の回数が多く、生活や学習に大きな影響が出ている
工夫を試しても改善せず、親子で疲れ切ってしまっている
子どもが「どうせ自分はできない」と自信をなくしている
こうした状況が見られたら、信頼できる相談先につなげることが大切です。
学校の先生だけでなく、スクールカウンセラーや地域の子育て相談窓口なども頼れる場所です。
診断がついていなくても、『忘れ物が多い』『集中が続かない』といった困りごとで悩んでいるお子様は少なくありません。
医師や専門家から明確な診断は受けていないけれど、日常生活に支障が出ているグレーな段階として『グレーゾーン』と呼ぶことがあります。
グレーゾーンにいるお子様は、周囲からは『怠けている』『だらしない』と誤解されやすいのですが、実際には本人が努力しても改善しにくい特性が背景にある場合も少なくありません。
だからこそ、診断の有無にかかわらず早めに相談につなげることで、理解や支援を受けやすくなり、安心して過ごせる環境を整えることができます。
なお、『グレーゾーン』についてはこちらで詳しく解説しています。
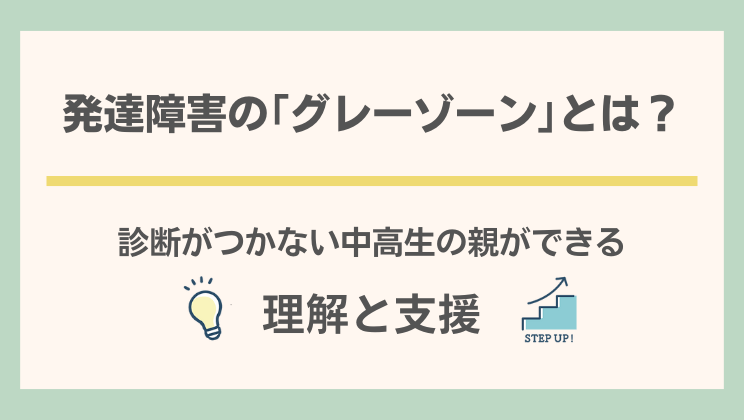
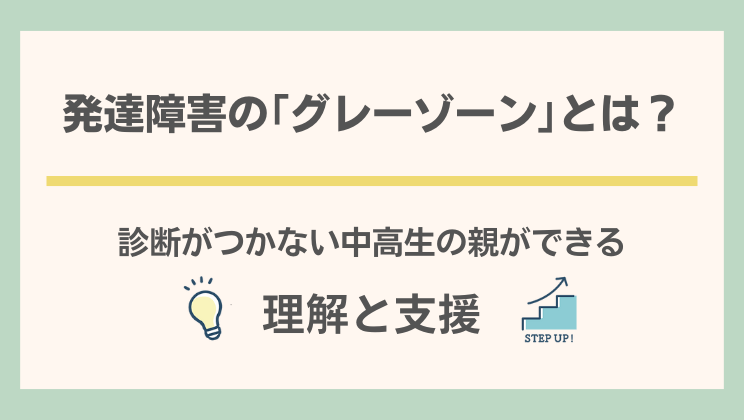
忘れ物についてよくある質問(Q&A)
- 忘れ物が多いのは性格の問題ですか?
-
性格や怠けが原因と考えられがちですが、忘れ物は必ずしも性格だけで説明できるものではありません。
成長段階による脳の発達や生活習慣の乱れ、一時的な体調や心理的な影響、発達特性など、複数の要因が重なって起こることが多いのです。詳しくはこちらをご覧ください。
忘れ物が多い原因とは? - 発達障がいの可能性がある場合はどうすればいいですか?
-
忘れ物が頻繁で、生活や学習に支障が出ている場合には、発達障がいの特性が関係していることもあります。
ただし『忘れ物=発達障がい』とは限りません。
気になる場合は、学校や専門機関に相談することで必要なサポートが受けやすくなります。発達障がいについてはこちらで詳しく解説しています。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
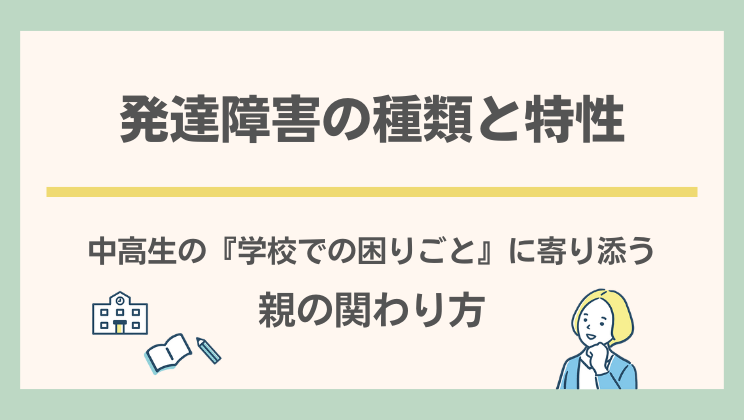 発達障害の種類と特性|中高生の『学校での困りごと』に寄り添う親の関わり方 | 【公式】ID学園高等学校_生… 発達障がいの種類と特性をわかりやすく解説。中高生が学校で直面しやすい困りごとや、親ができるサポートの工夫を紹介します。
発達障害の種類と特性|中高生の『学校での困りごと』に寄り添う親の関わり方 | 【公式】ID学園高等学校_生… 発達障がいの種類と特性をわかりやすく解説。中高生が学校で直面しやすい困りごとや、親ができるサポートの工夫を紹介します。 - 何度言っても忘れ物が減らないときは、叱るべきですか?
-
叱るだけでは効果は少なく、むしろお子様の自己肯定感を下げてしまうことがあります。
大切なのは『仕組みをつくる』こと。
チェックリストや持ち物の定位置を決めるなど、環境を工夫して「自分でできた!」を増やすことが解決につながります。家庭でできる忘れ物の対策はこちらで詳しく説明しています。
家庭でできる忘れ物対策|4つの工夫 - 学校にはどう伝えればいいですか?
-
『忘れ物が多い』という言い方よりも、具体的な行動の様子を伝えると先生に理解してもらいやすくなります。
たとえば「提出物は完成させているのにカバンに入れ忘れることが多い」「体操服を朝よく持って行き忘れる」といった日常の様子です。また、『家ではチェックリストを使っている』など、家庭で工夫してきたことも一緒に伝えると、先生もサポートの仕方を考えやすくなります。
学校への伝え方についてはこちらを参考にしてください。
学校との連携でできること - 忘れ物は成長すればなくなりますか?
-
年齢を重ねることで、生活習慣や自己管理の力がつき、忘れ物が少なくなっていくお子様は多くいます。
特に中高生の時期は脳がまだ発達の途中にあり、注意力や記憶力が不安定になりやすいため、忘れ物は『よくある困りごと』といえます。ただし、成長とともに必ず改善が見られるわけではありません。
発達特性が関係している場合は、大人になっても忘れ物に苦労することもあります。
だからこそ、「そのうち何とかなるだろう」と様子を見るのではなく、今できる工夫や環境づくりを進めることが安心につながります。 - 親はどこまでサポートすればいいですか?過保護になりませんか?
-
サポートは『全部やってあげる』ことではなく、『一緒に仕組みを整える』ことが大切です。
最初は保護者が一緒にチェックしても、慣れてきたら少しずつ任せていくなど、自立を意識した関わり方が望ましいです。 - 忘れ物が多いとき、受診した方がいいのでしょうか?
-
一時的な忘れ物であれば、成長段階で誰にでも見られることで、受診を急ぐ必要はありません。
思春期は脳の発達がまだ途上で注意力が不安定になりやすく、「わかっているのにできない」という状況はよくあることです。ただし、忘れ物が毎日のように続き学習や生活に支障がある場合は、発達相談センターや教育相談窓口などに相談するのも安心です。
診断がなくても利用でき、必要に応じて医療機関を紹介してもらえることもあります。
まとめ|忘れ物を減らす工夫で子どもの安心を支える
ここまで、忘れ物が多い原因や、家庭・学校でできる工夫について見てきました。
忘れ物は『工夫や環境次第で改善できるもの』です。
小さな工夫の積み重ねによって「自分でできた!」という経験が増えれば、お子様の自己肯定感や安心感を育てることにもつながります。
また、家庭だけで抱え込まず、学校や専門機関と一緒に取り組むことで、より安心して支えていけます。
お子様が忘れ物を減らし、自信を取り戻していく姿は、学習や学校生活全体への前向きさにも広がっていきます。
親御さんが安心してサポートできることこそが、子どもにとって最大の支えになるのです。
【この記事のポイント】
忘れ物は「性格や育て方」の問題ではなく、成長段階や発達特性などさまざまな要因が関わっている
叱るよりも、チェックリストや定位置決めなどの仕組みづくりが効果的
親の安心した関わりが、子どもの自信と前向きさにつながる
【ID学園】工夫を活かして自分らしく学べる学校
ID学園では、ICTを活用した学習環境が整っており、忘れ物対策にも役立つ工夫が取り入れられています。
たとえば、Slackを使った課題共有では、「次回の小テスト範囲」「提出物の確認」などが先生からメッセージとして送られるため、生徒は何度でも確認できます。


「一度聞いただけでは忘れてしまう…」というお子様でも、こうした記録が残っていることで安心して取り組めます。
親御さんも一緒に確認できる仕組みがあるため、家庭での声かけやサポートにもつなげやすいのが特徴です。
もし「もう少し詳しく知りたい」「うちの子に合う環境かどうか見てみたい」と思われた方は、ぜひ一度、説明会や個別相談で雰囲気を確かめてみてください。
きっと、お子様が安心して学べるヒントが見つかるはずです。