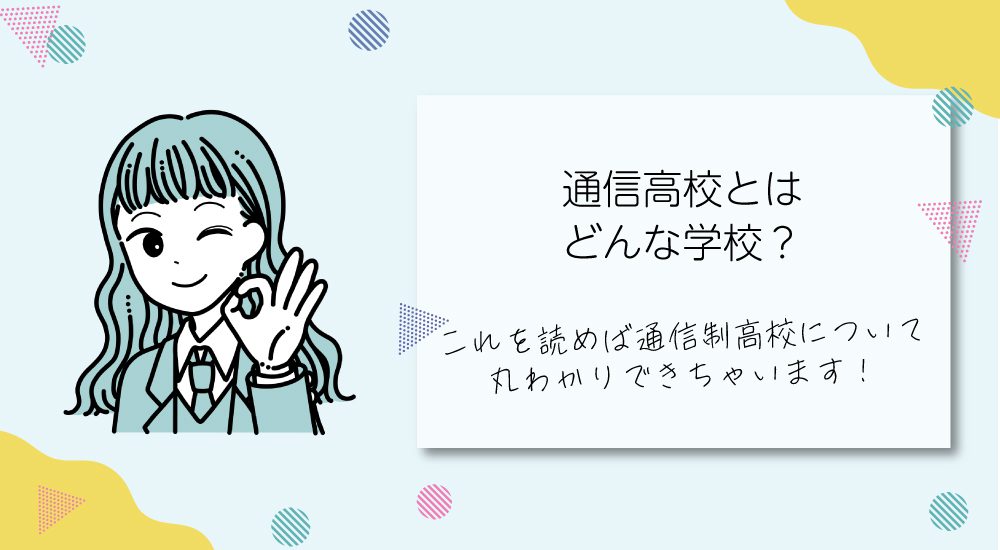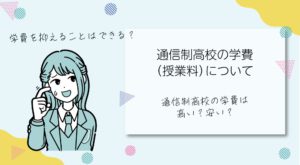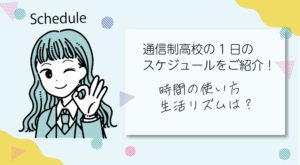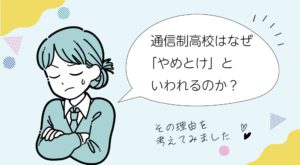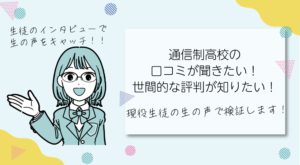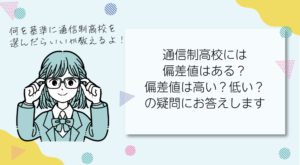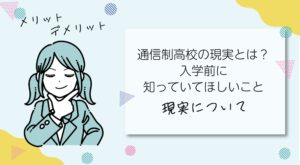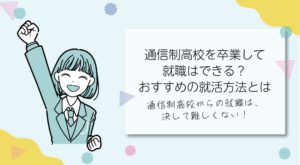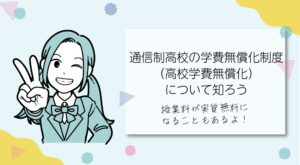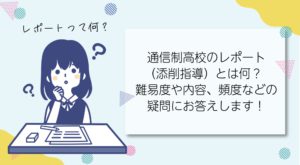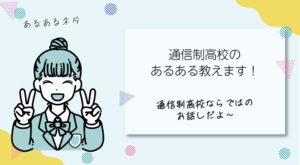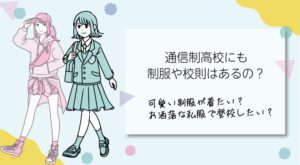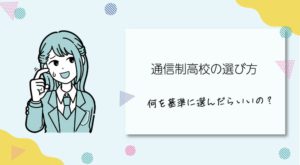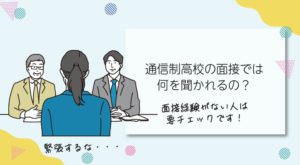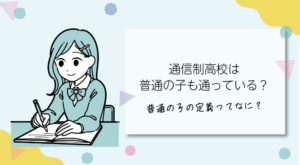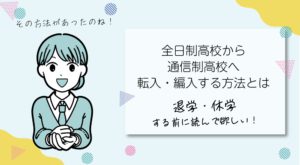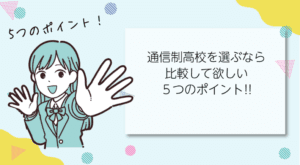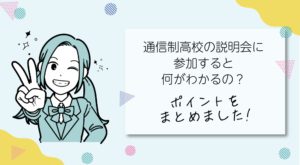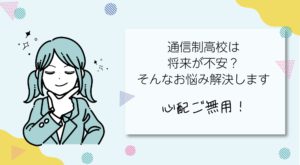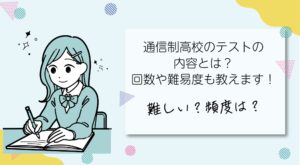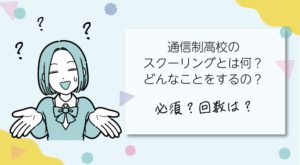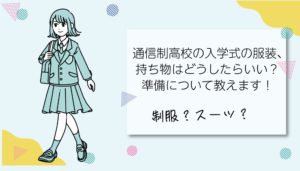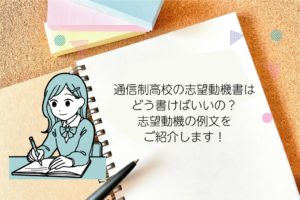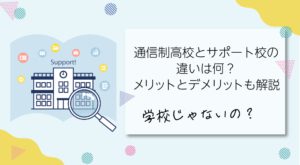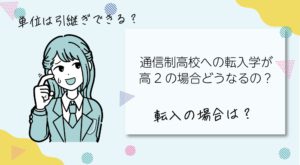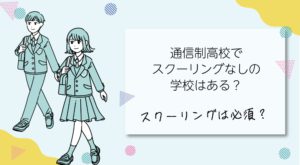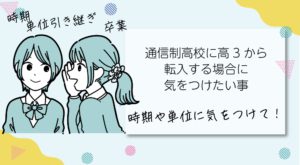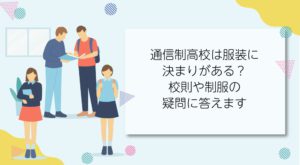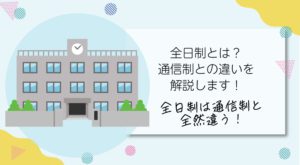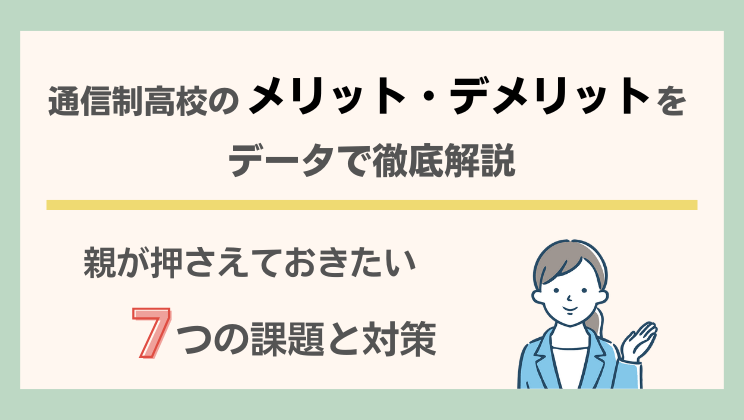
「通信制高校って、自由な反面、デメリットも多いって聞くけれど…本当に大丈夫なのかな?」
お子様の進路を考えるとき、そんな不安を抱く親御さんは少なくありません。
いま、通信制高校で学ぶ生徒は305,221人。
前年度から約1万5千人増え、高校生全体の約9.6%、つまり10人に1人が通信制を選んでいます。
(文部科学省「令和7年度 学校基本調査(速報)」)
かつては“特別な進路”と見られていた通信制ですが、いまや「自分のペースで学びたい」「新しい環境で再スタートしたい」と考える生徒たちに広く選ばれる学びの形になっています。
とはいえ、自由度の高さの裏には「自己能力を求められることもある」「学校やコースによっては、人とのつながりが少なくなる」など、入学前に知っておくべき課題もあります。
この記事では、通信制高校でよく言われる“デメリット”を、最新データや実際の仕組みに基づいて整理します。
さらに、そうした課題をどう防ぎ、どう支援していけるか―親御さんが知っておきたい具体的な工夫やサポート方法も紹介します。
通信制高校の実情を正しく理解することで、「うちの子にはどんな学び方が合っているのか」を見極めやすくなります。
もし入学手続きや制度の流れを知りたい場合は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。
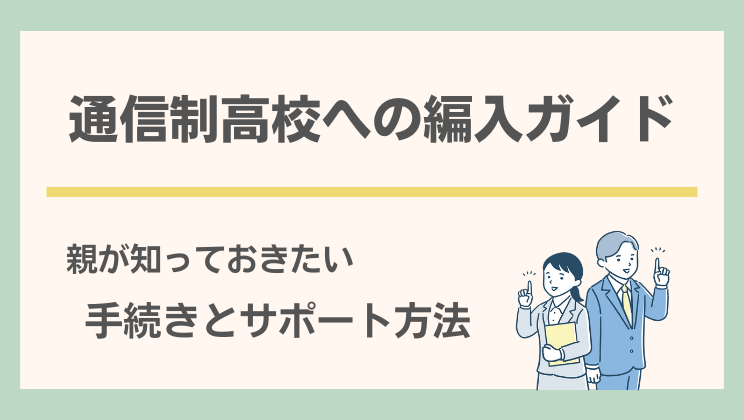
【この記事でわかること】
通信制高校の仕組みと、全日制・定時制との違い
通信制高校でよく言われる7つの“デメリット”とその背景
入学前に知っておきたい注意点と、家庭でできるサポート方法
【向いている人・向いていない人】を見極めるポイント
通信制高校で起こりやすい課題を支えるサポート体制
通信制高校は “新しいスタートの場” であり “自分らしく学び直す場所”
『通信制高校』と聞くと、かつては“特別な学校”という印象を持つ方も少なくありませんでした。
でも、いまは状況が大きく変わっています。
通信制で学ぶ生徒数が年々増加している理由は

集団生活が合わなかった



体調や家庭の事情で通学が難しかった
といった理由だけでなく



自分のペースで学びたい



得意を伸ばしたい
など、前向きな理由で通信制を選ぶお子様が増えていることがあります。
通信制高校の特徴は、時間や場所にしばられず、一人ひとりに合った学び方ができることです。
登校日数を選べたり、オンラインで授業を受けられたりと、柔軟な仕組みが整っています。
そのため、勉強だけでなく、趣味・アルバイト・療養などと両立しながら通う生徒も多くいます。
一方で、自由度が高い分だけ“自分で学びを進める力”が求められるのも事実です。
だからこそ、学校がどのようにサポートしてくれるかが大切になります。
たとえば
担任の先生が定期的に面談を行い、学習進度や生活面をサポートしてくれる
メッセージアプリやオンライン面談で、いつでも相談できる
カウンセラーや専門スタッフが在籍し、メンタル面を支えてくれる
※学校によってサポートは違いますので、希望する学校のサポート内容は、しっかりと確認しましょう
こうした人とのつながりの中で安心して再スタートできる環境が、通信制高校の魅力でもあります。
通信制高校は、“全日制が合わなかったから行く場所”ではありません。
お子様が自分のリズムで、もう一度学びを積み上げていける場所です。
親御さんにとっても、あわてずに一歩ずつ前へ進むお子様の姿を見守ることができる―そんな“新しいスタートの場”になっています。
通信制高校の仕組みと実情を知ろう
通信制高校は「授業がない」「自分で勉強するだけ」という誤解もありますが、実際は自分のペースで学びながらもサポートを受けられる仕組みが整っています。


全日制や定時制と同じく、卒業すれば高校卒業資格が得られる正式な高校です。
ここでは、通信制高校の基本的な仕組みと、学びのスタイルをわかりやすく整理します。
通信制高校の基本的な仕組み
通信制高校は、在宅での学習を中心に、必要に応じて登校して学ぶ仕組みです。
毎日登校する全日制とは異なり、家庭学習の比重が大きいのが特徴です。
学習の流れは次の3つで構成されています。
レポート提出:各教科の課題に取り組み、郵送やオンラインで提出。
スクーリング(対面授業):年数回〜月数回、学校や学習センターに登校して授業や面談を受ける。
単位認定テスト:学期末などにテストを受け、合格すれば単位が認定。
卒業には、全日制・定時制と同じく「74単位以上の修得」と「3年以上の在籍期間」「特別活動の要件」が必要です。
(大阪通信制高校グループ「通信制高校教育の 現状について」)
通信制高校のスクーリングについては、こちらで解説しています。
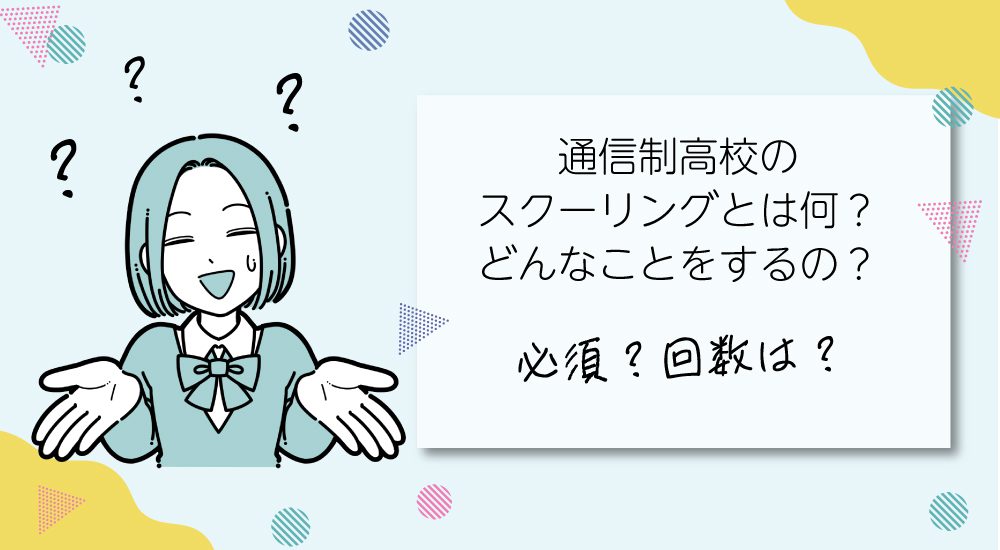
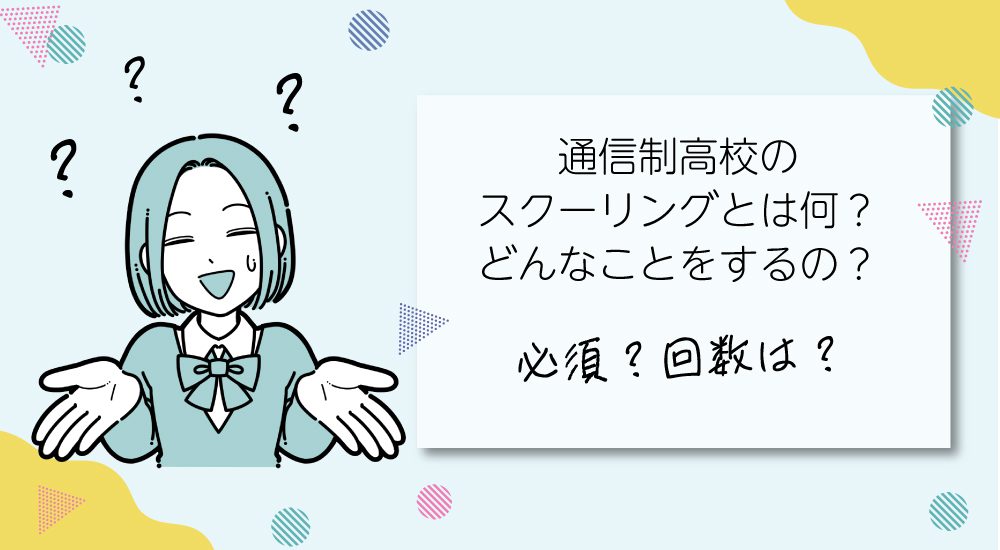
通い方・学び方の種類
“通信制=自宅学習”と思われがちですが、最近では多様な通学スタイルが広がっています。
たとえば
週1〜4日間だけ登校する通学コース
毎日通う全日型コース
自宅からオンラインで受講するオンラインコース
など、生活リズムや体調、目的に合わせて柔軟に選べます。
登校日には授業のほか、面談や探究活動、学校行事なども行われ、「人とのつながり」や「社会との接点」を大切にしている学校も増えています。
全日制・定時制との違い
高校には「全日制」「定時制」「通信制」という3つの課程があります。
どれも同じ“高等学校”ですが、学び方や通い方に違いがあります。
| 課程 | 主な通学スタイル | 特徴 |
| 全日制 | 平日昼間に毎日登校 | 授業数が多く、学校生活中心の学び。部活動・行事も充実。 |
| 定時制 | 昼・夕方・夜など時間帯を選んで登校 | 働きながら学ぶ生徒も多く、少人数でアットホームな環境。 |
| 通信制 | 在宅学習+登校(スクーリング) | 自分のペースで学べる。オンライン授業や個別指導が中心。 |
3つの課程は「通学の頻度」「時間の使い方」「サポートの形」に違いがあります。
通信制高校は、その中でも最も柔軟に、自分に合ったペースで学べるのが特徴です。
詳しい比較はこちらの記事をご覧ください。
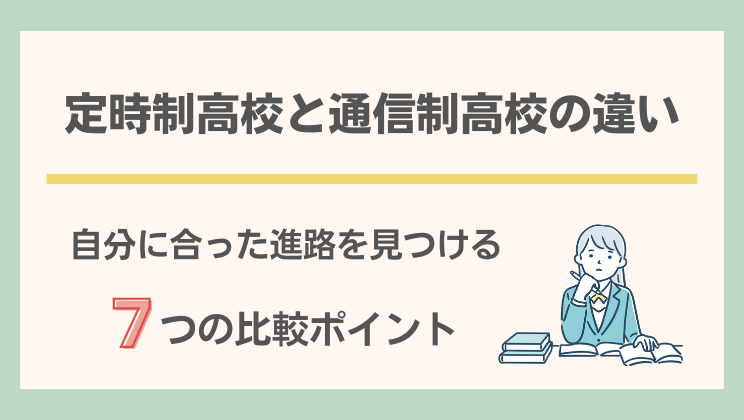
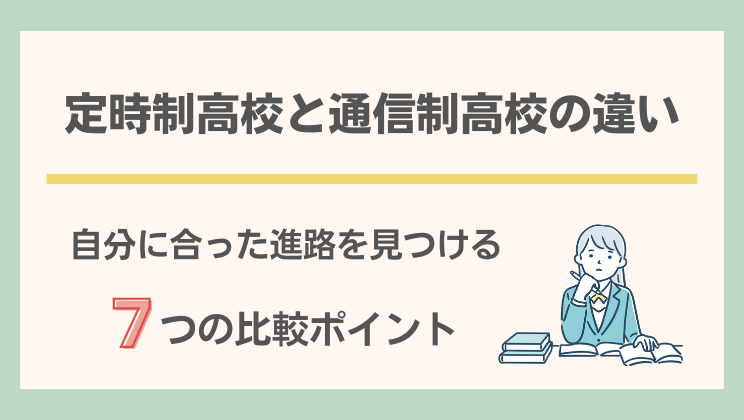
通信制高校のメリット|柔軟な学び方と個別対応


通信制高校のいちばんの魅力は、「一人ひとりに合った学び方が選べる」ことです。
通学日数・時間帯・学びのペースを自分で決められるため、体調や生活リズムに合わせて学習を進めることができます。
さらに、オンライン授業や個別面談、心理的サポートなど、近年は一人ひとりの状況に応じた支援体制も整っています。
ここでは、通信制高校の主なメリットを3つの視点から整理してみましょう。
① 時間と学び方の自由さ
通信制高校では、登校日数や授業の受け方を自分で選べます。
週1〜4日間登校するタイプから、オンライン中心の在宅コース、毎日通う通学型まで、さまざまなスタイルがあります。
たとえば
朝がつらいお子様は、午後登校型のクラスを選べる
医療通院や家庭の事情と両立できる
スポーツ・アルバイト・芸能活動と並行して学べる
こういった「自分に無理のない時間の使い方」ができるのが特徴です。
この柔軟さが、学びを続けるモチベーションを支える大きなポイントになります。
② 自分のペースで学習できる仕組み
通信制高校は単位制です。



これは、「学年ごとに進級する」のではなく、教科ごとに必要な単位を積み上げていく仕組みのこと。
全日制のように「クラス全体で同じペースで進む」必要がないため、得意な科目を先に進めたり、体調や状況に合わせてペースを調整したりすることができます。
たとえば
レポート提出やオンライン教材でコツコツ進める
スクーリングで先生に質問して理解を深める
個別指導・面談で学習計画を一緒に立てる
など、学校によって多様な学習サポートがあります。
「わからないところをそのままにしない」仕組みが整っているため、学び直しにも適しています。
③ 心理的な安心感と再スタートのしやすさ


通信制高校は、学力だけでなく「心」にも寄り添う学校が多くあります。
少人数制・個別対応・カウンセラー配置など、安心して通える環境づくりが進んでいます。
過去に不登校や中退を経験したお子様も、「もう一度チャレンジしたい」という気持ちで再スタートを切るケースが増えています。
登校日が少なくても、担任や専門スタッフとの関わりがあることで孤立を防ぎ、小さな成功体験を積みながら自信を取り戻す生徒も少なくありません。
通信制高校は、“全日制に行けなかった子が行く学校”ではなく、“自分に合った学び方で、自分らしく成長できる学校”です。
通信制高校のデメリット|入学前に知っておきたい7つの課題
通信制高校には、多様な学び方や柔軟な仕組みといった大きな魅力があります。
一方で、「自由度が高いからこそ、本人の努力やサポートが欠かせない」という面もあります。
入学前に“デメリット”を知ることは、失敗を避けるためではなく、安心して続けるための準備でもあります。
ここでは、通信制高校でよく見られる7つの課題を取り上げ、それぞれの背景と注意点を整理します。
「知っていれば防げること」も多いので、ぜひ親御さんも一緒に確認してみてください。
① 自己管理が難しく、学習ペースを保ちにくいこともある
- 課題
-
通信制高校では、選択するコースによっては登校日が少なくなるため、課題提出や学習の進み具合を自分で管理する必要があります。
そのため、生活リズムやモチベーションの波によって、学習が思うように進まなくなることがあります。 - よくあるケース
-
レポート提出が遅れ、単位認定に間に合わない
課題がたまり、どこから手をつければいいかわからなくなる
最初は意欲的だったのに、数か月でやる気が低下してしまうレポート提出が遅れて単位認定に間に合わなかった - 背景にある仕組み
-
通信制高校は、学習ペースを自分で決められます。
この自由さは大きな魅力ですが、裏を返せば“誰もスケジュールを管理してくれない”ということ。
授業も自宅学習中心で、外からの声かけが少ないため、自己管理が苦手なお子様にはプレッシャーになりやすい環境です。
また、家庭でのサポートが難しい場合、孤立感や焦りを感じてしまうこともあります。文部科学省の調査によると、通信制高校で中途退学した生徒のうち、約35%が「学校生活への不適応」や「学業不振」を理由に挙げており、自己管理の難しさが背景にあると考えられます。
(文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」) - 保護者が気をつけたいこと
-
学校見学の際に、担任制や面談の頻度を確認する
学習の進み具合を可視化できるアプリやシステムの有無をチェックする
保護者も進み具合を共有できるよう、学校との連携方法を事前に確認しておく
② 友人関係を築きにくく、孤独を感じやすい
- 課題
-
通信制高校では、選択する学校やコースによっては登校日が少なかったり、学年ごとのクラスがないなど、生徒同士の交流の機会が限られることがあります。
そのため、友人関係を築きにくく、孤独を感じやすいお子様も少なくありません。 - よくあるケース
-
登校日が月数回で、顔見知りはできても親しい友人ができにくい
オンライン中心の学習で、同級生とのやりとりがほとんどない
オンライン上のつながりだけで、孤立感を感じてしまう - 背景にある仕組み
-
通信制高校では、登校日や授業スケジュールが生徒ごとに異なります。
同じ学年・同じクラスといった固定的な集団がなく、顔を合わせる機会が限られるため、自然な友人関係を築くのが難しくなるのです。
特にオンライン中心の学習スタイルでは、やり取りが“学習目的だけ”に限られることが多く、気軽に話したり相談したりする関係が生まれにくくなります。 - 保護者が気をつけたいこと
-
学校説明会で「交流イベント」「探究活動」「オンラインホームルーム」などの有無を確認する
生徒同士が安心して交流できるオンラインコミュニティやチャットツールの仕組みがあるか確認する
友人関係の悩みを相談できる先生やカウンセラーの体制をチェックする
③ 学習内容の理解が浅くなりやすい
- 課題
-
通信制高校では、レポート提出が中心の学習スタイルが多く、どうしても“こなすこと”が目的になってしまうことがあります。
「提出はできているけれど、内容が理解できていない」と感じるお子様も少なくありません。 - よくあるケース
-
わからない部分をそのままにして課題を提出してしまう
先生に質問したいことがあっても、タイミングがつかめない
苦手な教科ほど手が止まり、学習意欲が下がっていく - 背景にある仕組み
-
通信制高校の学習は「レポート」「面接指導(スクーリング)」「テスト」で構成されています。
このうちレポート学習の比重が大きいため、その場で先生に質問できる機会が少ないのが実情です。
また、スクーリングの回数や授業時間は学校によって異なり、学びのサポートに差が生まれやすい傾向もあります。 - 保護者が気をつけたいこと
-
ライブ授業や質問チャットなど、その場で疑問を解消できる仕組みがあるか確認する
苦手な部分を後から繰り返し学べる録画授業があるか確認する
スクーリング時に、質問や補習の時間が設けられているかチェックする
④スクーリングや登校への不安が再発することがある
- 課題
-
過去に学校へ行けなかった経験があると、「また行けなくなるかも」と感じやすくなります。
スクーリングの日が近づくと、体調が乱れたり、緊張で不安が強まったりするお子様も少なくありません。 - よくあるケース
-
「登校」と聞くだけで体調が悪くなるほど緊張してしまう
グループワークや対面授業の時間にプレッシャーを感じる
一度欠席したことで「また行けなかった」と自己否定感が強まる - 背景にある仕組み
-
通信制高校では、卒業には対面授業(スクーリング)への出席が必要です。
「完全に自宅で学べる」と思って入学すると、登校義務を知って戸惑うケースがあります。
また、登校日程が固定されている学校では、体調や事情に合わせて調整しにくいこともあります。 - 保護者が気をつけたいこと
-
スクーリングの回数・日程・会場を事前に確認しておく
「在宅+オンライン対応」など、柔軟な選択肢がある学校を選ぶ
登校に不安を抱えるお子様には、事前に先生との面談や見学で雰囲気を確認させておく
スクーリングについては、こちらで詳しく解説しています。
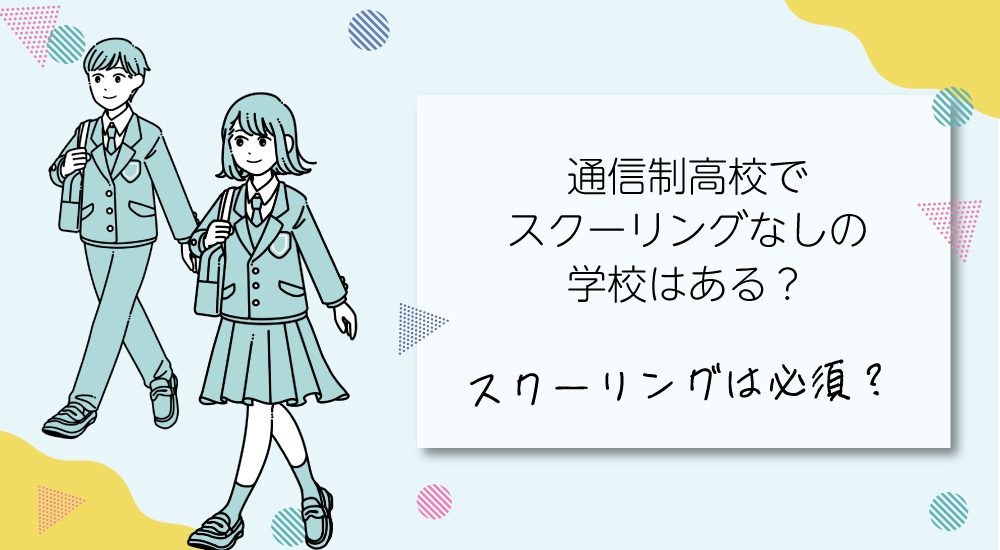
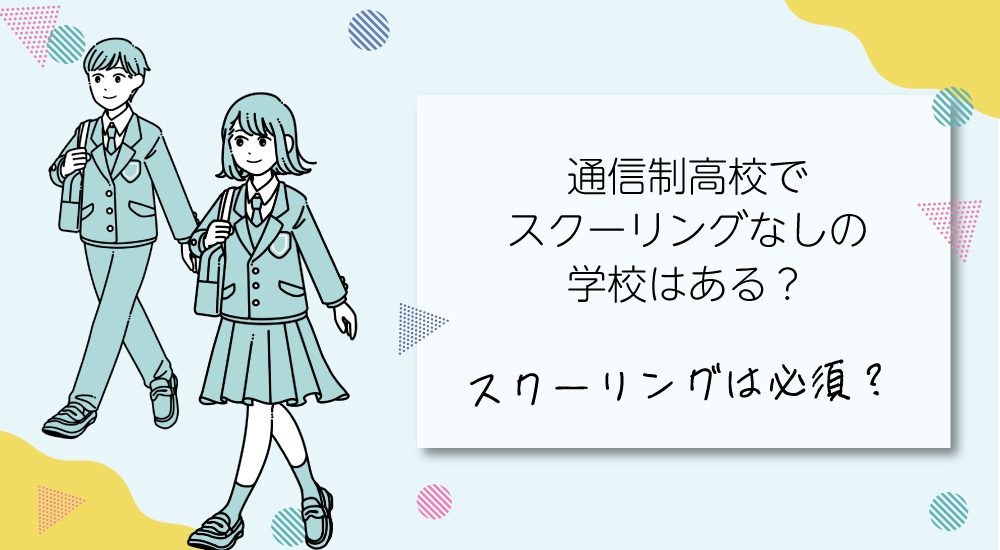
⑤ モチベーションを維持しづらく、途中で中だるみしやすい
- 課題
-
通信制高校は自分のペースで学べる反面、「誰かと一緒に頑張る」刺激が少なく、気持ちを保ちにくい面があります。
最初はやる気があっても、時間がたつにつれて目標があいまいになり、課題やレポートが後回しになってしまうお子様も少なくありません。 - よくあるケース
-
進級や卒業までの期間が長く感じられ、途中でモチベーションが下がる
一人で勉強しているうちに、何のために頑張っているのか分からなくなる
友人や先生とのつながりが薄く、孤立感が強まっていく - 背景にある仕組み
-
通信制高校では、学習の進め方や時間の使い方を自分で管理する必要があります。
コースによっては通学頻度が少なく、周囲の進捗が見えにくいため、「今どれくらい頑張れているのか」が実感しにくいのです。
また、定期的な行事やクラス活動が少ない学校では、“区切り”や“達成感”を感じにくいことも、やる気の低下につながります。 - 保護者が気をつけたいこと
-
学校が定期的な面談や振り返りの機会を設けているか確認する
探究活動や資格講座など、目的をもって取り組めるカリキュラムがあるかチェックする
家庭でも、勉強以外の話題でお子様の努力を認める・声をかける時間をつくる
⑥費用の仕組みが複雑なことも。勘違いで思わぬ負担になることがある
- 課題
-
通信制高校は「学費が安い」と紹介されることもありますが、実際には学校によって費用の内訳が大きく異なります。
とくに「通信制高校」と「サポート校」を併用する場合、契約が別々になっており、思わぬ出費が発生するケースもあります。 - よくあるケース
-
「月3万円程度」と聞いていたのに、サポート校の費用が別途必要だった
教材費・施設利用費・スクーリング費などが後から加算され、想定より高額になった
費用の説明が不十分なまま契約し、トラブルにつながった - 背景にある仕組み
-
通信制高校によっては、「本校(通信制高校)」と「学習センター」または「サポート校」が連携していることがあります。
このうち、卒業資格を与えるのは通信制高校側であり、サポート校や学習センターはあくまで学習や生活支援を行う外部の教育機関です。
そのため、学費は通信制高校の授業料+サポート校の支援費用と二重構造になることがあります。 - 保護者が気をつけたいこと
-
契約前に、希望する通信制高校・サポート校・学習センターの関係性を明確に確認する
費用の内訳(授業料・教材費・スクーリング費など)を学校説明会や、できれば個別相談で確認する
「高等学校等就学支援金制度」の対象になるかどうかも必ず確認する
通信制高校の学費については、こちらの記事もご覧ください。
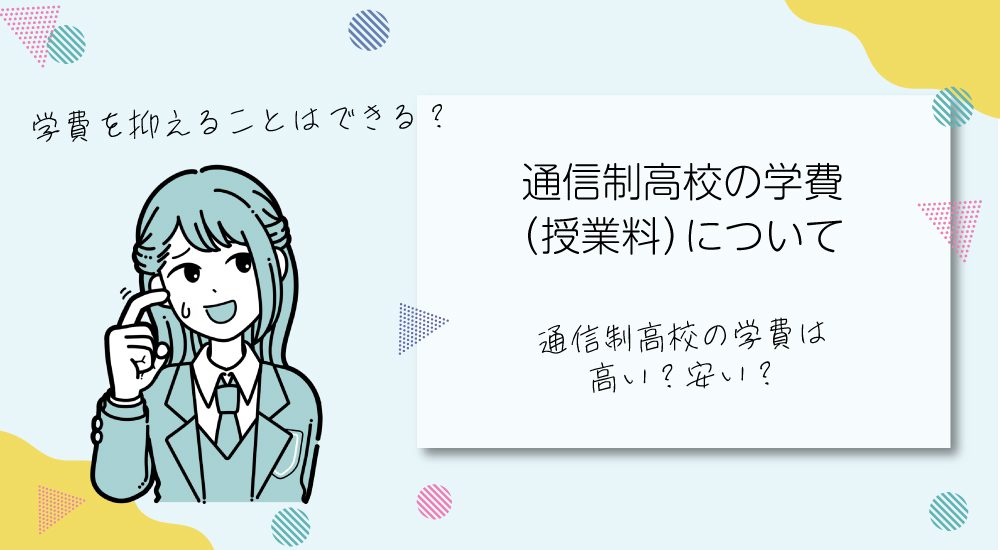
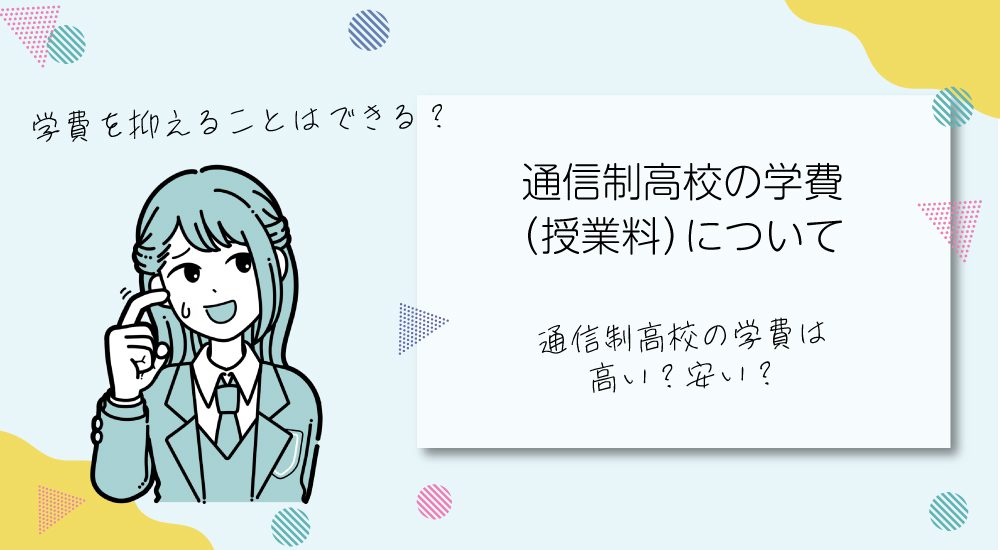
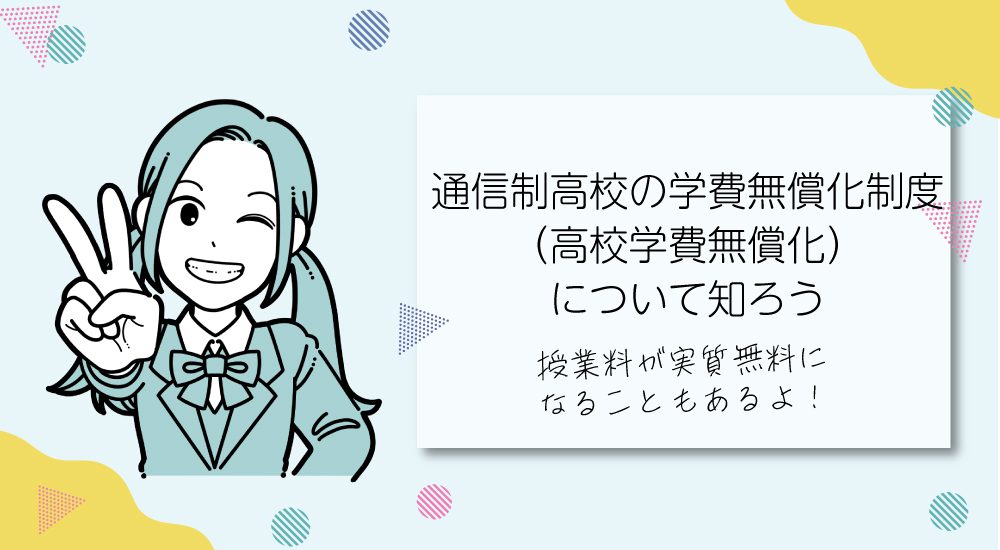
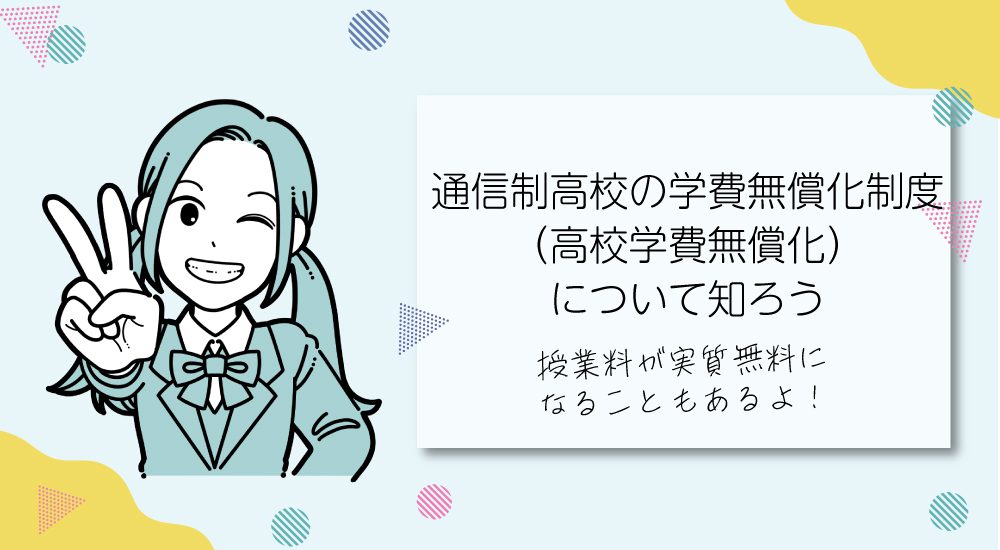
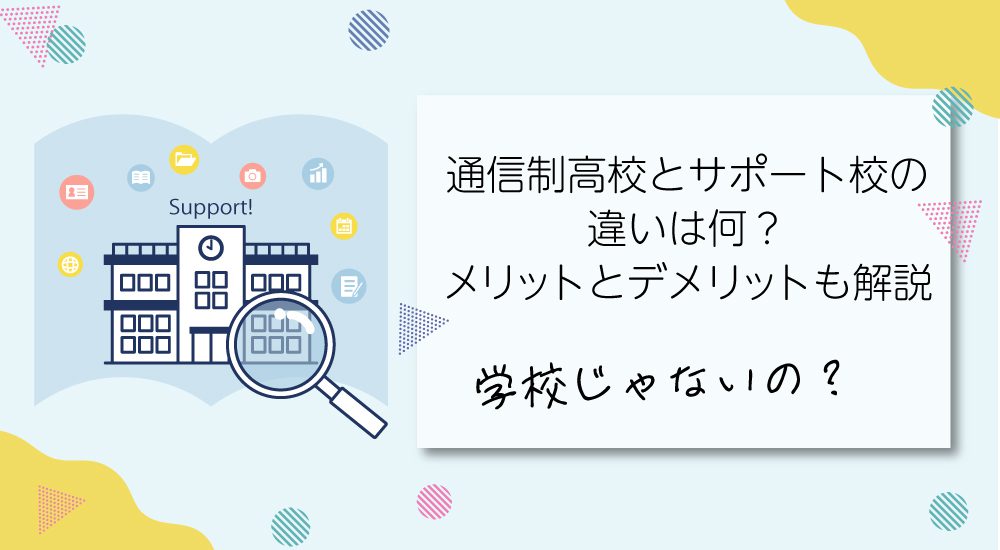
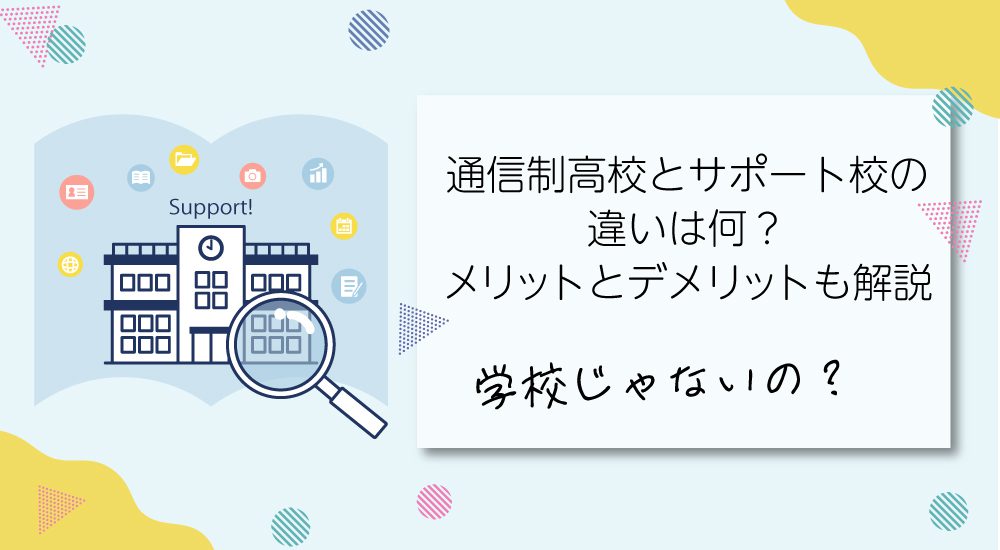
⑦ 進学・就職で不利になるという誤解がある
- 課題
-
通信制高校に対して、「全日制よりも不利ではないか」「大学進学が難しいのでは?」といった不安を持つ保護者は少なくありません。
こうした印象から、せっかくお子様に合った環境があっても、選択をためらってしまうケースがあります。 - よくあるケース
-
「通信制だと履歴書に書いたとき印象が悪いのでは」と心配する
「大学受験では不利」と周囲に言われ、進学意欲が下がる
子ども本人が「通信制だから無理かも」と自信を失ってしまう - 背景にある仕組み
-
通信制高校の卒業資格は、全日制・定時制とまったく同等です。
入試や就職の際も、評価が変わることはありません。
それでも誤解が残るのは、かつて「夜間・社会人向け」というイメージが強かった時代の名残によるものです。
しかし現在では、大学や専門学校への進学を目指す生徒が増加しており、文部科学省の調査(令和5年度間)によると、通信制高校の卒業生のうち約5割が進学(大学・短大・専門学校)しており、進路の幅は年々広がっています。
(文部科学省:「高等学校教育の在り方ワーキンググループ 審議まとめ 参考資料集」) - 保護者が気をつけたいこと
-
「通信制=不利」という情報をうのみにせず、最新の進学実績や卒業後の進路データを確認する
オープンキャンパスや学校説明会で、大学進学者の事例やサポート体制を具体的に聞いてみる
通信制ならではの「探究活動」や「自己PRのしやすさ」が評価される入試方式(総合型・推薦型)にも注目する
通信制高校からでも、卒業後の進路は幅広く開かれています。
近年は大学だけでなく、短期大学や専門学校への進学を選ぶ生徒も増えています。
通信制高校からの進学実績や受験の準備方法については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
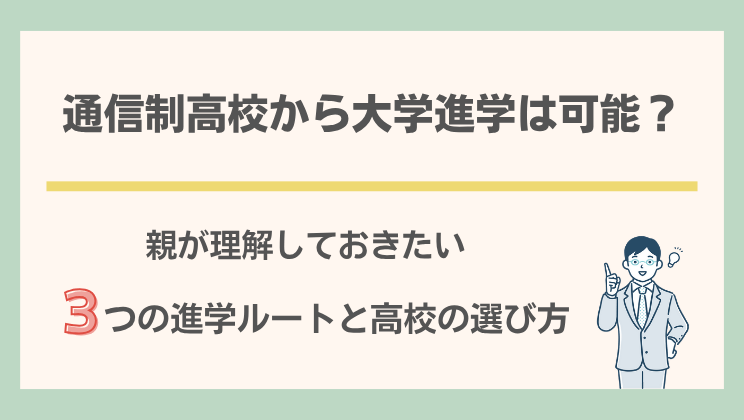
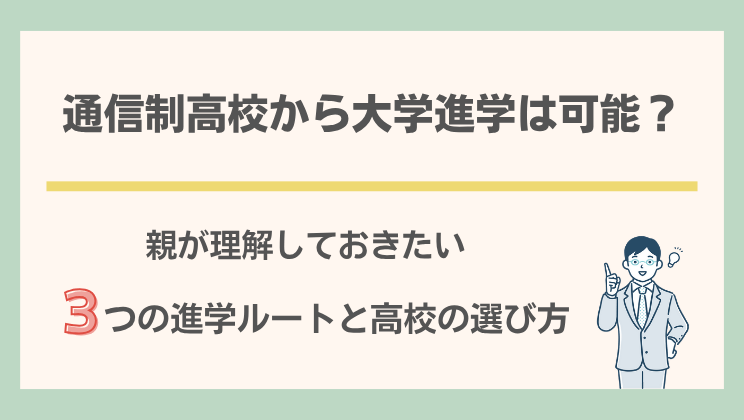
通信制高校のオンラインコースが「向いていない人」・「向いている人」
通信制高校は、一人ひとりのペースに合わせた学びができる柔軟な仕組みが魅力です。


ただし、通信制高校のオンラインコースを希望する場合は、どんなお子様にも合うというわけではありません。
ここでは、「向いていないタイプ」と「向いているタイプ」の特徴を比較しながら見ていきましょう。
| 比較項目 | 向いていないタイプ | 向いているタイプ |
| 学習スタイル | 計画的に進めるのが苦手で、課題が後回しになりがち | 自分のペースで学習を進められる、集中力がある |
| 人との関わり方 | 関わりを避けたい・相談が苦手で孤立しやすい | 少人数やオンラインでも、人とのつながりを大切にできる |
| 学校への期待 | 行事や部活動など、日常の学校生活を重視 | 学びや資格取得、探究活動など目的意識がある |
| 学習への姿勢 | 指示がないと動けない、サポートがあっても続けにくい | 自分から行動できる、興味をもって深められる |
| 目標意識 | 「とりあえず進学」など目的が曖昧 | 「再スタートしたい」「得意を伸ばしたい」など意欲がある |
| サポートの受け方 | 困っても助けを求めにくい、自己完結しがち | 担任やカウンセラーに相談できる柔軟さがある |
通信制高校のオンラインコースに「向いていない」タイプ
通信制高校は、自分のペースで学べる自由度が魅力ですが、オンラインコースの場合、より自己管理の力や目的意識が必要になります。
どんなお子様にも合うわけではなく、どのようなサポートがあるかを意識して選ぶことが大切です。
計画を立てるのが極端に苦手で、課題を後回しにしがち
人との関わりを避け、先生や友人に相談しにくい
行事や部活動など「学校生活」そのものを楽しみたい
「とりあえず高校に行く」という気持ちで、目標がまだ曖昧
このようなタイプのお子様は、通信制高校でも「孤立」や「意欲の低下」が起こりやすい傾向があります。



ただし、これは“向いていない”というより、支援の形を工夫する必要があるタイプです。
たとえば、担任との定期面談やカウンセラーのサポートがある学校を選ぶことで、計画立てや気持ちの整理をサポートしてもらえます。
通信制高校を検討する際は、「本人がどれくらい自立的に学べるか」だけでなく、「どんな支援を受けながらなら続けられるか」を一緒に考えることが大切です。
通信制高校に「向いている」タイプ
一方で、通信制高校の柔軟な仕組みをうまく活かせるお子様も多くいます。


共通しているのは、「自分のペースで進めたい」「新しい環境で再スタートしたい」という前向きな姿勢です。
コツコツ学ぶことが得意で、マイペースに取り組める
得意分野や興味を深めたい、探究心がある
一度挫折を経験したが、もう一度学び直したい意欲がある
オンライン学習や個別サポートを活用できる柔軟さがある
通信制高校では、学び方の自由さを活かして、勉強と趣味・仕事・療養などを両立させながら、自分らしい学びを続けることができます。
特に、探究活動や資格取得に挑戦できる学校も増えており、「自分の興味を形にできる環境」が整っています。
大切なのは、「合っているかどうか」ではなく、「お子様が安心して力を発揮できる環境かどうか」。
通信制高校は、“新しいスタート”を支える柔軟な選択肢のひとつです。
転入・編入後に起こりやすい失敗例とその背景
通信制高校への転入・編入は、新しい環境での再スタートです。
自由度が高い反面、生活や学習のスタイルが大きく変わるため、最初の数か月でつまずくケースも少なくありません。
でも、こうした“つまずき”は誰にでも起こりうることで、決して特別なことではありません。
不安を感じたときは、こちらの記事も参考にしてみてください。
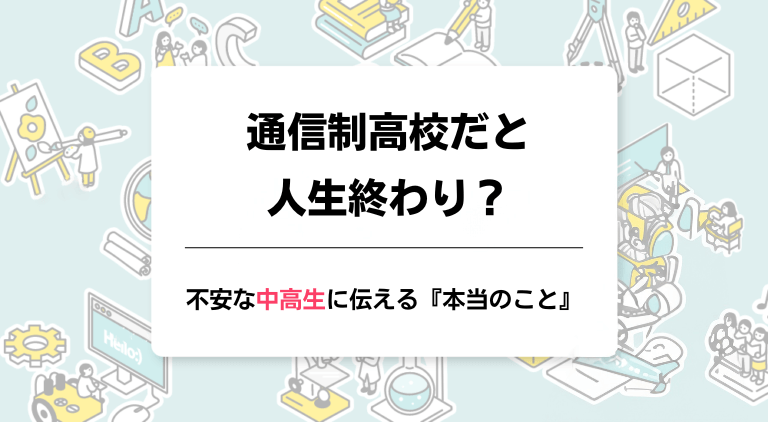
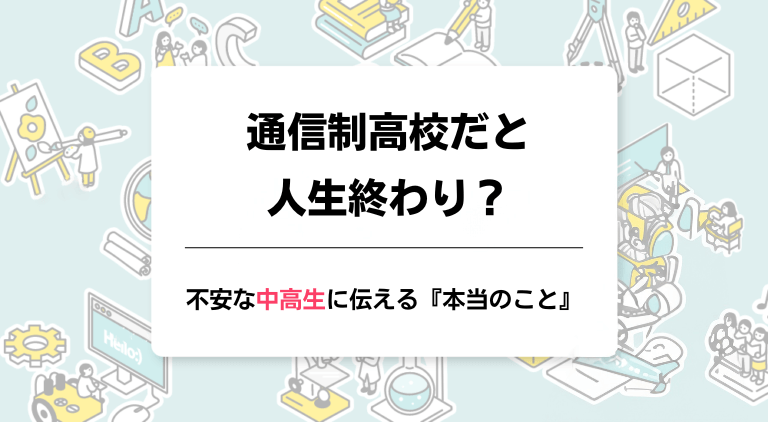
ここでは、よくある3つの“つまずきパターン”を紹介します。
「起こりやすい理由」を知ることで、親としてできるサポートが見えてきます。
入学直後にペースをつかめず、課題がたまる
通信制高校では、自分のペースで課題やレポートを進める仕組みになっています。
大切なのは、“一人で頑張る”よりも、“つながりを活かす”こと。
入学して間もない時期は、新しい教材の使い方や課題提出のペースがつかめず、気づけば「やることが多すぎて手が止まる」というお子様も少なくありません。



これは怠けではなく、“環境に慣れるための時間が必要なだけ”です。
最初から完璧を求めず、「1日1ページ」「1科目ずつ」など、小さなステップで自信を積み重ねていくことが大切です。
人とのつながりを避けすぎて孤立
通信制高校では、集団行動が苦手な生徒でも安心して学べる環境が整っています。
一方で、「誰にも会わなくていい」「自分一人で頑張れる」と思い込んでしまうと、サポートを受けるきっかけを逃し、孤立感が強まることもあります。
オンラインやチャットなど、ゆるやかに関われる仕組みがある学校も増えています。



大切なのは、“一人で頑張る”よりも、“つながりを活かす”こと。
ほんの少しのやり取りでも、安心感やモチベーションの維持につながります。
一人で頑張ることも大切ですが、必要なときに助けを求められることも成長の一歩です。
焦って単位を詰め込みすぎる
通信制高校では、単位制の仕組みにより、自分のペースで学びを進められます。
しかし、「早く卒業したい」「前の遅れを取り戻したい」と焦るあまり、一度に多くの科目を履修してしまい、心身ともに負担が大きくなるケースもあります。
単位の取得は“積み重ね”が基本です。



一気に詰め込むより、確実に修得していく方が結果的に近道になることも。
通信制高校の魅力は、時間をかけて「自分のペースを取り戻せる」こと。
卒業時期よりも、学びを続けられるリズムを大切にしましょう。
通信制高校のデメリットを防ぐための工夫とサポート方法
通信制高校には、「自由度の高さ」と引き換えに、自己管理や人とのつながりといった面で課題が生じやすいという特徴があります。
しかし、仕組みを正しく理解し、学校・家庭・専門機関がそれぞれの立場で支えることで、ほとんどの課題は防ぐことができます。
ここでは、入学前から意識しておきたい工夫とサポート方法を整理します。
学校選びの段階で確認しておくこと
通信制高校ごとに、授業形式や担任制度、進路指導体制には大きな違いがあります。
入学後のミスマッチを防ぐためには、「制度を理解したうえで、自分に合う学校を選ぶ」ことが第一歩です。
以下の5つのポイントを事前に確認しておくと安心です。
① 卒業要件の誤解に注意
通信制高校でも、卒業には 「74単位以上の修得」と「3年以上の在籍期間」「特別活動の要件」が必要です。
「短期間で卒業できる」と誤解されやすいですが、計画的に単位を積み上げる必要があります。
② スクーリングは必要
通信制高校は「完全在宅」ではありません。
年数回のスクーリング(対面授業)が法律で義務づけられています。
登校頻度や場所、オンライン対応の有無は学校によって異なるため、事前に確認しましょう。
③ レポート提出は“出席扱い”
通信制では、レポート提出が出席の代わりになります。
未提出が続くと、単位認定や進級に影響することもあります。
学習進度を管理できるアプリや面談制度がある学校なら、提出ペースを保ちやすく安心です。
④ 通信制高校とサポート校の違い
サポート校は「教育支援機関」であり、卒業資格を与えるのは通信制高校側です。
両者の関係を理解し、学費や契約内容を必ず確認しましょう。
併設・提携の形態によってサポート範囲(学習・メンタル・進路指導など)が異なります。
⑤ 単位の引き継ぎは学校長の判断
転入・編入時に前の高校で取得した単位を引き継げるかは、学校長の判断によります。
同一科目でも内容が改訂されている場合は再履修になることもあるため、早めの相談が大切です。
家庭でできるサポート
通信制高校での学びには、家庭の支えが何よりも大切です。
お子様の努力を“外から支える存在”として、次のような工夫が効果的です。
生活リズムを一緒に整える
起床・食事・学習時間などの目安を共有
小さな達成を言葉にして認める
レポート提出や登校などを「よく頑張ったね」と声に出す
「頑張りすぎない」声かけを意識する
調子が悪い日は休む勇気も肯定する
相談のハードルを下げる
「困ったら言ってね」より、「一緒に考えようね」と伝える
学校との情報共有を大切にする
担任やカウンセラーと連携してサポート
“支える=管理する”ではありません。
心のエネルギーを満たす関わりが、お子様の安心につながります。
外部支援・相談窓口を活用する
学校や家庭だけで抱え込まず、外部機関の支援を早めに使うことも大切です。
困ったときに相談できる先を知っておくことで、保護者自身の安心にもつながります。
教育支援センター(適応指導教室):不登校や復学支援の相談が可能
スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー:心理・家庭・生活面の相談
もろうよこころ(厚生労働省):こころの健康・子どもの悩みに関する全国的な相談サイト
一人で悩まず、つながる力を活かすこと。
それが、通信制高校での学びを続けるいちばんの支えになります。
【Q&A】通信制高校のデメリットに関するよくある質問
- 通信制高校は本当に卒業できますか?
-
はい。通信制高校でも、全日制・定時制と同じ卒業資格が得られます。
卒業には「74単位以上の修得」「3年以上の在籍期間」「特別活動(校長認定)」の3要件が必要です。通信制の特徴は、自分のペースで単位を積み上げられること。
体調や家庭の事情に合わせて進められるので、途中でのブランクがあっても無理なく続けられます。仕組みや卒業までの流れを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
通信制高校の仕組みと実情を知ろう - 通信制高校の卒業は大学進学に不利ですか?
-
いいえ。通信制高校の卒業資格は全日制・定時制とまったく同等です。
実際、文部科学省「令和5年度間 学校基本調査」によると、通信制高校の卒業生の約35%が大学・短大へ進学しています。近年は、知識だけでなく「探究力」「主体性」「表現力」を評価する総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜が主流になりつつあります。
通信制の自由な時間や探究活動は、むしろこれらの入試で強みになることもあります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
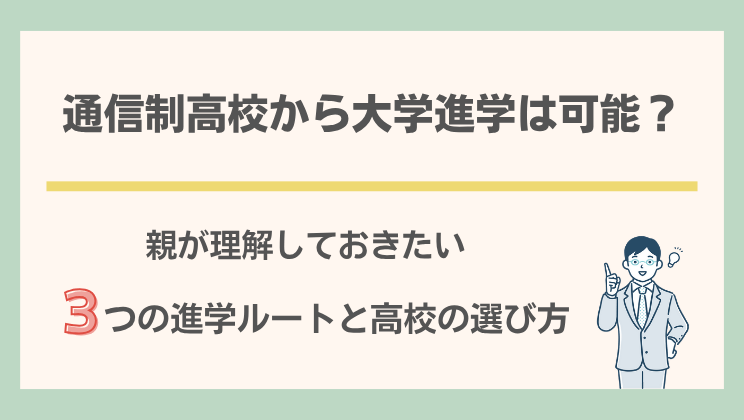 通信制高校から大学進学は可能?|親が理解しておきたい3つの進学ルートと高校の選び方 | 【公式】ID学園… 通信制高校からでも大学進学は十分に可能です。入試制度の仕組みや3つの進学ルート、学校・コース選びのポイントをわかりやすく解説。受験対策やサポート体制、先輩の実例…
通信制高校から大学進学は可能?|親が理解しておきたい3つの進学ルートと高校の選び方 | 【公式】ID学園… 通信制高校からでも大学進学は十分に可能です。入試制度の仕組みや3つの進学ルート、学校・コース選びのポイントをわかりやすく解説。受験対策やサポート体制、先輩の実例… - 通信制高校は「友達ができない」と聞きました。本当ですか?
-
たしかに、登校日が少ない学校では自然な交流の機会が限られます。
しかし最近では、オンラインHR・探究学習・学校イベントなど、つながりを育てるための取り組みが充実しています。たとえば、オンラインでグループ活動を行う学校や、チャットツールを使って生徒が自由に交流できる環境も増えています。
大切なのは、「つながる仕組みがあるか」を入学前に確認することです。通信制高校での友達作りについては、こちらの記事もご覧ください。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
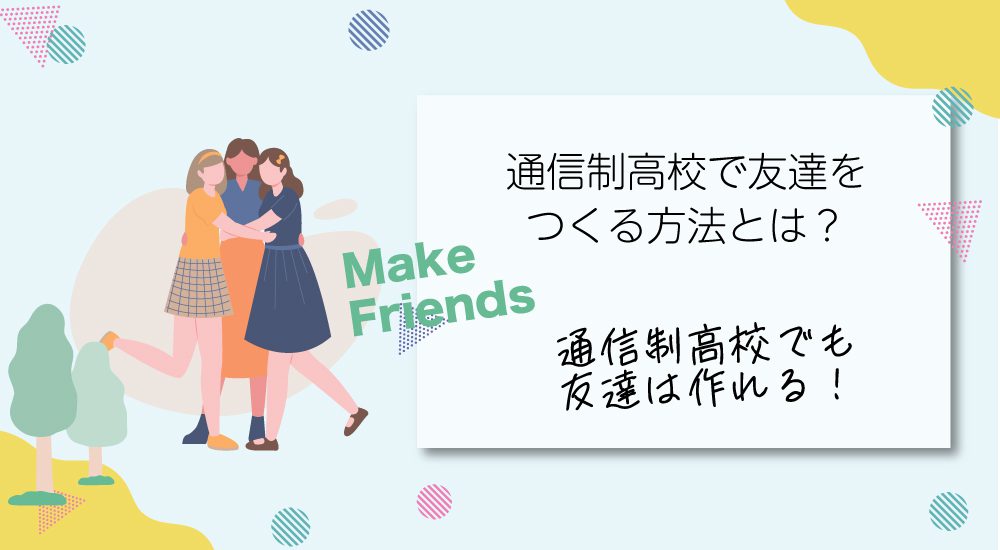 通信制高校で友達をつくる方法と4つのタイミング | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で1番大切に… 通信制高校に入学を考えている生徒さんの中には中学や今までの環境と全く違った単位制の学校生活の中で友達ができるのか不安に思っている人も多いでしょう。今回は通信制高…
通信制高校で友達をつくる方法と4つのタイミング | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で1番大切に… 通信制高校に入学を考えている生徒さんの中には中学や今までの環境と全く違った単位制の学校生活の中で友達ができるのか不安に思っている人も多いでしょう。今回は通信制高… - 通信制と定時制はどう違うの?どちらが合うでしょうか?
-
どちらも「柔軟に学べる高校」ですが、仕組みは少し異なります。
定時制高校:毎日登校するスタイル。生活リズムを整えたい人に向く
通信制高校:登校日を選び、自分のペースで学ぶスタイル。自己管理がしやすい人に向く「どちらが良い」ではなく、お子様の性格や生活スタイルに合う方を選ぶことが大切です。
詳しい比較はこちらの記事で紹介しています。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
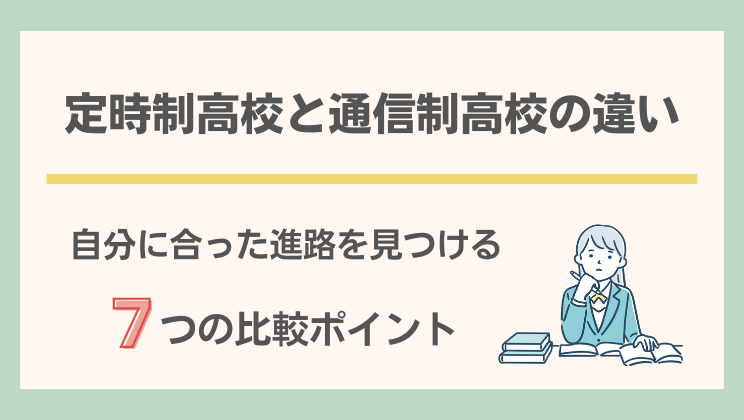 定時制高校と通信制高校の違い|自分に合った進路を見つける7つの比較ポイント | 【公式】ID学園高等学校_… 定時制高校と通信制高校の違いをわかりやすく比較。通学ペース・学費・サポート体制など7つの観点から、お子様に合った学び方を見つけるためのポイントを紹介します。
定時制高校と通信制高校の違い|自分に合った進路を見つける7つの比較ポイント | 【公式】ID学園高等学校_… 定時制高校と通信制高校の違いをわかりやすく比較。通学ペース・学費・サポート体制など7つの観点から、お子様に合った学び方を見つけるためのポイントを紹介します。 - 授業料が安いとサポートが少ないですか?
-
「授業料の安さ=サポートが少ない」とは限りません。
公立・私立・サポート校のどの形態かによって仕組みが異なります。公立校は授業料が安いが、個別支援の時間が限られがち
私立校は費用がかかる一方で、カウンセラーや進路指導が充実
サポート校併用型では、民間の支援機関が学習や生活面をフォロー大切なのは、「どこまでサポートしてもらえるか」を確認することです。
見学や説明会で、担任制・面談の頻度・学習サポート体制などを具体的に質問してみましょう。 - 通信制高校は怠けやすいように思いますが…
-
通信制では、登校の義務が少ない分、自己管理力が求められます。
そのため「怠けやすい」と感じるのは自然な不安かもしれません。ですが、最近の通信制高校では
担任の先生が定期的に学習進度をチェックする
学習管理アプリで進み具合を見える化する
Slackなどで日々のやり取りを行うなど、「続けられる仕組み」が整っています。
サポートがしっかりしている学校を選べば、むしろ「自分で進める力」を育てる学びの場になります。 - 不登校だった子でもやっていけますか?
-
はい。通信制高校は、「もう一度学びたい」という気持ちを受け止める学校です。
登校日を自分で決められるため、少しずつ学校生活に慣れていけます。また、カウンセラー・スクールソーシャルワーカー・担任が連携して、心理的サポートを行う体制を整えている学校も多くあります。
焦らず、自分のペースで再スタートできる環境を選ぶことが大切です。もしサポート体制を重視したい方は、こちらも参考にしてみてください。
通信制高校のデメリットを防ぐための工夫とサポート方法
まとめ|「デメリットを知ること」が安心の第一歩
通信制高校には、時間や場所にしばられずに学べるという大きな自由があります。
一方で、「自己管理の難しさ」や「人とのつながりの希薄さ」など、入学してから気づく課題もあります。
こうした“デメリット”を事前に知っておくことは、決してマイナスではありません。
むしろ、「どう備えればいいか」「どんな学校なら安心か」を考えるための大切な第一歩です。
【通信制高校を選ぶときに意識すること】
① 制度(単位制・スクーリング・レポート提出の仕組み)
② サポート体制(担任制・カウンセラー・進路支援)
③ 本人の性格や目的(自立・探究・再スタートなど)
お子様にとって「続けやすい」「安心できる」環境を見つけることが、何よりの支えになります。
通信制高校は、“特別な進路”ではありません。
一人ひとりが自分らしいペースで学び、再び未来へ歩き出すための“可能性の場”です。
環境を選び、支援を受けながら学び続ける経験そのものが、これからの時代に必要な“生きる力”を育てていきます。
【ID学園】通信制の「課題」を「成長の糧」に
通信制高校で直面しやすい課題―「自己管理」「孤独」「モチベーションの維持」。
ID学園では、それらを“弱点”ではなく、“成長のきっかけ”と考えています。
一人ひとりのペースと気持ちに寄り添いながら、「続ける力」「自分で考える力」「未来を描く力」を育てる環境を整えています。
柔軟な学び方が「自分で選ぶ力」を育てる
月ごとに「通学」や「オンライン」を自由に選べる仕組みがあり、生活リズムや体調に合わせた学び方が可能です。
「自分で選び、調整する」経験を通して、主体的に行動する“自己決定力”が育ちます。


担任制とオンライン支援が「続ける力」を支える
担任の先生・カウンセラーが連携し、学習だけでなく生活やメンタル面まで丁寧にサポートします。
Slackなどのオンラインツールを使えば、いつでも気軽に相談できる環境が整っています。


探究と夢教育が「未来を描く力」を伸ばす
ID学園の「ID型夢教育」では、探究・キャリア・起業教育などを通して、「自分は何をしたいか」「どう社会に関わりたいか」を深く考える力を育てます。
お子様が自分の可能性を信じ、未来に向かって一歩ずつ進めるように―ID学園はその挑戦を支えています。


通信制高校は、“特別な進路”ではなく、“可能性を広げる学びの場”です。
お子様が自分のペースで成長していける環境を、一緒に見つけていきませんか。
もし少しでも「話を聞いてみようかな」と思われたら、ぜひ学校説明会や個別相談にご参加ください。