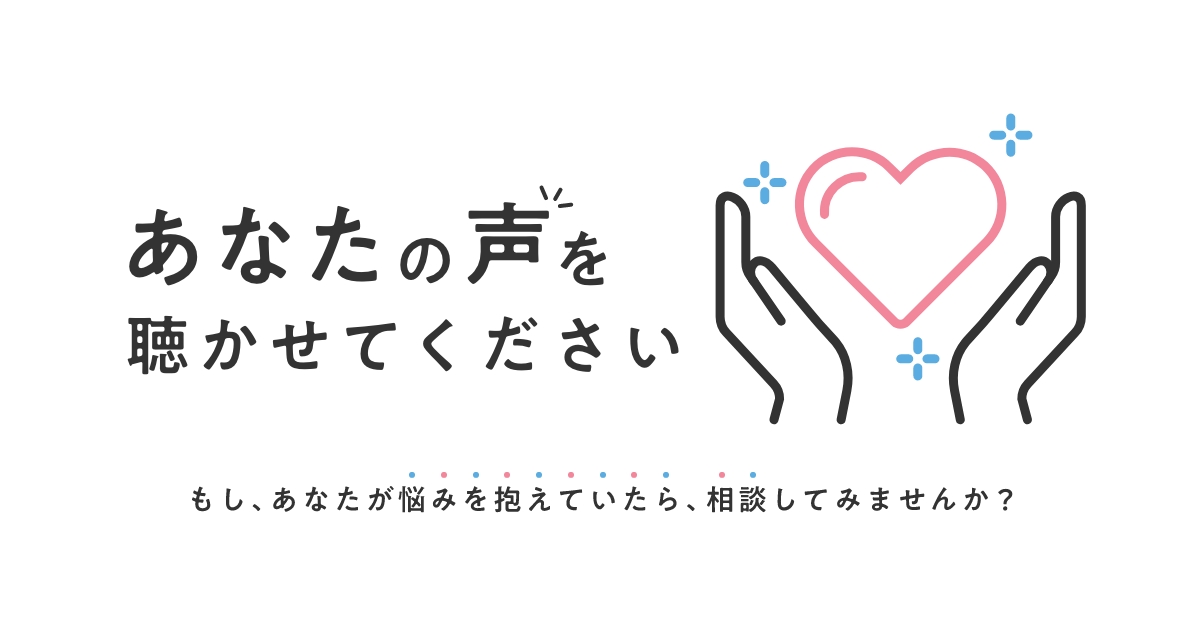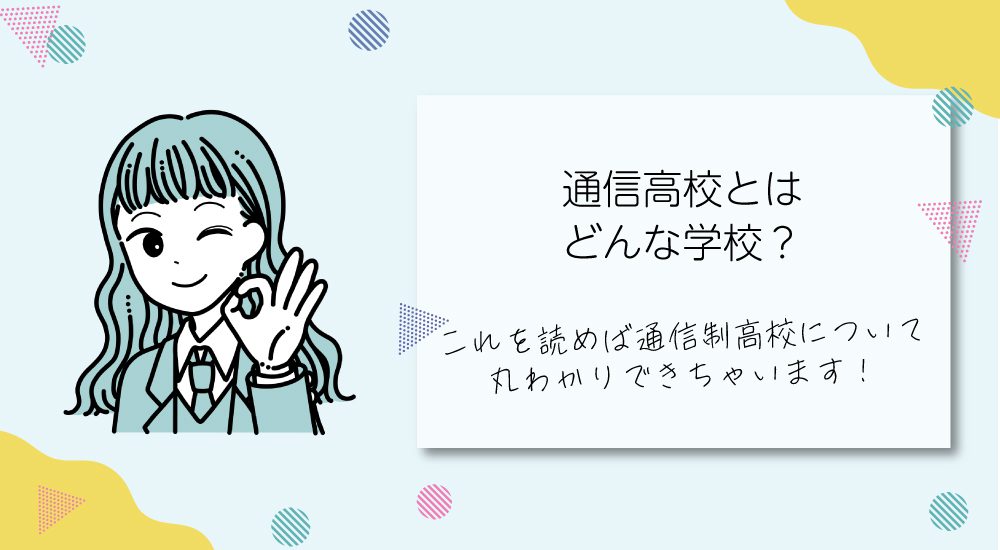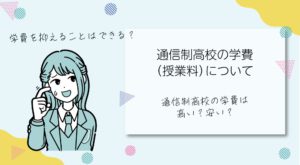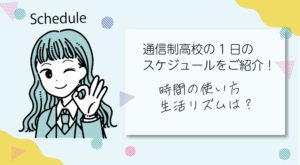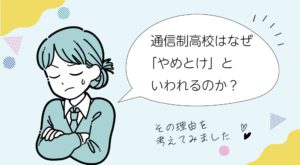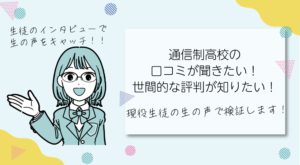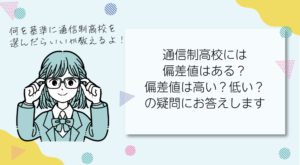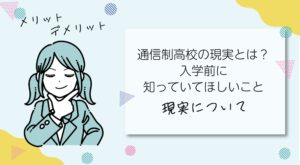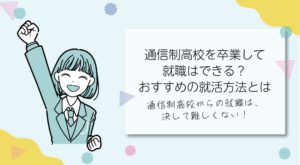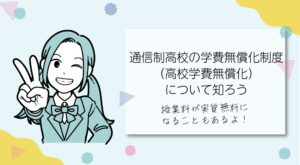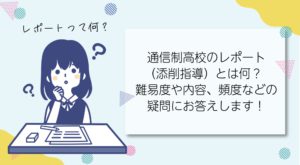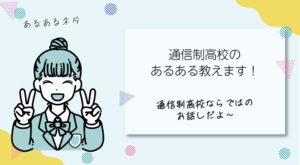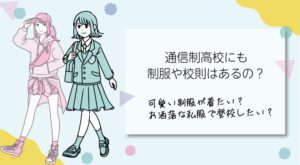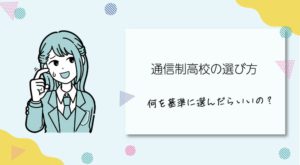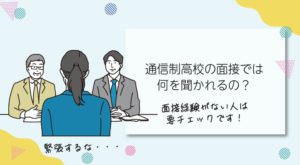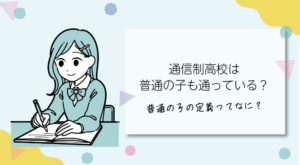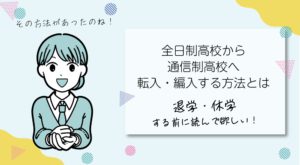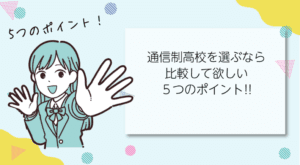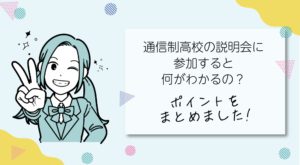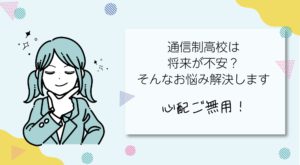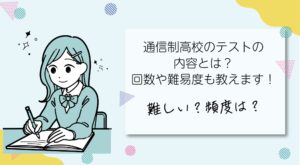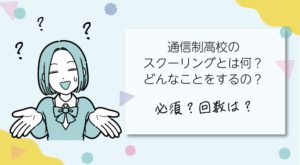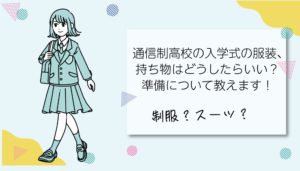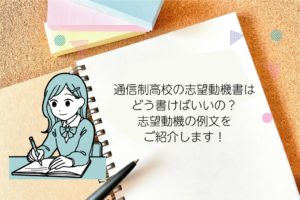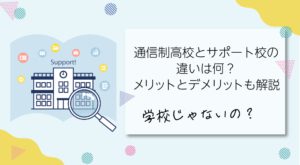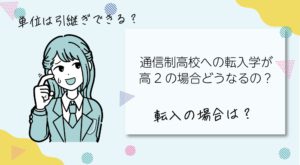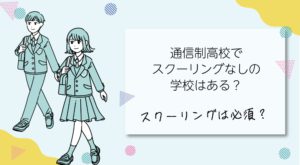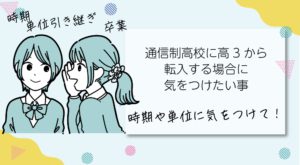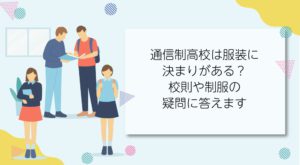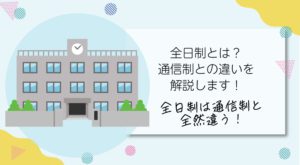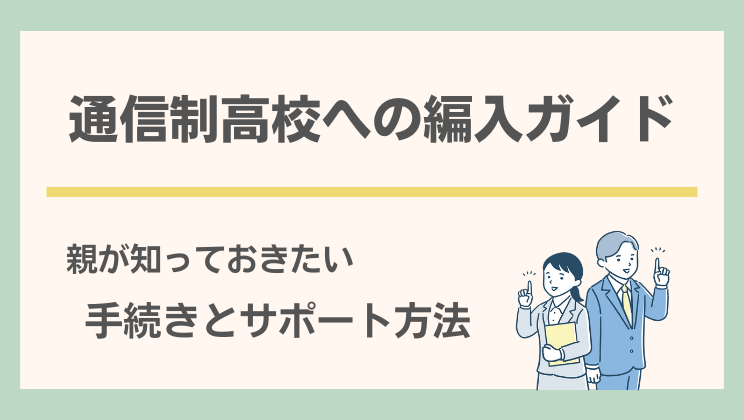
「もう一度、高校に行ってみようかな…」
「でも、今から行ける学校、あるのかなあ」
そんなお子様の言葉を聞いたとき、親御さんとしてはうれしさと同時に、「また同じように苦しむのでは」「今から間に合うの?」と不安がよぎるかもしれません。
文部科学省の調査によると、令和6年度に高校を中途退学した生徒は全国で約45,000人となっています。
(文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」)
多くの家庭が同じような悩みを抱えており、親御さんが感じている不安は、決して特別ではありません。
通信制高校には、『編入』という制度があります。
一度高校をやめた人が、別の高校に入り、学び直せる仕組みです。
年齢やブランクに関係なく、「もう一度がんばってみたい」という気持ちがあれば、再スタートの道は開けます。
この記事では、通信制高校への編入の仕組み、必要な書類、手続きの流れ、単位の引き継ぎ、編入後につまずきやすい場面への対策までを、親御さんにもわかりやすく整理してお伝えします。
あわせて、お子様の再スタートを支える家庭での関わり方や相談先も紹介します。
焦らず、一歩ずつ。
お子様のペースに寄り添いながら、前に進んでいきましょう。
【この記事でわかること】
通信制高校の『編入』とは何か、転入や再入学との違い
編入の手続き時期と必要書類のそろえ方
空白期間や単位引き継ぎの扱いと注意点
編入後につまずきやすいポイントと、家庭でのサポート方法
お子様の再スタートを支えるために、親ができる行動と相談先
はじめに|高校を中退しても、通信制高校で再スタートできます
高校を途中でやめる決断をしたとき、多くの親御さんは「この先どうなるのだろう」と不安を感じます。
ですが、高校を中退したことは人生の終わりでも、将来を閉ざすものでもありません。
文部科学省によると、全国で44,571人の生徒が高校を中途退学しています。
退学理由として最も多いのは「進路変更」で全体の約3割。
次いで「学校生活への不適応」「学業不振」「体調不良」など、さまざまな背景があります。
(文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」)
つまり、“高校をやめる=挫折”ではなく、“自分に合う環境を探したい”という前向きな選択である場合も多いのです。
そして今は、「もう一度高校に行きたい」と思ったときに学び直せる仕組みが整っています。
その代表が『通信制高校』への編入です。

通信制高校は、年齢やブランクに関係なく再スタートできる制度があり、お子様の「もう一度挑戦したい」という気持ちを受け止めてくれる場所です。
親御さんとしては

またつらい思いをするのでは



ちゃんと続けられるのかな…
と心配になるかもしれません。
そう思うのも、当然のことです。
通信制高校には、学び直す意欲を支える先生のサポートや仕組みがあり、お子様が安心して“自分のペース”で成長していける環境が整っています。
編入は“失敗からのやり直し”ではなく、“未来への再出発”。
一度立ち止まった経験を力に変えながら、子どもが自分らしく前に進める―。
この記事では、そのための最初の一歩を、わかりやすくお伝えしていきます。
通信制高校の「編入」とは?
高校をやめたあと、「もう一度入学できるのかな」「転入と編入ってどう違うんだろう」と迷う方も多いでしょう。
特に通信制高校を検討する際には、これらの制度の違いを理解しておくことが大切です。
なぜなら、仕組みを誤解したまま選ぶと、



思っていたのと違った



こんなはずじゃなかった
と後から戸惑うケースがあるからです。
でも大丈夫です。
仕組みを知れば、「うちの子にはどの方法が合うか」を冷静に判断でき、安心して再スタートの準備ができます。
高校を変わるときには、「転入」「編入」「再入学」といった言葉を目にすることがあります。
どれも“学校に入り直す”ことを指しますが、実は意味が少しずつ異なります。
まずは全体像を整理しておきましょう。
| 用語 | タイミング | 入り直す学校 | 主な対象 | ポイント |
| 転入 | 在学中 | 別の高校 | 途中で学校を変えたい生徒 | 学期途中でも可能 |
| 編入 | 退学後 | 別の高校 | 一度やめて再スタートしたい生徒 | 年齢やブランクに関係なく入学できる |
| 再入学 | 退学後 | 同じ高校 | 元の学校に戻りたい生徒 | 学校の方針や空き状況で制限あり |
この中でも、通信制高校を選んで編入する生徒が少なくありません。
退学後でも受け入れ体制が整っており、年齢やブランクに関係なく再スタートしやすい環境です。
次の章では、この「編入制度」について、仕組みや特徴をもう少し詳しく見ていきましょう。
編入とは?|一度退学してから、別の高校に入り直す制度


「編入」とは、一度高校を退学したあとに、別の高校へ入り直す制度のことです。
すでに高校を離れた生徒が、再び高校教育を受けたいと思ったときに利用できる仕組みで、「もう一度学び直したい」という気持ちを形にできる制度です。
よく似た制度に「転入」がありますが、こちらは在学中に別の高校へ移る場合を指します。
「編入」は退学後に改めて入学し直すケースであり、出願時期や必要書類も異なります。
この違いを理解しておくことで、手続きの流れや準備の見通しが立てやすくなります。
こちらの記事で、『転入』と『編入』の制度的な違いや、どちらを選ぶとよいかを詳しく解説しています。
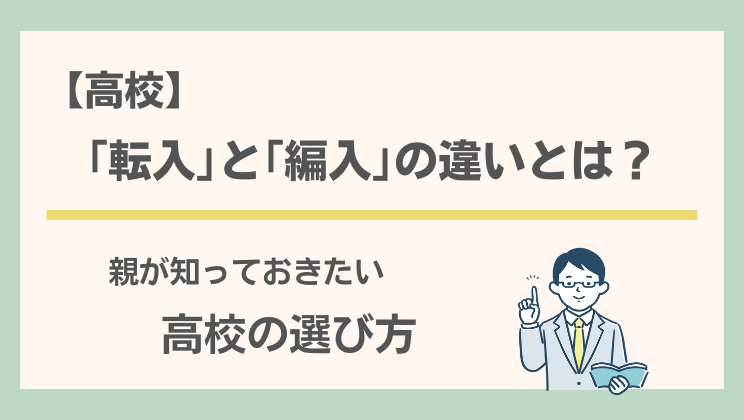
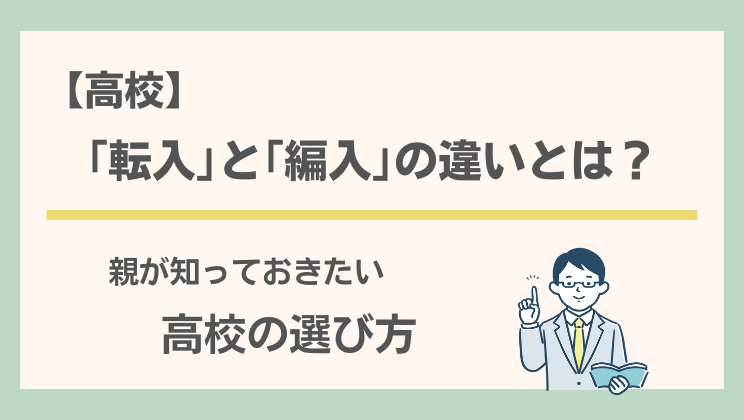
「編入」を選ぶ理由は人それぞれですが、たとえば次のようなケースがあります。
体調や人間関係の問題で高校を離れ、少し休んでから学び直したい
アルバイトや仕事をしながら、高校卒業資格を取りたい
自分のペースで学べる環境に変えたい
学び直して、大学や専門学校への進学を目指したい



編入は“失敗をリセットするやり直し”ではなく、自分に合った学び方を選び直すチャンスです。
通信制高校では、この編入制度を利用する生徒が特に多く、年齢やブランクを問わず受け入れが可能です。
単位制を採用している学校が多く、前の高校で修得した単位を引き継げるため、卒業までの見通しも立てやすいのが特徴です。
また、学力試験よりも意欲や継続力を重視し、「もう一度挑戦したい」という気持ちを大切にする制度として広く活用されています。
再入学との違い
「編入」と混同されやすい言葉に「再入学」があります。
どちらも「一度高校を離れたあとに再び学ぶ」という点では似ていますが、仕組みは少し異なります。


「再入学」は、以前に通っていた“同じ高校”にもう一度入学し直す制度です。
一方、「編入」は、“別の高校”に新たに入る制度を指します。
再入学を選ぶ生徒には、たとえば次のようなケースがあります。
在籍していた学校に信頼できる先生や友人がいるので、同じ学校に戻る方が安心できる
通学環境や人間関係に大きな問題がなかったため、同じ学校で再挑戦したい



再入学は「元の学校での学びを続けたい」という希望を持つ生徒に向いています。
ただし、学校の方針や定員の都合によっては受け入れが難しい場合もあります。
そのため、「編入」制度を利用して新しい環境で再スタートすることが、現実的な選択肢として選ばれやすいです。
次に、編入する際に気になる「単位の引き継ぎ」について見ていきましょう。
単位の引き継ぎルール
編入を考えるとき、親御さんが特に気になるのが



前の高校で取った単位はどうなるの?
という点ですよね。
通信制高校では、これまでに学んだ努力を無駄にしないよう、一定の条件を満たせば単位を引き継げる制度が整っています。
ここでは、単位が認定される条件と、引き継げない場合の注意点をそれぞれ見ていきましょう。
単位が引き継がれる条件


前の高校で修得した単位は、新しい学校が「同等の内容」と認めた場合に引き継ぐことができます。
これは文部科学省の単位認定基準に基づいた仕組みで、たとえば次のような条件を満たすと、単位が認められやすくなります。
同一教科・同等内容の科目である(例:「国語総合」→「国語総合」)
普通科から普通科など、学科が同じである
前籍校で「単位修得証明書」が発行されている
(文部科学省「〔別紙3〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等」)
引き継ぎできない場合の注意点
一方で、カリキュラムの変更があった場合や、科目名が変わっている場合(例:「国語総合」→「現代の国語」など)は、学校の判断で再履修になることもあります。
ただし、通信制高校では自分のペースで学習を進められるため、再履修が必要になっても大きな負担にはなりにくいのが特徴です。
どの単位が引き継げるか不明な場合は、出願前の個別相談や説明会で確認しておくと安心です。
通信制高校への編入を考えるときの最初のステップ
お子様と話し合い、「もう一度高校に通おう」と決めても、いざ動き出そうとすると



何から始めればいいの?
と戸惑ってしまいますよね。
通信制高校への編入は、制度や流れが少し複雑に感じるかもしれませんが、一つひとつ順番に進めていけば、決して難しい手続きではありません。
この章では、編入を考え始めたときにまず取り組みたい3つのステップを、親御さんにもわかりやすく整理してお伝えします。
最初にやるべき3つの準備
通信制高校への編入の手続きをスムーズに進めるために、まず以下の3つを整理しておくと安心です。
① 前の籍校から必要書類を取り寄せる
成績証明書や在学(退学)証明書など、前の高校で発行してもらう書類が必要です。
発行には数日から2週間ほどかかる場合があるため、早めに依頼しておくと安心です。
② 通信制高校の情報を集める
通信制高校といっても、学校によって学び方やサポート体制はさまざまです。
公式サイトを見たり、資料請求をしたり、体験授業や説明会に参加したりして、複数の学校を比較してみましょう。
「どんな雰囲気か」「どんな先生がいるか」は、実際に見てみないとわからないものです。
③ 希望時期と単位の引き継ぎ条件を確認
「いつから通い始めたいか」「前の学校で取った単位はどこまで引き継げるか」を確認しておくことで、卒業までのスケジュールが見えてきます。
通信制高校の多くは随時入学を受け付けていますが、4月・10月入学に合わせると手続きがスムーズです。
これらの準備を、お子様と一緒に進めることで、「やることが見える」安心感が生まれます。
親子で話し合いながら、「どんな学校がいいか」「どんなペースで通いたいか」を確認していきましょう。
通信制高校の学び方や生活面の不安についてはこちらの記事で紹介しています。
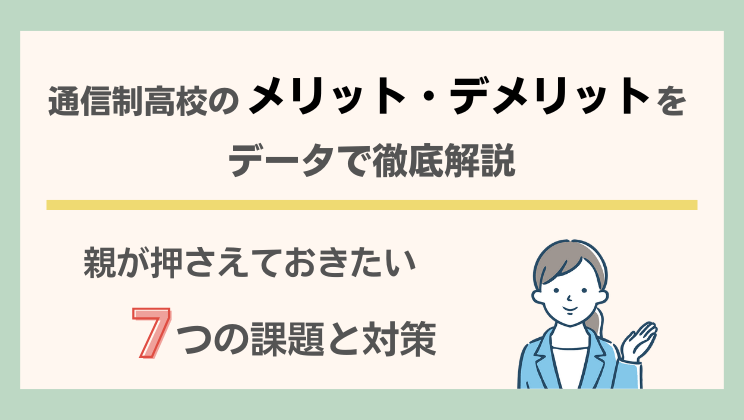
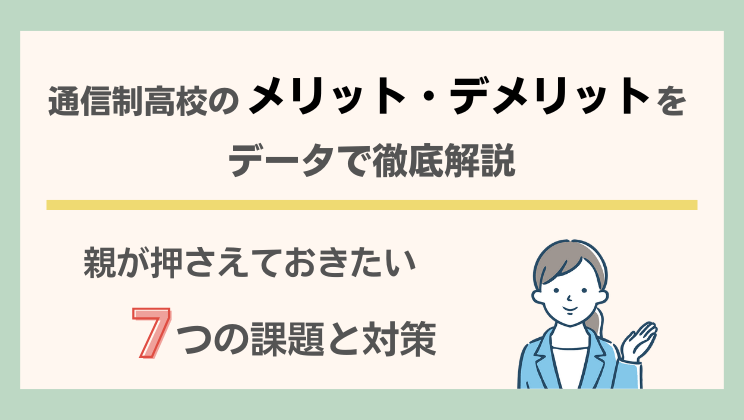
通信制高校への編入手続きの流れ|まずは全体をつかもう
通信制高校への編入は、手続きの流れを理解しておくことが大切です。
全体像を先に把握しておくことで、スケジュールの見通しが立ち、慌てず準備を進めることができます。
ここでは、編入の基本的な流れを5つのステップに分けて整理しました。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| Step1 | 情報収集と比較検討|自分に合う学校を探す | 通信制高校ごとの特徴を調べ、登校スタイル・費用・サポート体制を比較 |
| Step2 | 必要書類の準備 | 前籍校で発行してもらう証明書類を整理 |
| Step3 | 出願手続き | 願書・成績証明書などの提出。オンライン出願対応の学校も増加 |
| Step4 | 選考(面接・作文など) | 学力よりも意欲や目標を重視。リラックスして受け答えを |
| Step5 | 合格発表と入学手続き | 納付・履修登録・オリエンテーションなど、入学後の準備を進める |
この5つのステップを順に進めていけば、初めてでも迷うことはありません。
特にStep1とStep2は、その後の流れをスムーズにする大切な準備段階です。
次の章では、それぞれのステップをもう少し具体的に見ていきましょう。
Step1:情報収集と比較検討|自分に合う学校を探そう
通信制高校といっても、学び方やサポート体制は学校によって大きく異なります。
まずは情報を集めて、「お子様に合う学校」を見つけることが第一歩です。
情報収集のポイント
どんな学校があるのかを知るには、以下のような方法があります。
公式サイトやパンフレットで基本情報を確認する
登校スタイル(週1・在宅・オンラインなど)、学費、スクーリングの場所・回数をチェック
資料請求で比較検討する
複数校の資料を並べてみると、それぞれの特色やサポート内容の違いが見えてきます
体験授業や個別相談に参加する
先生や在校生と話すことで、学校の雰囲気がよりリアルに伝わります
口コミや卒業生の声を参考にする
実際に通った生徒・保護者の感想は、学校選びの判断材料になります
通信制高校には、通学型(週1〜5日登校)と在宅型(オンライン中心)があり、さらにサポート校を併設しているケースもあります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、生活リズムや性格に合わせて選びましょう。
サポート校についてはこちらで説明しています。
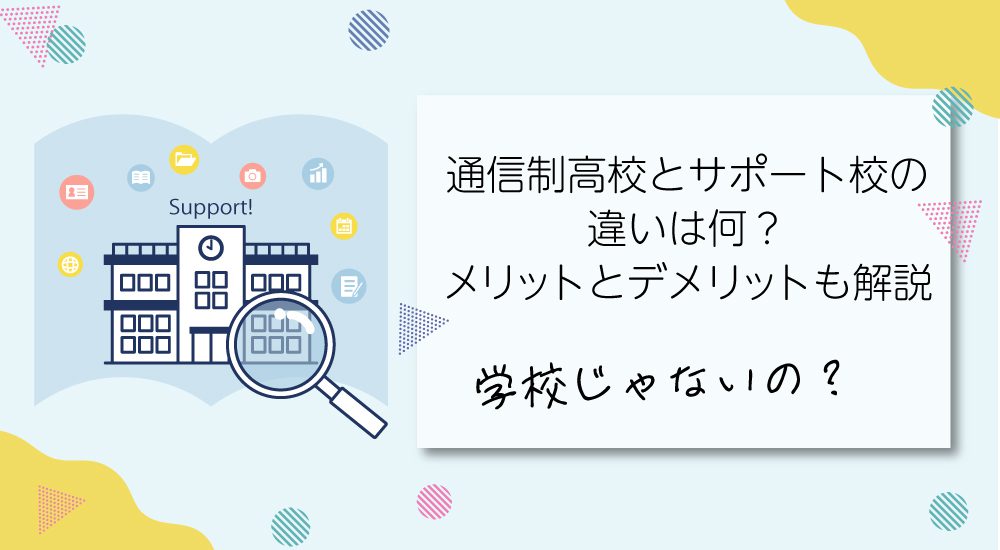
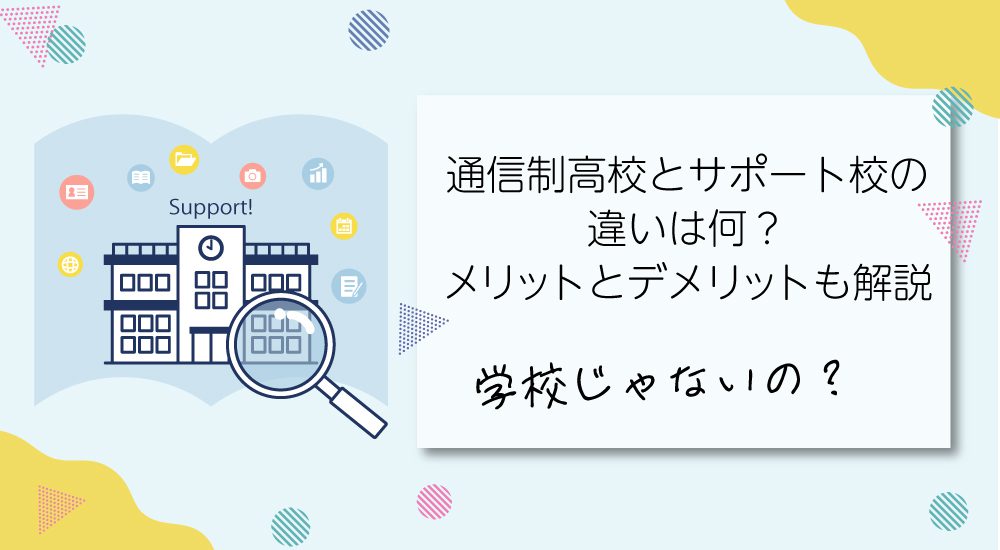
見学・相談のときに確認しておきたいポイント
通信制高校は、学校によって仕組みや雰囲気が大きく異なります。
見学や個別相談のときに、次の項目をチェックしておくと安心です。
登校日数はどのくらい?(週・月・年単位で確認)
通学距離・アクセスは?無理なく通える場所か
担任・カウンセラーなど、サポート体制は整っているか
オンライン授業や在宅学習のサポートはあるか
授業料以外に、サポート校費用・教材費などはかかるか
大学進学や資格取得など、進路サポートはどの程度あるか
Step2:必要書類の準備|手順・注意点を確認しよう
通信制高校への編入では、前に通っていた高校(前籍校)からいくつかの書類を取り寄せる必要があります。
これらの書類は、単位の引き継ぎや入学資格の確認に使われる大切なものです。
スムーズに進めるために、早めの準備をおすすめします。
主な必要書類
| 書類名 | 内容 | 主な用途 |
| 成績証明書 | これまでに履修した教科や単位の内容を示す書類 | 新しい学校で単位を引き継ぐ際の判断材料になる |
| 在籍(退学)証明書 | 在籍していた期間や退学日を証明する書類 | 「転入」か「編入」かを判断するために必要 |
| 単位修得証明書 | 修得済みの単位を証明する書類 | どの科目が認定対象になるかを確認するために使用 |
これらの書類は、前籍校が閉校していても教育委員会が保管している場合があります。
迷ったときは、県や市の教育委員会に問い合わせましょう。
(参考:東京都教育委員会「都立高等学校の閉校等に伴う卒業証明書等諸証明の発行について」)
書類発行の流れ
1. 前籍校に電話またはメールで依頼内容を伝える
2. 申請書を記入・提出(郵送・窓口・Webなど学校によって異なる)
3. 発行までに数日〜2週間ほどかかるのが一般的
4. 封印された状態で届く場合が多いため、開封せずに提出する
発行手数料は1通あたり300〜500円前後。
また、書類には有効期限(おおむね発行から3か月以内)があるため、出願時期に合わせて準備するようにしましょう。
よくあるトラブルと注意点
| よくあるケース | 対応方法 |
| 前籍校が廃校になっている | 教育委員会に問い合わせると、保存期間内であれば発行可能 |
| 書類を紛失した | 教育委員会または統合先の学校に再発行を相談 |
| 発行に時間がかかりすぎる | 編入先の学校に「発行中である旨」を伝え、提出期限の延長を相談 |
| 成績証明書が発行できない | 成績関連書類の保存期間は5年、学籍関連は20年。保存期間を過ぎると再発行できないこともある(文部科学省「学校教育法施行規則」) |
Step3:出願手続き|必要書類とスケジュールを確認しよう
必要な書類がそろったら、いよいよ出願の準備です。
通信制高校の出願は、学校によって時期や方法が異なるため、募集要項をよく確認することが大切です。
出願の時期
通信制高校では、4月入学と10月入学を基本に、年度途中でも「随時編入」を受け付けている学校が多くあります。
| 出願時期 | 特徴 |
| 4月入学(前期) | 新年度スタート。出願は1〜3月ごろに集中。 |
| 10月入学(後期) | 学期の区切りに合わせて再スタートしやすい。出願は7〜9月ごろ。 |
| 随時入学 | 学校独自のタイミングで随時受付。柔軟だが、希望時期を事前に相談すると安心。 |
年度途中で編入したい場合は、単位の引き継ぎやスクーリング日程にも影響するため、希望時期を早めに伝えておくのがポイントです。
出願に必要な主な書類
出願時には、Step2で準備した書類(成績証明書・在籍(退学)証明書・単位修得証明書)に加えて、以下のようなものを提出します。
通信制高校によっては、オンライン出願に対応している学校もあり、書類の郵送が不要な場合もあります。
願書(学校指定の用紙またはWebフォーム)
写真(3か月以内に撮影した証明写真)
志望理由書または作文(テーマは学校によって異なる)
受験料の納付書
出願時のチェックポイント
通信制高校によって出願方法は少しずつ異なります。
以下のポイントを確認しながら準備を進めましょう。
提出期限を必ず確認
郵送の場合、「消印有効」か「必着」かを必ずチェック。期日を過ぎると受理されないこともあります。
書類に不備がないか再確認
特に証明書類の有効期限や押印漏れに注意しましょう。コピーではなく原本が必要な場合もあります。
志望理由書は本人の言葉で書く
「なぜ通信制を選んだのか」「どんな学び方をしたいのか」を簡潔に伝えることが大切です。
保護者欄の署名・押印を忘れずに
申請者本人と保護者の両方の署名が必要な場合が多いので、記入漏れがないか確認を。
志望動機の書き方については、こちらを参考にしてください。
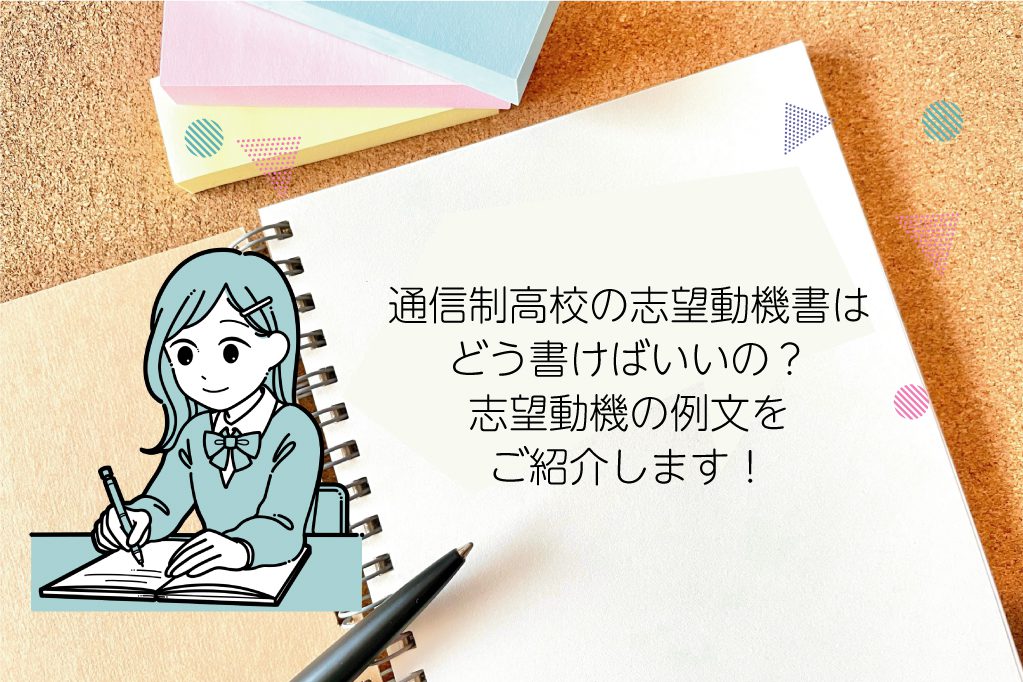
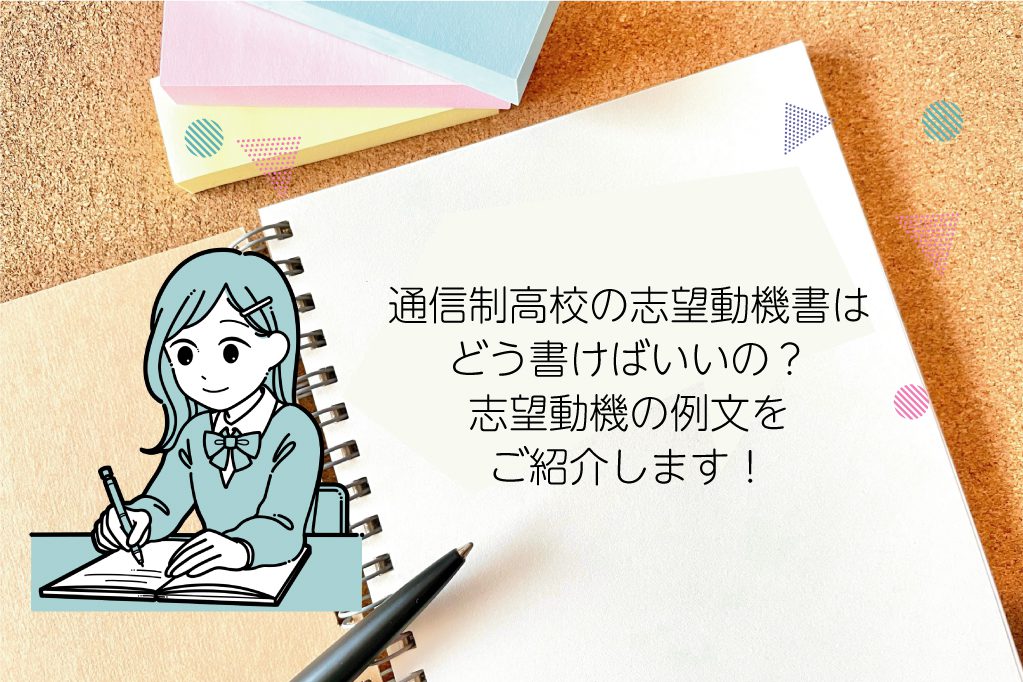
Step4:選考(面接・作文など)|意欲を見せるポイントを押さえよう
通信制高校の選考は、学力テストよりも「意欲」や「目的意識」が重視されます。
学力よりも、これからどう学びたいか・どんな生活を送りたいかという姿勢を見ています。
面接でよく聞かれる質問
なぜ通信制高校を選びましたか?
これからどんな学び方をしたいですか?
将来どんな進路を考えていますか?
今の生活で頑張っていることはありますか?



どれも「正しい答え」を求める質問ではありません。
「こういう学び方なら続けられると思う」「将来は○○を目指したい」など、気持ちを自分の言葉で伝えられれば十分です。
作文・志望理由書で大切にしたいポイント
作文や志望理由書では、次の3つを意識すると伝わりやすくなります。
① きっかけ:「高校を辞めてからどう感じたか」「なぜ通信制で学びたいと思ったか」
② 目標:「どんな力を身につけたいか」「卒業後にどうなりたいか」
③ 姿勢:「無理のないペースで頑張りたい」「続ける努力をしたい」



文章の上手さよりも、「前を向いている気持ち」が伝わることが大切です。
学校側も、お子様の「これからの意欲」を見たいと考えています
親御さんは、面接や作文の準備を“手伝いすぎない”こともポイント。
お子様が自分の言葉で考える時間を尊重することが、前向きな再スタートにつながります。
面接や作文については、こちらで詳しく解説しています。
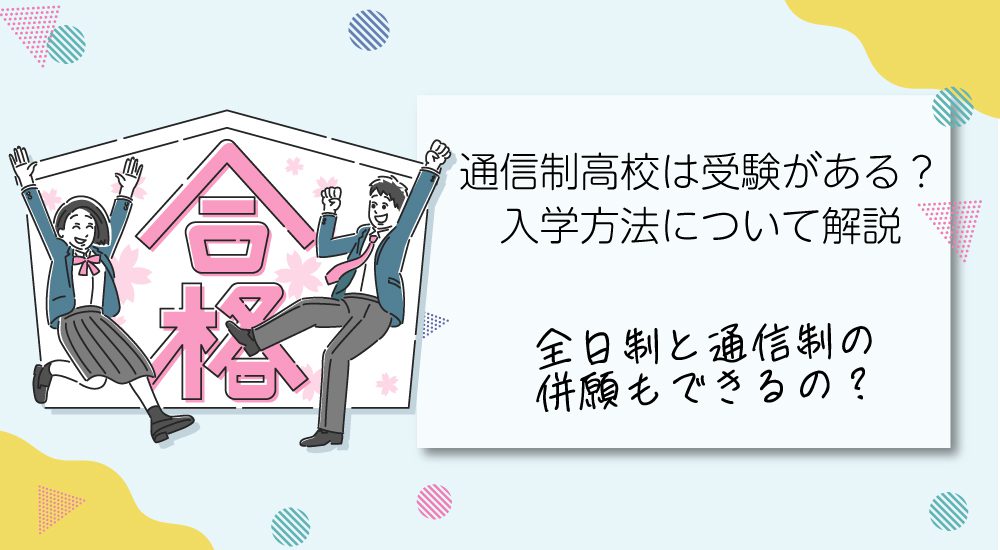
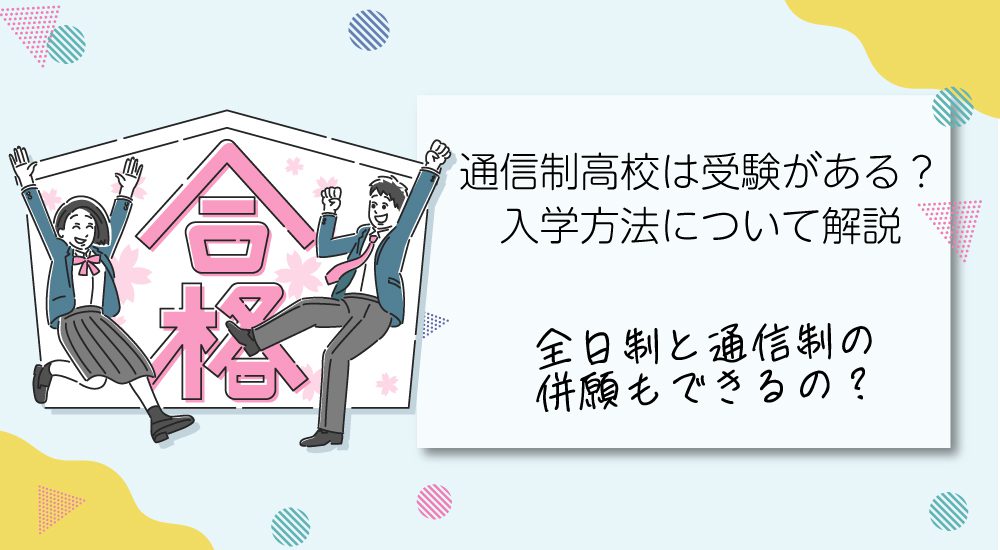
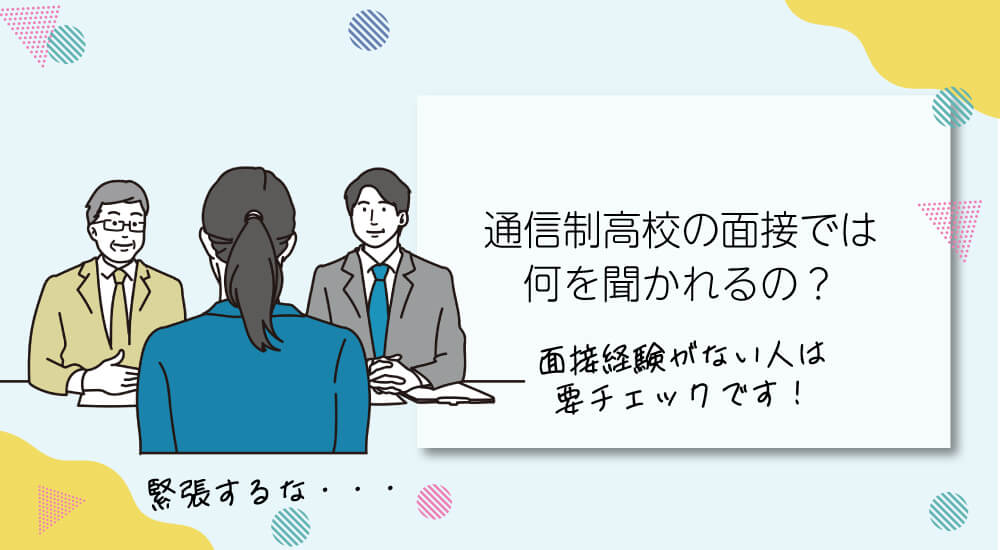
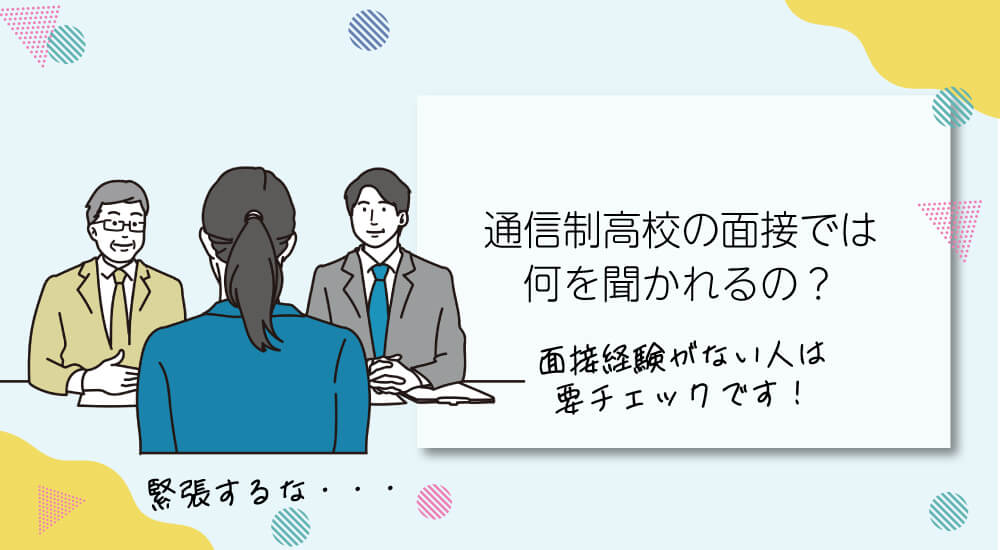
Step5:合格発表と入学手続き|入学までに必要な準備を整えよう
合格通知が届いたら、いよいよ新しいスタートの準備です。
期限内に手続きを済ませることが大切なので、スケジュールを確認しながら進めましょう。
入学手続きの基本ステップ
入学手続き書類の提出
合格通知と一緒に届く案内に従い、入学願書・誓約書・写真・振込証明書などを提出します。
提出期限は学校によって異なりますが、期日を過ぎると入学が取り消されることもあるため要注意です。
学費の納付
入学金・授業料などの納付期限も必ず確認しましょう。
公立は数万円程度、私立の通信制高校は20〜40万円前後が目安です。
教科書や教材の準備
履修登録後に教科書リストが配布されます。指定書店で購入する学校もあれば、入学時に一括配布される場合もあります。
オリエンテーション・初登校の確認
初登校日は、入学前オリエンテーションやガイダンスを兼ねている場合があります。
持ち物や集合時間など、案内書類をしっかりチェックしておきましょう。
通信制高校の学費については、こちらをご覧ください。
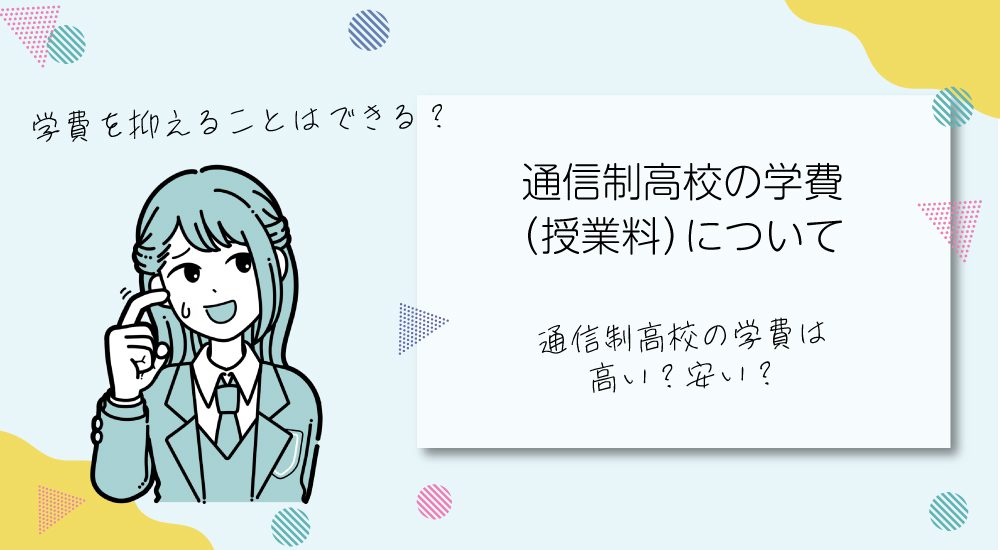
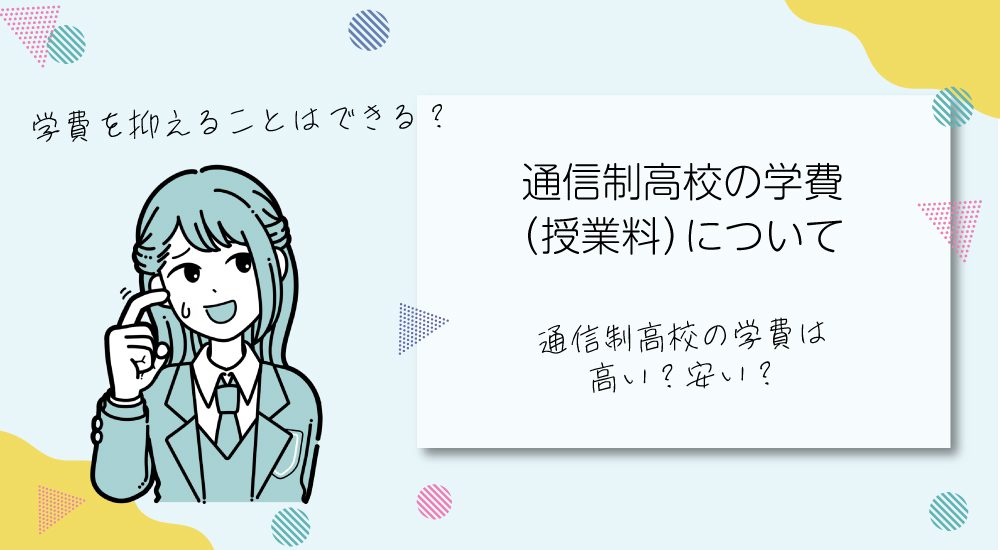
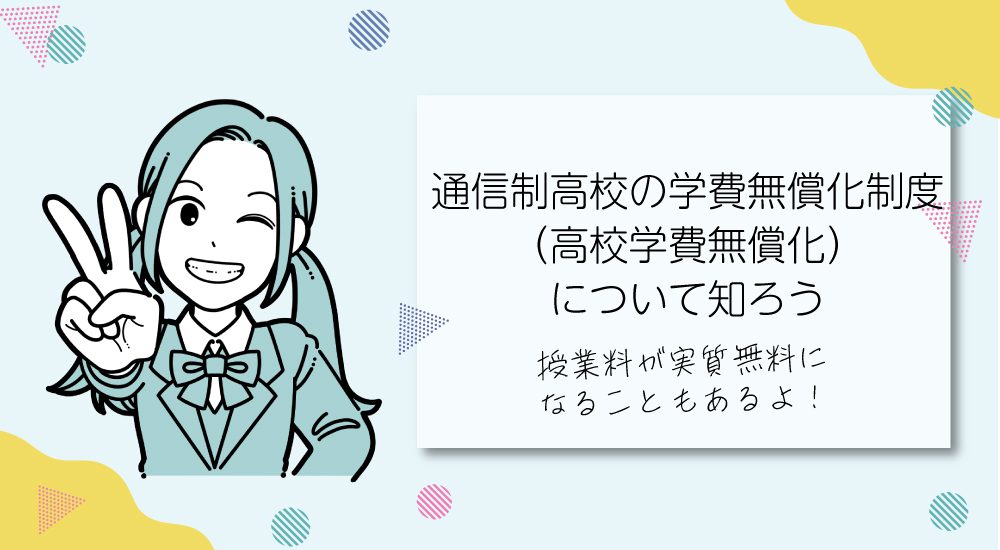
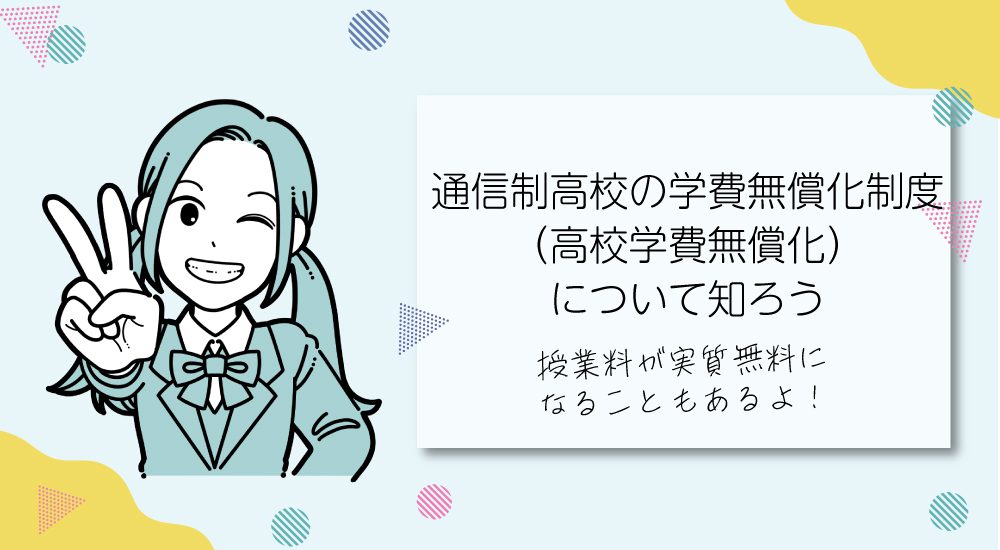
事例で見る|通信制高校への編入で再スタートした生徒たちの歩み
通信制高校への編入を考えるとき



実際に通い始めたらどうなるの?
という不安を感じる方も多いでしょう。
ここでは、通信制高校へ編入した生徒のよくあるケースをもとに、個人を特定できないよう配慮し再構成した事例を2つ紹介します。
「うちの子にもこんな可能性があるかも」とお子さんの状況に重ねながらご覧ください。
ケース①:高校1年で中退→通信制に編入し、再び前を向けたサクラさん(17歳)
高校1年の秋、人間関係のトラブルがきっかけで登校が難しくなり、中退を選んだサクラさん。
自宅で過ごす日々が続き、「自分はもうダメかもしれない」と自信を失っていました。
そんなとき、親御さんと一緒に通信制高校の個別相談に参加。
「自分のペースで通える」「先生が話を聞いてくれる」環境に安心感を覚え、編入を決意しました。
入学後は、週2日の登校とオンライン授業を組み合わせ、少しずつ生活リズムを取り戻していきます。
先生との面談を重ねるうちに、「大学で心理学を学びたい」という新しい目標も生まれました。


環境を変えることで、お子様はもう一度前を向けます。
焦らず、支えてくれる大人の存在があれば、再スタートを切ることができます。
ケース②:1年間のブランクを経て、通信制で少しずつ学び直したショウタさん(18歳)
高校2年の春、体調不良と登校ストレスでやむを得ず退学したショウタさん。
その後1年間は自宅療養中心の生活でしたが、少しずつ体調が整い、「もう一度勉強してみたい」と思うようになります。
通信制高校に編入後は、週1回の登校と在宅課題からスタート。
最初は不安もありましたが、担任の先生やカウンセラーが定期的に声をかけてくれたことで安心して続けられました。
半年が過ぎるころには、登校日数を週2日に増やし、クラスメイトと少しずつ交流する姿も。
「焦らず、自分のペースで進めばいい」という実感が、次の目標への意欲につながりました。


学び直しに“遅すぎる”ということはありません。
どんなに時間がかかっても、再出発のタイミングは自分で決めていいのです。
編入後に気をつけたいポイントとよくあるつまずき
通信制高校への編入が決まり、新しい生活が始まると、ほっとする一方で



ちゃんと続けられるかな…
という不安が出てくることがあります。
実際、編入後の数か月は、生活リズムや気持ちがまだ落ち着きにくい時期です。
これはめずらしいことではありません。
環境が変われば、誰でも少なからず戸惑うもの。
大切なのは、完璧を目指すことではなく、少しずつ「自分のペース」を取り戻すことです。
この章では、通信制高校に編入した生徒がつまずきやすいポイントと、保護者ができる見守り方を紹介します。
ポイントは次の3つです。



①焦らない
②比べない
③相談する
子どもの変化を「心配」ではなく「成長の途中」と捉える視点を持てば、サポートはぐっとしやすくなります。
焦らず、一緒に少しずつ整えていきましょう。
焦って授業を詰め込みすぎない
通信制高校に編入したばかりの頃は、「早く追いつかなきゃ」「遅れを取り戻したい」と焦る気持ちが出やすい時期です。
特に中退やブランクを経験したお子様ほど、その思いは強くなりがちです。
ですが、無理に単位を詰め込みすぎると、疲れがたまりやすく、かえって続かなくなることもあります。
通信制高校は、自分のペースで履修を進められる柔軟な仕組みです。



最初のうちは“頑張りすぎないこと”が、長く続けるためのコツになります。
履修の計画は、担任や学習サポートスタッフと一緒に立てると安心です。
「どの科目をどの時期に取るか」「どのくらいのペースが負担にならないか」を話し合いながら決めましょう。
必要に応じて、科目数を減らす・レポート提出を分散するなどの調整もできます。
焦って単位を詰め込みすぎない
生活リズムを整えることを優先する
担任やスタッフに相談して、無理のない計画を立てる
焦らず続けることが、最短の道です。
親御さんが「今は少しずつでいいよ」と声をかけてあげると、お子様は安心して新しい生活に慣れていけます。
人間関係に不安を感じたときの相談先
通信制高校でも、人間関係に悩む生徒は少なくありません。
登校日数が少ない分、友人づくりのきっかけが限られたり、オンライン中心の学び方に慣れるまで時間がかかったりすることがあります。
そんなとき、親として「子どもがどこに相談できるか」を知っておくことが大切です。
学校には、担任の先生のほかにも、スクールカウンセラーやサポートスタッフなど、話を聞いてくれる大人がいます。
もしお子様が悩んでいる様子があれば、「一人で抱え込まずに、先生やカウンセラーに相談してみようか」とやさしく声をかけてみてください。
担任の先生→学習面だけでなく、生活や人間関係の悩みも相談できる
スクールカウンセラー→気持ちの整理やストレスの相談に専門的に対応
サポートスタッフ→登校や課題提出など、日常的な支援を担当
保護者→家庭で“聞き役”になるだけでも、子どもは安心できる
お子様が親御さんに話をしてきたときには、「どうしたの?」と原因を聞くよりも、まずは「そう感じたんだね」「つらかったね」と受け止めてあげましょう。
共感の言葉をかけることで、「話しても大丈夫なんだ」という安心感が生まれます。
また、学校で相談しづらいときは、外部の相談機関を利用することもできます。
目標を見失った子どもを支える親のサポート方法
編入後しばらくすると、最初の緊張がほぐれて少しずつ慣れてくる一方で



何のために通っているんだろう



将来どうしたいのか分からない
と、目標を見失ってしまう生徒も少なくありません。
そんなときに大切なのは、焦らせず、比べず、話を聞くことです。
① 焦らせない
「せっかく編入したのに」「もう少し頑張らなきゃ」と急かしてしまうと、お子様は「期待に応えなきゃ」と感じ、かえってプレッシャーになることがあります。
焦りは回復の敵。まずは、今のペースで続けていること自体を認めてあげましょう。
声かけの例



少しずつでも通えているね



今のペースでいいよ
② 比べない
友達やきょうだいと比べて、つい「○○くんは進学準備をしているのに…」と口にしてしまうと、お子様は自信を失ってしまいます。
比べる対象は“他人”ではなく、“昨日の自分”。
小さな成長に気づいたときに



できるようになったね
と伝えるだけで、自己効力感が育ちます。
自己効力感を育てるお子様の声かけについてはこちらの記事で紹介しています。
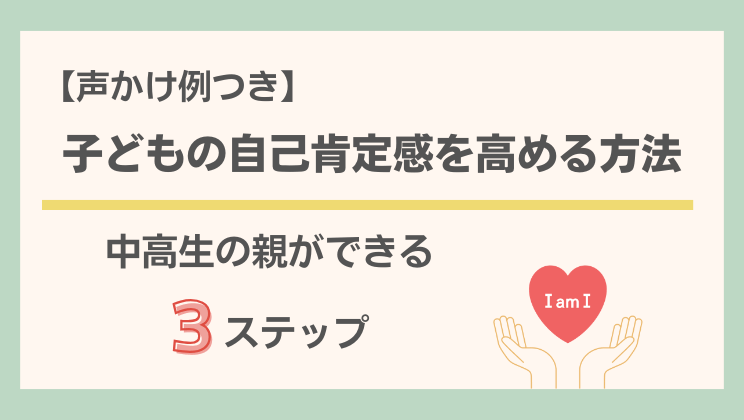
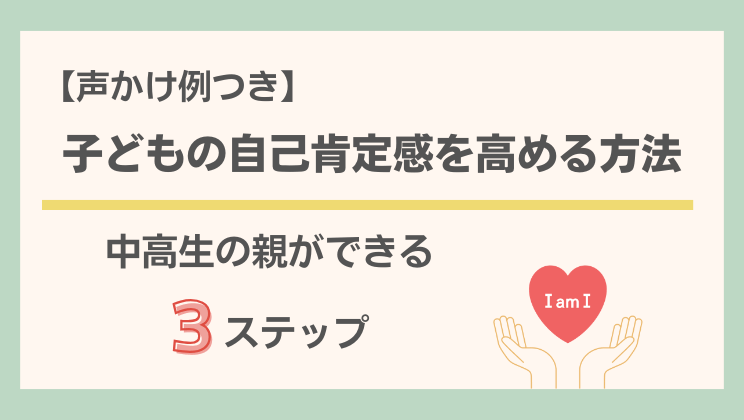
③ 話を聞く
お子様が言葉に詰まっても、無理にアドバイスをしようとしなくて大丈夫です。
「どうしたらいいか分からない」という言葉の裏には、「分かってほしい」「聞いてほしい」という気持ちが隠れています。
ただ静かに聞き、共感するだけで、お子様は安心して気持ちを整理できます。
この時期の子どもは、「立ち止まっているようで、心の中では次の一歩を探している」状態です。


焦らず、比べず、話を聞く。
この3つの姿勢が、お子様が再び自分の道を見つけるための土台になります。
【Q&A】通信制高校への編入でよくある質問
- 高校を中退した後、空いている期間は長くても編入できますか?
-
はい、可能です。
通信制高校は年齢やブランクに関係なく入学できる仕組みを整えています。
たとえ数年空いていても、「高校卒業資格を取りたい」という意欲があれば、再スタートが可能です。詳しくはこちらで解説しています。
通信制高校の「編入」とは? - 編入できる時期はいつですか?
-
通信制高校は随時入学が基本ですが、主なタイミングは4月・10月です。
この時期は受け入れ枠が多く、手続きもスムーズに進みます。
一方で、学校によって出願締切が異なるため、早めの情報収集が大切です。出願手続きの流れはこちらで詳しく紹介しています。
通信制高校への編入手続きの流れ|まずは全体をつかもう - 単位はどこまで引き継げますか?
-
前の高校で修得した単位が、同一または類似の科目であれば認定される場合が多いです。
ただし、科目名や内容が改訂されている場合は再履修になることもあります。詳しくはこちらをご参照ください。
単位の引き継ぎルール - 試験や面接は難しいですか?
-
通信制高校の選考では、学力よりも意欲や生活面の安定を重視します。
面接では「なぜ編入したいか」「どんな学び方をしたいか」を素直に伝えれば大丈夫です。
作文も同様に、“等身大の言葉”で気持ちを表現することが評価されます。面接の流れはこちらで紹介しています。
通信制高校の編入手続き|Step4:選考(面接・作文など) - 費用はどれくらいかかりますか?
-
目安は次の通りです。実額は学校・コースで差があります。
公立の通信制:年間の授業料は数万円程度(教科書代・スクーリング交通費などは別途)
私立の通信制:年間およそ30〜80万円前後が目安(入学金・授業料・施設費・教材費などを合算)
サポート校を併用:通信制高校(本校)とは別契約で、月謝・指導料などが追加発生確認ポイント就学支援金などの学費支援制度の対象か
納付タイミング(入学金・授業料の支払い時期
分納可否や奨学金制度の有無
スクーリングの交通費や教材費などの実費項目※費用の全体像は見積書で総額と年/学期/月の内訳を確認すると安心です。
- 通信制高校に編入しても大学進学はできますか?
-
はい、十分可能です。
通信制高校の卒業資格は全日制・定時制と同等で、すべての大学入試方式(総合型・推薦・一般)に出願できます。通信制高校からの大学進学についてはこちらで詳しく解説しています。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
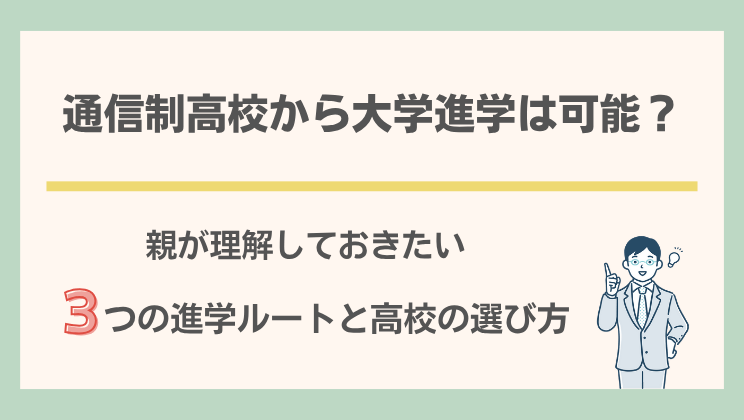 通信制高校から大学進学は可能?|親が理解しておきたい3つの進学ルートと高校の選び方 | 【公式】ID学園… 通信制高校からでも大学進学は十分に可能です。入試制度の仕組みや3つの進学ルート、学校・コース選びのポイントをわかりやすく解説。受験対策やサポート体制、先輩の実例…
通信制高校から大学進学は可能?|親が理解しておきたい3つの進学ルートと高校の選び方 | 【公式】ID学園… 通信制高校からでも大学進学は十分に可能です。入試制度の仕組みや3つの進学ルート、学校・コース選びのポイントをわかりやすく解説。受験対策やサポート体制、先輩の実例… - 学校に通えなくなった場合、再び退学になってしまいますか?
-
通信制高校では、体調や家庭の事情に合わせて登校頻度を柔軟に調整できます。
長期欠席が続いても、担任やカウンセラーと相談しながら在籍を続けられるケースが多いです。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
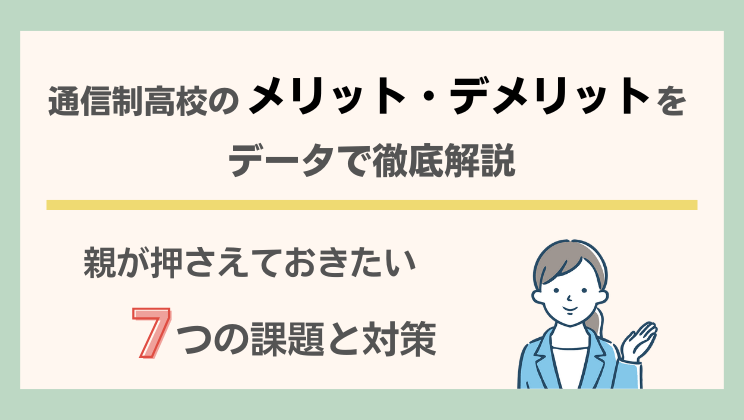 通信制高校のメリット・デメリットをデータで徹底解説|親が押さえておきたい7つの課題と対策 | 【公式】I… 通信制高校のメリット・デメリットをデータに基づいて解説。自己管理・友人関係・学習ペースなど入学前に知っておきたい注意点と、安心して続けるためのサポート方法を紹介…
通信制高校のメリット・デメリットをデータで徹底解説|親が押さえておきたい7つの課題と対策 | 【公式】I… 通信制高校のメリット・デメリットをデータに基づいて解説。自己管理・友人関係・学習ペースなど入学前に知っておきたい注意点と、安心して続けるためのサポート方法を紹介… - ブランクが長くても友達はできますか?
-
できます。通信制は年齢や背景が多様で、「はじめまして」のスタートが日常です。
関わりやすい場から少しずつでOKです。ホームルーム・ゼミ活動:少人数で参加しやすい
探究・作品発表・ボランティア:共通のテーマで自然に会話が生まれる
オンライン交流(チャット/面談):対面が不安な時期の“入口”に向く
登校日を固定:同じ顔ぶれに会える頻度が増え、関係が育ちやすい親御さんは「無理に広げなくていいよ。まず“安心できる場所”ができれば十分」と声をかけ、
小さな関わりを後押ししてあげてください。 - 通信制高校と定時制高校、どちらが編入しやすいですか?
-
どちらも編入可能ですが、通学頻度の柔軟さや学び方の自由度を重視するなら通信制が向いています。
「生活リズムを整えたい」場合は定時制も選択肢に入ります。定時制高校との違いについてはこちらで説明しています。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
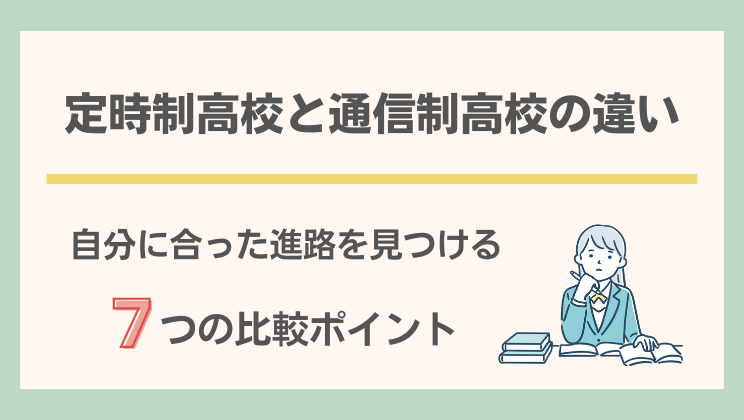 定時制高校と通信制高校の違い|自分に合った進路を見つける7つの比較ポイント | 【公式】ID学園高等学校_… 定時制高校と通信制高校の違いをわかりやすく比較。通学ペース・学費・サポート体制など7つの観点から、お子様に合った学び方を見つけるためのポイントを紹介します。
定時制高校と通信制高校の違い|自分に合った進路を見つける7つの比較ポイント | 【公式】ID学園高等学校_… 定時制高校と通信制高校の違いをわかりやすく比較。通学ペース・学費・サポート体制など7つの観点から、お子様に合った学び方を見つけるためのポイントを紹介します。 - 通信制高校に編入するメリットやデメリットはありますか?
-
通信制の最大のメリットは「自分のペースで学べる自由さ」です。
一方で、自己管理の難しさや孤立感を感じることもあります。通信制高校の良さと課題についてはこちらで解説しています。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
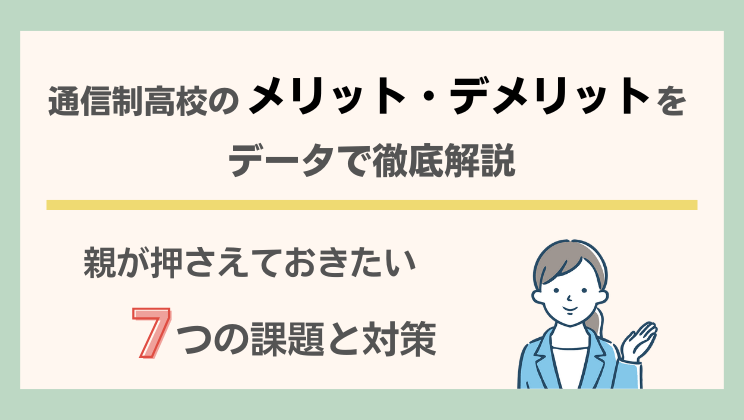 通信制高校のメリット・デメリットをデータで徹底解説|親が押さえておきたい7つの課題と対策 | 【公式】I… 通信制高校のメリット・デメリットをデータに基づいて解説。自己管理・友人関係・学習ペースなど入学前に知っておきたい注意点と、安心して続けるためのサポート方法を紹介…
通信制高校のメリット・デメリットをデータで徹底解説|親が押さえておきたい7つの課題と対策 | 【公式】I… 通信制高校のメリット・デメリットをデータに基づいて解説。自己管理・友人関係・学習ペースなど入学前に知っておきたい注意点と、安心して続けるためのサポート方法を紹介…
まとめ|焦らず、一歩ずつ前へ。編入は“新しい学びの設計”
高校に編入するという選択は、決して「失敗をやり直すこと」ではありません。
それは、自分に合った学び方や環境を見つけ直し、新しいスタートを切るための再設計です。
通信制高校では、年齢やブランクに関係なく学び直せる制度が整っており、お子様の「もう一度挑戦したい」という気持ちを大切に受け止めてくれます。
焦らず、比べず、一歩ずつ。
親御さんが寄り添いながらサポートすることで、お子様は自分のペースで確実に前へ進んでいけます。
【この記事のポイント】
編入は「やり直し」ではなく、自分に合う学びを選び直す再スタート
通信制高校なら年齢やブランクに関係なく学び直せる
前籍校での単位を引き継ぎ、卒業までの見通しを立てやすい
編入の流れ(書類準備〜出願〜入学)は5ステップで整理できる
保護者は「焦らず・比べず・相談する」姿勢でサポートを
【ID学園】安心して“再スタート”できる3つの理由
ID学園は、“学び直しやすい環境設計”を重視している学校です。
「柔軟な学習スタイル」「担任制によるサポート」「ID型夢教育」という3つの柱で、多様な生徒を支えています。
① 月ごとに学び方を変えられる“柔軟な仕組み”
通学型・オンライン型を毎月変更できるため、体調や生活リズムに合わせて無理なく続けられます。


② 担任制とオンライン支援による“人のつながり”
全コースで担任制を導入。Slackなどのツールを使い、先生にいつでも相談できます。
また、「メンタルサポートネット」では、電話・ビデオ通話・メール・チャットなど、状況に合わせた方法で専門カウンセラーに相談できます。


③ 郁文館夢学園グループの「ID型夢教育」で“未来につながる学び”
“夢を実現する力”を育てる教育理念のもと、大学進学・資格取得・探究活動などを幅広くサポート。
「卒業するだけで終わらない」学びが、次の成長へとつながります。


編入は、お子様にとっても親御さんにとっても、大きな決断です。
「もう一度、前を向いて歩きたい」という気持ちを応援する環境が、ID学園にはあります。
まずは説明会や個別相談で、お子様に合った学び方を一緒に見つけてみませんか?