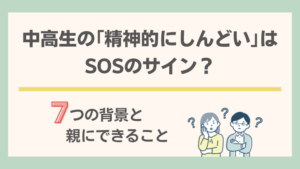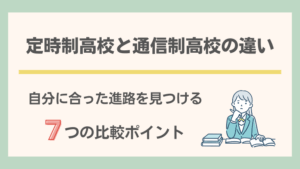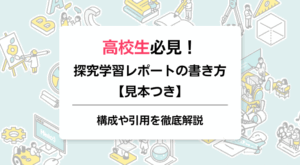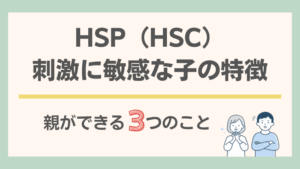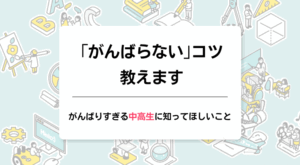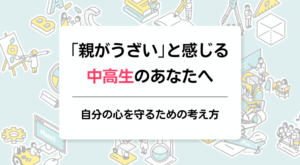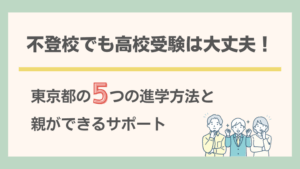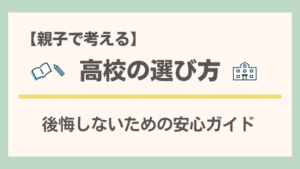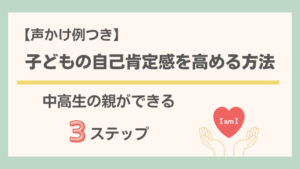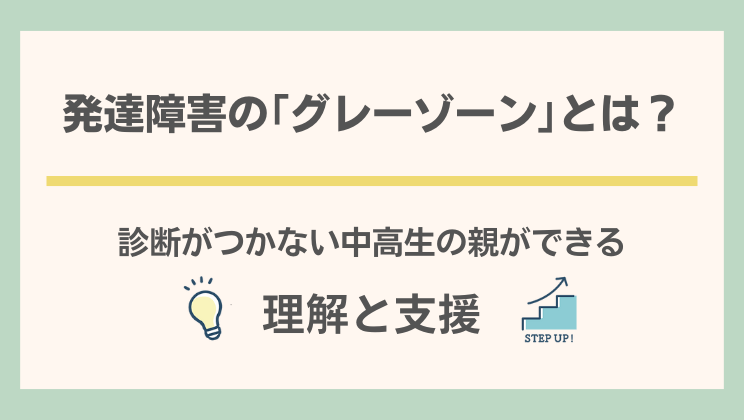
「診断はつかないけれど、学校生活で困りごとが多いんだよね」
「発達障がいではないと言われたのに、どうしてこんなに大変なんだろう…」
そんな迷いや不安を抱えている親御さんは、とても多いものです。
特に“グレーゾーン”と呼ばれる子どもたちは、一生懸命がんばっていても成果につながらず、周囲から誤解されやすいことがあります。
そのたびに「やっぱり育て方のせい?」とご自分を責めてしまう親御さんも少なくありません。
でも本当は、困りごとがあるのは“親のせい”ではなく、脳の働き方や発達の特性によるものです。
診断の有無にかかわらず、「困っている」という事実は確かにあり、その子どもたちには支援や工夫が必要なのです。
この記事では、グレーゾーンの中高生に見られる特徴や誤解されやすいポイント、そして家庭でできるサポートの方法を、できるだけわかりやすく紹介します。
まずは「うちの子だけじゃない」「困りごとを一緒に受け止めていいんだ」と、少しでも安心していただけたらと思います。
なお、『発達障害』の表記については、行政の動きにならい、本文では『発達障がい』とひらがな表記で統一しています。
【この記事でわかること】
グレーゾーンとはどういう状態か(正式な診断との違い)
中高生に多い特徴(学習・対人関係・生活面など)
誤解されやすい困りごとと、その背景にある特性
診断がなくても受けられる支援や家庭でできる工夫
保護者が安心してサポートするための考え方
発達障がいの『グレーゾーン』とは?
診断はつかないけれど、日常生活や学校生活で困りごとが多い
そんな子どもたちを説明するために使われるのが、『グレーゾーン』という言葉です。

『グレーゾーン』は、発達障がいの特性がいくつか認められるものの、診断基準すべてにあてはまるわけではないため、確定診断には至らない状態を指す言葉です。
つまり、白(発達障がいではない)でも黒(診断がつく発達障がい)でもない、ちょうど中間にある状態なので 『グレーゾーン』と呼ばれています。
医学的な診断名ではなく、教育や支援の現場で広く使われる表現であるため、医師や専門家によって使い方が異なる場合もあります。

うちの子は診断がついていないけれど、特徴があるかもしれない…
と不安に思う方は、発達障がいの種類ごとの特性を知ることで理解が深まり、安心につながることもあります。
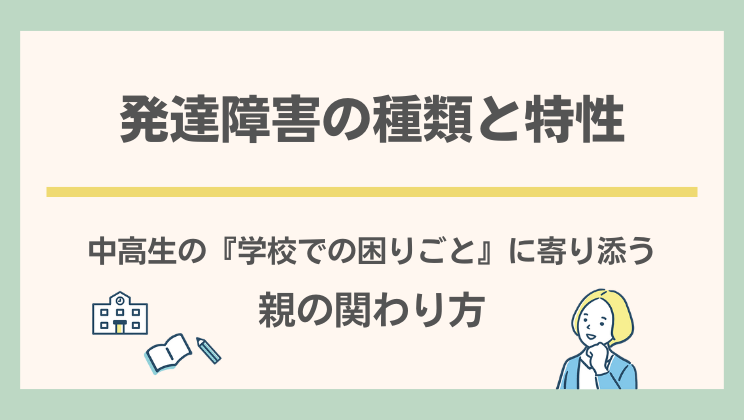
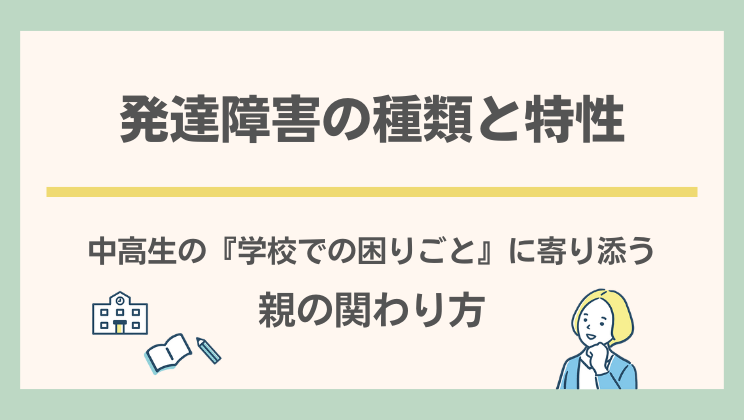
グレーゾーンは『怠けている』『性格の問題』ではなく、脳の働き方や発達の特性によるものだと理解できると、親御さんが感じやすい「育て方のせいかも…」という不安も、少しずつ和らいでいくでしょう。
文部科学省の調査によると、通常学級に在籍する小中学生の約8.8%が「発達障害の可能性があり、特別な教育的支援を必要としている」と報告されています。
高校生でも約2.2%が該当しており、進学後も一定数の子どもが困りごとを抱えていることがわかっています。
さらに、平成24年度の調査(小中で約6.5%)と比べても増加傾向にあり、診断がなくても支援が必要な子が確実に増えていることが示されています。
(文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」令和4年 12 月)
特に高校では、学習内容の難易度や進路へのプレッシャーが大きくなるため、それまで目立たなかった困難が表面化することもあります。
つまり大切なのは、『診断があるかどうか』ではなく、目の前のお子様が抱えている“困りごと”にどう寄り添うかという視点です。
では実際に、グレーゾーンの中高生にはどのような特徴があるのかを見ていきましょう。
グレーゾーンの中高生に見られる特徴
【グレーゾーンの子どもたちの共通点】
診断基準を満たさないために『発達障がい』とは言われないけれど、日常生活や学校生活の中で困難を抱えている
ただし、その表れ方は一人ひとり異なります。
勉強面でつまずきが多い子もいれば、友だちとの関係がうまくいかない子、『だらしない』と誤解される子もいます。
いずれの場合も『努力不足』と見られてしまいやすく、親御さんも「どうしてできないのだろう…?」と悩んでしまうことが少なくありません。


この背景には、実行機能(計画・整理・記憶・切り替えの力)の未熟さや、脳の働き方の特性が関係している場合が多いのです。
グレーゾーンの特徴は軽く見えることもあり、教師や親が見逃してしまうこともあります。
しかし適切な支援がないと、『不登校』『自尊感情の低下』『気分の落ち込み』といった困難につながることもあります。
ここからは、グレーゾーンの中高生に表れやすい特徴を【学習面】【対人関係】【生活習慣】の3つの点から見ていきましょう。
学習面の特徴
【学習面での困りごと】
宿題や提出物を忘れてしまう
ノートがうまく整理できない
テスト勉強の計画が立てられない
親御さんから見ると



やればできるのに、どうして続かないの?
と感じてしまうかもしれません。
ですが、これは決して怠けや性格のせいではありません。
こうした困りごとの背景には、実行機能と呼ばれる力が関係していることがあります。


『実行機能』とは、「行動や思考、気持ちを整理し、計画的に進める力」のこと。
予定を立てたり、やることを順番にこなしたり、必要なものを忘れずに準備したりするときに使われる力です。
この力は、多くの中高生にとってまだ発達の途中にあり、「わかっているのにできない」という状況は誰にでも起こりえます。
たとえば



提出物を完成させることはできても、カバンに入れ忘れて提出できない…
といったケースです。
こうした困りごとは、お子様の努力不足ではなく、発達段階で多くの子に見られるものです。
ただし、程度や表れ方には個人差があり、強く出る子もいれば目立たない子もいます。
だからこそ、『努力が足りない』という視点だけでなく、その子なりの特性に合わせた工夫が必要になります。
学習面の工夫については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。
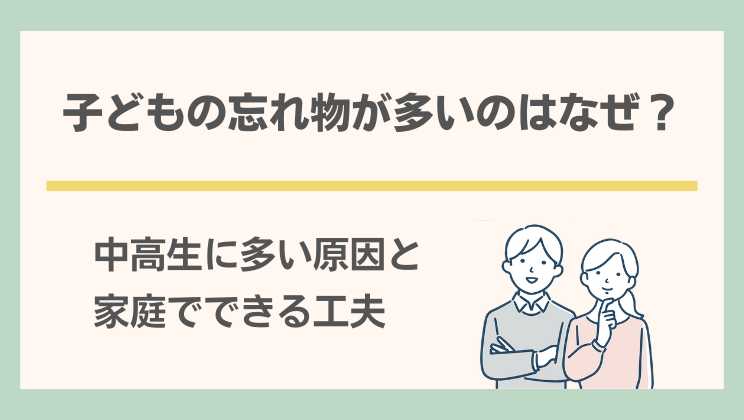
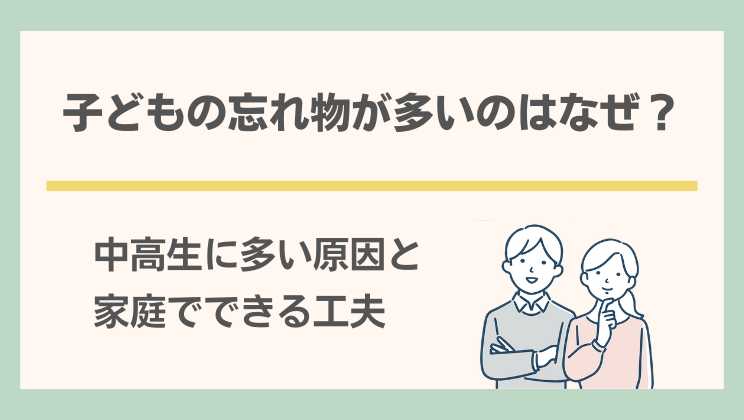
対人関係の特徴
【対人関係での困りごと】
相手の気持ちを読み取るのが苦手で誤解が生じる
場面に合った距離感をつかみにくく、周囲から「空気が読めない」と言われてしまう
グレーゾーンの子どもたちは、友だちや先生との関わりの中でつまずきを感じやすいことがあります。
本人にとっては一生懸命なのにうまくいかず、友人関係が長続きしなかったり、孤立感につながったりすることもあります。



周りの友達は普通にできるのに、自分だけできない
と感じてしまうと、心のしんどさが大きくなり、自己否定感につながることもあります。
こうした対人面の困りごとは、努力不足ではなく『相手の気持ちをつかむ力』や『状況を読み取る力』がまだ発達途中にあるために起こるものです。
そのため、家庭では「どうしてできないの?」と責めるのではなく、安心して気持ちを受け止めてもらえる経験が大切になります。
「親は味方なんだ」と感じられることが、お子様の心の支えにつながります。
行動・生活面の特徴
【行動・生活面での困りごと】
物や時間の管理が苦手
部屋を片づけられない
身支度に時間がかかってしまう
睡眠リズムが乱れやすく、朝なかなか起きられない
グレーゾーンの子どもたちは、日常生活の中でも「どうしてできないの?」と誤解されやすい行動が見られることがあります。
こうした姿は周囲から『だらしない』『やる気がない』と受け取られがちですが、実際にはお子様自身も困っていることが多いのです。



やろうと思っているのに、気づけば忘れていた



片づけたいのに、どこから手をつければいいのかわからない
そんな葛藤を抱えているお子様も少なくありません。
家庭で工夫することで助けられる部分もありますが、それだけでは限界を感じることもあります。
だからこそ、学校生活の中で先生にどう伝えるか、環境をどう整えてもらうかといった視点も大切です。
親御さんが具体的な様子を伝えることで、先生も理解しやすくなり、お子様が安心して過ごせる環境につながります。
行動や生活習慣の困りごとについては、こちらの記事もご覧ください。
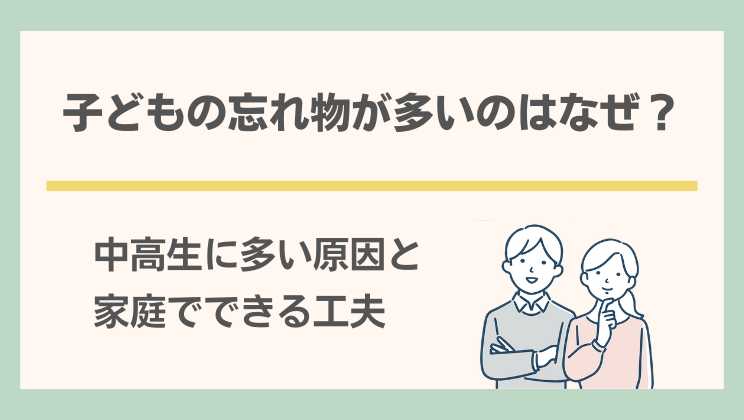
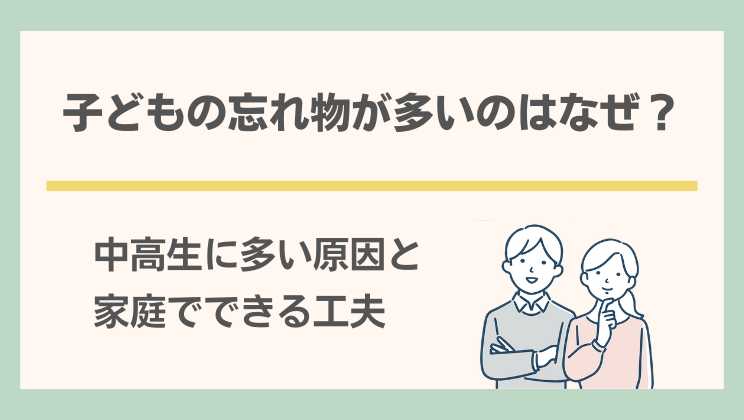
グレーゾーンの特徴がもたらす困りごとと誤解
グレーゾーンの子どもたちは、「診断がついていないから大きな問題ではない」というわけではありません。
勉強のこと、友だち関係、生活のリズムなど、さまざまな場面での特徴が重なり、学校や家庭で困りごとにつながるケースも多く見られます。
しかし、その困りごとはしばしば『本人の努力不足』や『親のしつけの問題』と誤解されてしまいます。


「やればできるはずなのに」「わがままを言っているだけ」と見られてしまうと、お子様は「自分はダメだ」と感じやすくなります。
また、親御さんも



育て方が悪かったのでは…
と自分を責めてしまい、親子ともに苦しくなることがあります。
大切なのは、困りごとはお子様の特性や実行機能の未熟さが背景にある場合が多いという理解です。
誤解を減らし、正しく理解することが、お子様と家庭を守る大きな力になります。
グレーゾーンが見過ごされやすい理由
周囲から見ると困りごとが目立たず、支援が必要でも「特に問題はない」と判断されてしまいがち―これが、グレーゾーンの大きな特徴のひとつです。
たとえば
学力が平均程度に見える→『特に問題はない』と受け止められがち
行動面の困りごとが軽度→『性格の問題』と片づけられてしまう
「成長すれば自然に解決するだろう」と思われやすく、困りごとが続いていても見過ごされる
保護者や先生が「頑張ればできるのでは」と考えてしまい、支援のタイミングを逃す
その結果、お子様が一番つらい時に手を差し伸べてもらえず、孤独感や不安を深めてしまうことがあるのです。
子どもが抱える困りごとと誤解
グレーゾーンの困りごとは、学校や友人関係の中で「努力が足りない」と誤解されてしまうことがあります。
実際には本人の力不足ではなく、ものの受け取り方の特性が影響している場合が多いのです。
けれども周囲からの誤解が重なると



自分はダメなんだ
と自己否定しやすくなり、気持ちの落ち込みやストレスにつながってしまいます。
ここでは、学校生活と友人関係の場面で表れやすい困りごとを見ていきましょう。
学校での困りごと
学校生活では、宿題や提出物、授業への集中、グループ活動など、日常の場面でつまずきが表れることがあります。
たとえば
宿題や提出物を忘れてしまう、集中力が途切れる → 「怠けている」「努力不足」と誤解される
グループ活動での衝突や授業中のちょっとしたミス → 「空気が読めない」「協調性がない」と評価されやすい
学校での評価が内申点や進学に結びつくため、将来への不安やプレッシャーを抱えやすい
「わかっているのにできない」状況で、自己否定感を深めやすい
友人関係での困りごと
友人との関わりでも、小さな行き違いや誤解が重なりやすいことがあります。
たとえば
話の切り出し方や会話のテンポがずれる → 「変わっている」「空気を読まない」と思われやすい
小さなトラブルや誤解の積み重ね → 孤立やいじめのきっかけになることもある
「嫌われている」「自分が悪い」と過剰に受け止めてしまい、強いストレスを抱えやすい
保護者が抱える不安と誤解
「発達障がいなのかどうか分からない」という曖昧さは、親御さんにとって大きなストレスになります。
診断がつかないことで



支援が受けられないのでは?
という不安が強まり、さらに



育て方のせいなのでは…
と自分を責めてしまうこともあります。
こうした不安や誤解が強いほど、お子様に余計なプレッシャーを与えてしまい、親子でつらい状況になってしまいます。
診断に関する不安



診断が出ないと支援につながらないのでは?
という思い込みは、多くの保護者が抱える不安のひとつです。


実際には、診断名がなくても受けられる支援はあります。
けれども「診断書がない=困っている証明がない」と感じてしまうため、不安になるのも当然のことです。
育て方に関する誤解や罪悪感
お子様の困りごとを「しつけ不足」や「親の甘やかし」と誤解されることは少なくありません。
周囲からの「ちゃんと叱らないからじゃない?」「親が甘やかしすぎなんだよ」といった無理解な言葉が重なると、「自分の育て方が悪かったのでは」と感じ、強い罪悪感を抱いてしまうのも自然なことです。


しかし、困りごとの多くは特性によるもので、親御さんのせいではありません。
誤解に振り回されず、安心して向き合えるようになることが大切です。
診断がなくても受けられる支援と、診断がある場合の違い


診断がある = 支援が受けられる


診断がない = 支援が受けられない
こう考えてしまう保護者の方は少なくありません。
確かに、法律や制度上の支援では『障がいのある子』が対象とされる場面があります。
けれども、診断書が必須とは限らず、学校生活の中での日常的な配慮であれば、診断の有無にかかわらず相談できることもあります。
大切なのは診断の有無そのものではなく、目の前のお子様がどんな困りごとを抱えていて、それに応じた支援をどうつなぐかという視点です。
法律や制度上の支援(合理的配慮)
制度上の支援のひとつに『合理的配慮』があります。
【合理的配慮】
障害者差別解消法や文部科学省の通知では『障害のある人』が対象
(内閣府「合理的配慮を知っていますか?」)
たとえば、定期テストで時間延長をお願いする場合は診断書が求められることがありますが、日常の授業では『席を前にする』『口頭だけでなく黒板にも書いてもらう』といった工夫は診断の有無にかかわらず可能です。
このように、診断書がなくてもできる支援はたくさんあります。
診断書は『絶対条件』ではありませんが、制度上の支援を得やすくする“後押し”になるケースがあるのです。
日常生活での支援(診断がなくても可能なこと)
一方で、学校生活の中では診断がなくても受けられる配慮があります。
先生の負担が少ない範囲であれば、サポートしてもらえることも多いです。
たとえば
座席を前にしてもらう
口頭指示だけでなく黒板にも書いてもらう
宿題の量を調整してもらう
こうした小さな工夫は、診断の有無にかかわらず学校に相談できます。
また、発達相談窓口や教育相談機関などの公的機関も、診断がなくても利用可能です。
「診断がないから支援が受けられない」と思い込まずに、まずは身近なところへ相談してみることが大切です。
グレーゾーンの中高生を支える|家庭でできる3つのサポート方法
家庭での関わり方は、お子様が安心して挑戦できる土台になります。
グレーゾーンの子どもたちは、誤解されたり注意される場面が多く、「自分はダメだ」と感じやすい傾向があります。 だからこそ、『できないこと』を叱るのではなく、『どうすればできるようになるか』を一緒に工夫する視点がとても大切です。
こうした関わりの積み重ねが、「自分にもできることがある」という気持ちを育て、自己肯定感につながっていきます。
自己肯定感が育つことで、困りごとに対しても少しずつ自分なりの対処法を見つけられるようになります。
自己肯定感について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
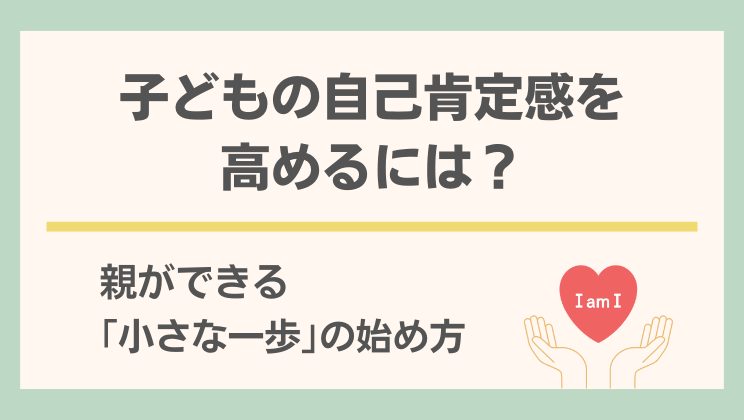
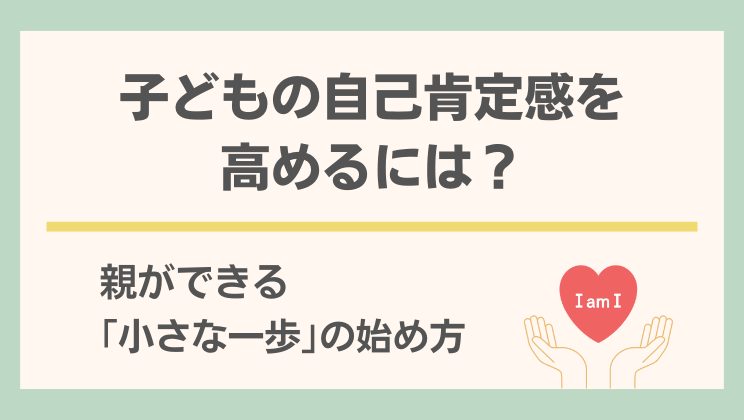
学校や医療機関に頼るだけでなく、家庭でできる工夫もたくさんあります。
家庭でのサポートはお子様の特性を理解する第一歩となり、学校との連携もしやすくなるでしょう。
ここでは、家庭で取り入れやすい3つのサポート方法をご紹介します。
ただし、すべてを完璧にする必要はありません。
できることから少しずつ、取り入れてみてくださいね。
① 環境を整えるサポート
忘れ物や予定の管理は、『仕組み』でカバーすることができます。
カレンダーや付箋で予定を“見える化”する
持ち物リストを玄関に貼る
勉強や宿題は短時間で区切って集中しやすくする
睡眠・食事・休息といった生活リズムを安定させる



環境を工夫することで『努力しなければできない』ではなく『自然にできる』状況をつくることができます。
忘れ物について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。
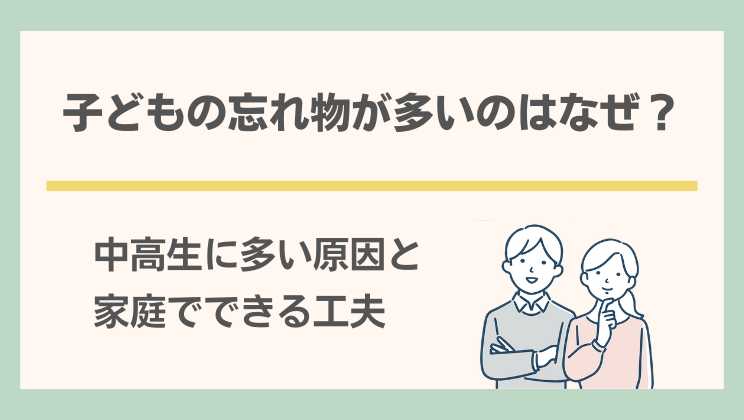
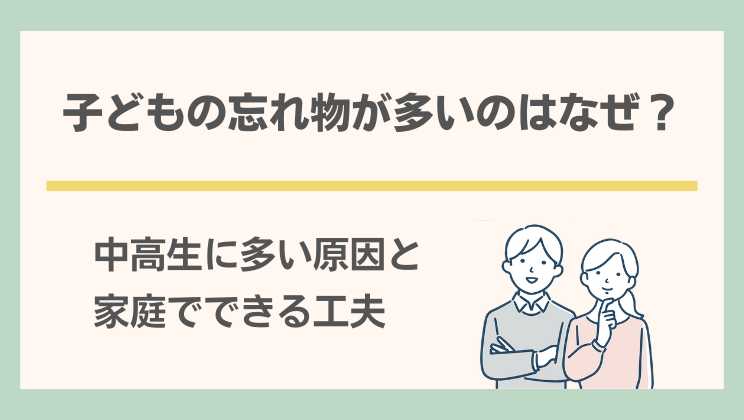
② コミュニケーションでのサポート
言葉のかけ方ひとつで、お子様の受け止め方は大きく変わります。
「どうしてできないの?」ではなく、「どうしたらやりやすい?」と聞く
お子様の困り感に共感し、『親は味方』と感じてもらう
成功したときは小さなことでも認めて、自信につなげる



親が味方であると感じられることで、お子様は安心して挑戦できるようになります。
③ 学校や周囲とつなぐサポート
家庭だけで困りごとを抱え込まず、学校や周囲に伝えることも大切です。
「忘れ物が多いです」ではなく、「黒板に書いてもらえると助かります」と伝え方を工夫する
必要に応じてスクールカウンセラーや発達相談窓口に相談する
家庭での様子を先生に共有することで、理解や配慮につながりやすくなる



学校や地域とつながることは、親御さんにとっても「自分だけで何とかしなくていい」という安心感につながります。
グレーゾーンの中高生に関するよくある疑問Q&A
- グレーゾーンは正式な診断名ですか?
-
いいえ、正式な診断名ではありません。
発達障がいの診断基準に一部は当てはまるけれど、すべてを満たしていない状態を『グレーゾーン』と呼んでいます。
白(診断がつかない)でも黒(診断がある)でもない、その中間にある状態を分かりやすく表す言葉です。 - 診断がなくても学校で支援は受けられますか?
-
はい、受けられる場合があります。
制度上の大きな配慮(入試での時間延長など)は診断書を求められることもありますが、日常生活のちょっとした工夫は診断がなくても相談できます。たとえば、座席を前にしてもらう、指示を板書と口頭の両方で伝えてもらう、宿題の量を調整してもらう、といった配慮です。
詳しくはこちらをご覧ください。
診断がなくても受けられる支援と、診断がある場合の違い - 将来、発達障がいと診断されることもありますか?
-
あります。
中高生の時点では診断に至らなかったお子様が、大人になってから診断されるケースも珍しくありません。
発達は一人ひとり違うペースで進むため、年齢や環境の変化によって困りごとが目立つようになり、診断に結びつくことがあります。 - 学校の先生に子どもの特性を伝えるとき、どう説明すればいいですか?
-
『できないこと』だけでなく、『どうすればやりやすいか』を具体的に伝えるのがおすすめです。
たとえば「忘れ物が多いです」ではなく「黒板に宿題を書いてもらえると助かります」とお願いすると、先生も対応しやすくなります。 - グレーゾーンの子どもは不登校になりやすいですか?
-
必ずしもそうではありませんが、誤解や孤立が続くと学校に行きづらくなることがあります。
大切なのは「学校が安心できる場所」になるように、家庭や先生が支えていくことです。 - 進路選びで気をつけることはありますか?
-
『みんなと同じだから安心』ではなく、お子様が安心して学べる環境を重視することです。
通信制高校のように、少人数で自分のペースを大切にできる環境も選択肢の一つです。
高校選びや進学の場面では、オープンキャンパスや説明会で具体的に確認しておくと安心です。高校の選び方については、こちらも参考にしてください。
【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
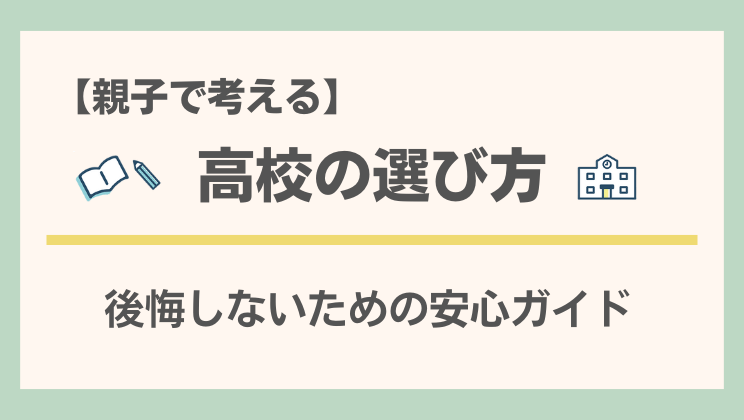 【親子で考える】高校の選び方|後悔しないための安心ガイド | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で… 高校選びで迷う親御さんとお子様へ。普通科・専門学科・通信制などの違いや、学費・通学・進路・サポート体制まで、親子で確認したいポイントをやさしく解説。後悔しない選…
【親子で考える】高校の選び方|後悔しないための安心ガイド | 【公式】ID学園高等学校_生徒の個性を日本で… 高校選びで迷う親御さんとお子様へ。普通科・専門学科・通信制などの違いや、学費・通学・進路・サポート体制まで、親子で確認したいポイントをやさしく解説。後悔しない選… - 家庭でできるサポートにはどんなものがありますか?
-
予定や持ち物をカレンダーや付箋で見える化したり、玄関にリストを貼ったりすると、忘れ物や予定の抜けを減らすことができます。
また、「どうしてできないの?」ではなく「どうしたらやりやすい?」と声をかけることで、お子様は安心しやすくなります。
さらに、短時間でも勉強に取り組めた、忘れ物が一つ減ったといった小さな成功を一緒に喜ぶことが、自信につながります。詳しくはこちらをご覧ください。
グレーゾーンの中高生を支える|家庭でできる3つのサポート方法 - グレーゾーンは大人になったらどうなりますか?
-
特性は大人になっても続きますが、工夫や環境調整によって過ごしやすくなる方は多いです。
一方で、大人になってから働き方や人間関係で困りごとが目立ち、改めて診断につながるケースもあります。
まとめ|グレーゾーンの理解と支援の第一歩
『グレーゾーン』は正式な診断名ではなく、発達の特性があるものの診断基準を満たさない状態を指す言葉です。
学校生活や家庭の中では、そうした特徴が困りごとにつながりやすく、周囲からの誤解や保護者の不安を生みやすい面があります。
大切なのは診断の有無にとらわれることではなく、『今、お子様が困っている』という事実に目を向けることです。
家庭でできる小さな工夫は、お子様の自己肯定感を支える力になりますし、学校との連携もしやすくなります。
そして何より、親御さんだけで抱え込まず、学校や医療機関、相談窓口とつながることが、お子様の未来をひらく第一歩になります。
【ID学園】グレーゾーンの子も安心できる『選べる特別活動』
グレーゾーンは診断基準に当てはまらないだけでなく、“人と合わせること”に不安を抱える子も少なくありません。
集団活動で理解されないと感じると、学校がしんどい場所になってしまうこともあります。
ID学園では『特別活動』として、森林ボランティア・博物館見学・外部講師による特別授業など、多様なプログラムから自分に合った活動を選ぶことができます。
たとえば『自分のペースで動けるボランティアに参加して、心地よく過ごせた』という体験は、集団への安心感を育てるきっかけになります。
こうした体験こそ、グレーゾーンのお子様が『学校も自分の居場所になる』と感じられるための、前向きな第一歩になります。
ID学園についてもっと知りたい方は、ぜひ説明会や個別相談会に足を運んでみてください。