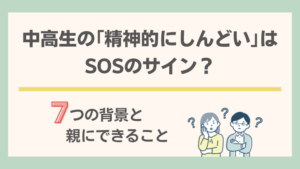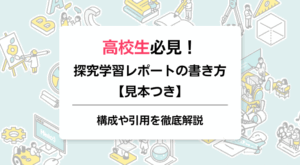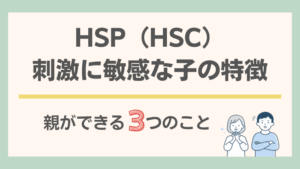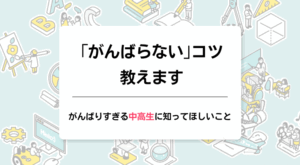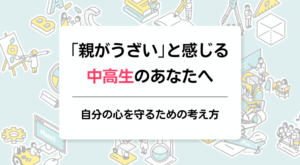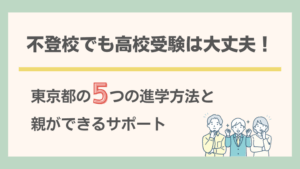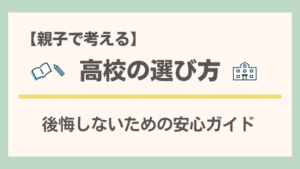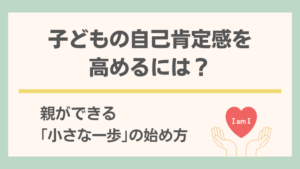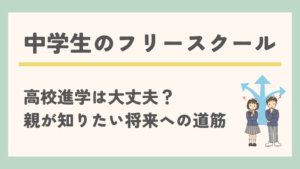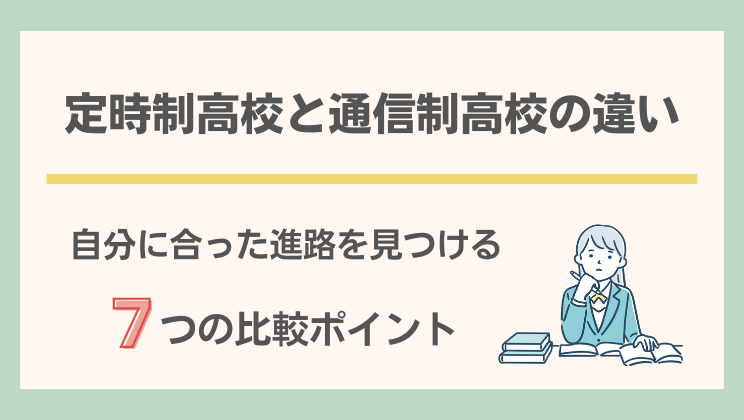
「定時制高校と通信制高校、どう違うんだろう?」
「なんとなく似ているような気がするけど、うちの子にはどちらが合っているのかな…」
そんなふうに感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
どちらも“自分のペースで学べる柔軟な高校”として注目されていますが、通学スタイルや授業の仕組み、サポート体制にはそれぞれ特徴があります。
近年は、昼間に通える定時制(昼間定時制)や、通学型の通信制高校も増え、違いが分かりづらくなっているのが現状です。
本記事では、「通学ペース」「授業スタイル」「学費」「サポート体制」など7つの比較ポイントから、定時制と通信制の違いをわかりやすく整理します。
大切なのは、「どちらが良い・悪い」ではなく、お子様の生活スタイルや性格に合う学び方を選ぶこと。
お子様が無理なく、安心して学べる環境を見つけるヒントを紹介します。
【この記事でわかること】
定時制高校と通信制高校、それぞれの仕組みと基本的な違い
定時制の新しい形(昼間定時制・単位制定時制)と今の実態
通学ペース・授業スタイル・学費など、7つの比較ポイント
お子様の性格や生活スタイルから見る「向いているタイプ」
後悔しない高校選びのために保護者が確認しておきたいポイント
「夜の学校」だけじゃない、今の定時制高校
定時制高校=夜に通う学校
働きながら学ぶ生徒が通う場所
そんなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
しかし、現在の定時制高校はその姿を大きく変えています。
文部科学省「学校基本調査」によると、定時制高校の総数はこの10年間で減少傾向にありますが、その中でも昼間定時制の設置校は増加しています。
| 年度 | 定時制高校総数 | 昼間定時制 | 夜間定時制 |
| 平成26年度 | 663校 | 59校 | 486校 |
| 令和6年度 | 613校 | 66校 | 427校 |
令和6年度には定時制全体で613校、そのうち昼間定時制が66校、夜間定時制が427校となっており、平成26年度(昼59校、夜486校)と比べると、夜間型から昼間型への移行が進んでいることがわかります。
こうした変化の背景には、「働きながら夜に通う」生徒が減少した一方で、「昼間に無理なく通いたい」「全日制は合わなかったけれど、毎日通いたい」といった生徒のニーズが増えたことがあります。

つまり今の定時制高校は、「もう一度学校に通いたい」「生活リズムを整えながら学びたい」という生徒が、自分のペースで通える柔軟な学びの場へと変化しているのです。
定時制高校の仕組みと特徴を知ろう
定時制高校と通信制高校の違いを理解するには、まず「定時制とは何か」を正確に知っておくことが大切です。
ここでは、制度としての定時制の基本的な仕組みと、現代的な定時制高校(昼間・単位制など)の特徴を整理していきます。
定時制高校とは?基本の仕組みを簡単に整理
定時制高校は、学校教育法で「夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程」と定められています。
(文部科学省「高等学校制度の概要 」)
全日制に比べて授業時間が短く、生徒の生活スタイルに合わせて柔軟に学べるのが特徴です。
授業は「昼」「夕方」「夜間」などの時間帯に設定され、1日の授業時間は3〜4時間程度の学校が多く見られます。
在籍期間は原則4年間ですが、単位制定時制を導入している学校では、3年間で卒業を目指すことも可能です。
学年制と単位制定時制の違い
定時制高校には、従来の「学年制」だけでなく、単位制定時制を導入している学校もあります。

単位制定時制では、学年ごとの区切りがなく、自分のペースで必要な科目を履修し、一定の単位を修得すれば卒業できる仕組みです。
そのため、3年で卒業する生徒もいれば、じっくり4年以上かけて学ぶ生徒もいます。
通信制高校と同じように、在籍期間や履修順序を自分で調整できるため、「生活リズムを整えながら通いたい」「体調や家庭の事情に合わせて学びたい」といったニーズに応えやすい制度です。
全日制・定時制・通信制の比較表
定時制高校の特徴をより理解するために、全日制・通信制と比較して見てみましょう。
どの課程も「高校卒業資格」は同じですが、通い方や学び方には大きな違いがあります。
| 比較項目 | 全日制高校 | 定時制高校 | 通信制高校 |
| 通学スタイル | 平日昼間に毎日登校 | 昼・夕方・夜など柔軟に通学 | 在宅・通学どちらも可(週1〜5日) |
| 授業時間 | 1日6時限前後 | 1日3〜4時限 | 通学型:1日3〜5時限程度在宅型:自宅学習+スクーリング |
| 在籍期間 | 3年 | 原則4年(単位制定時制なら3年も可) | 3年以上で卒業可 |
| 学び方の特徴 | 学校生活中心 | 少人数で柔軟に学べる | 通学頻度や学び方を自由に選べる |
このように、定時制高校は全日制と通信制の“中間的な立ち位置”にあります。

通学の習慣を保ちながらも、時間帯やペースを柔軟に調整できるのが大きな特徴です。
定時制⇄通信制の転入・編入はできる?


定時制高校から通信制高校へ、またはその逆も、「転入」や「編入」という形で移ることが可能です。
両課程を併設している高校では、同一校内での転籍ができる場合もあります。
単位制を導入している学校では、修得済みの単位を引き継げることが多く、転入や編入後もスムーズに学びを続けられるケースが増えています。
定時制 → 通信制:通学負担を減らし、仕事や体調との両立を図りたい生徒
通信制 → 定時制:毎日の登校を通じて生活リズムを整えたい生徒
制度上の制約は少ないものの、転入時期・受け入れ枠・単位認定方法は学校ごとに異なります。
単位認定や学校長の判断に委ねられている部分もあるなど、早めに学校へ相談しておくと安心です。
転入や編入の基本的な仕組みを詳しく知りたい方は、こちらで整理しておきましょう。
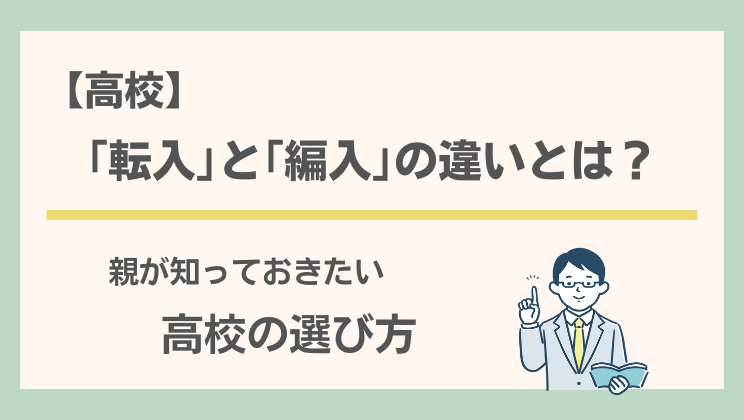
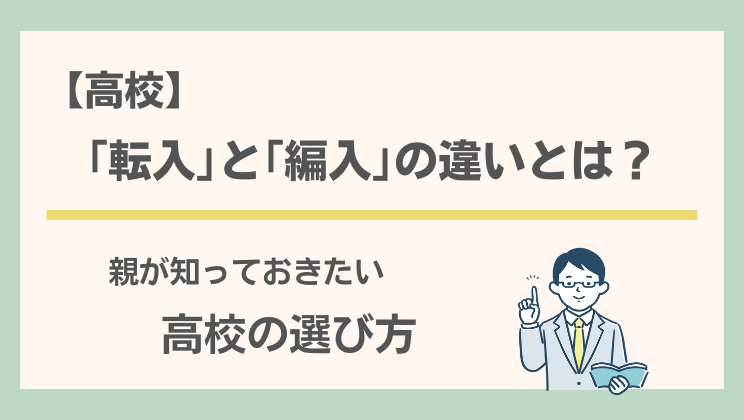
また、通信制高校への具体的な編入手続きや流れを知りたい方は、こちらも参考になります。
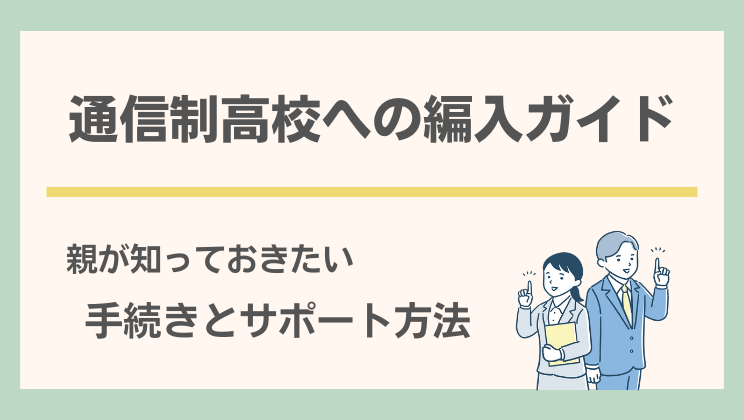
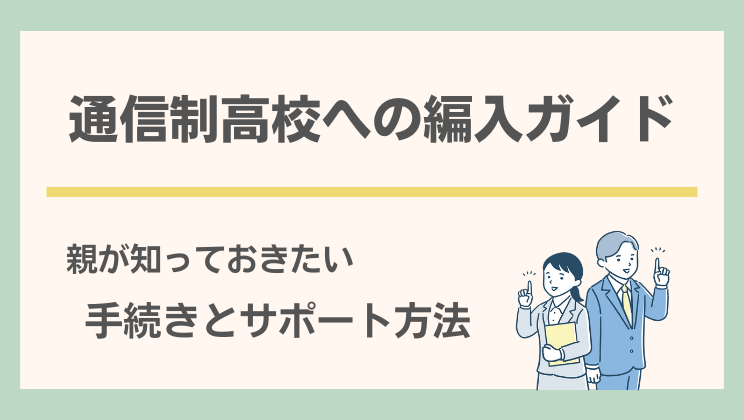
定時制高校の特徴|少人数・柔軟・学び直しの場
定時制高校の魅力は、少人数で手厚いサポートが受けられることです。
1クラスの人数は20人以下の学校が多く、先生との距離が近い環境です。
学習スタイルは学校によって異なりますが、次のような柔軟性があります。
通学時間帯を選べる
→昼・夕方・夜など、生活リズムに合わせた通学が可能
単位制の導入が進んでいる
→自分のペースで単位を積み上げられる
幅広い年齢層の生徒が在籍
→中退後の再入学や社会人の学び直しなど
こうした柔軟な仕組みにより、働きながら通う生徒や、体調を考慮して登校時間を調整したい生徒も、無理なく学べる環境が整っています。
また、登校日には授業だけでなく、面談・ゼミ・行事などを通して人とのつながりを取り戻す場にもなっています。
昼間定時制・単位制定時制が増えている背景
夜間に通う定時制高校は年々減ってきていますが、一方で、昼間に通える「昼間定時制」や、在籍期間を自由に設定できる「単位制定時制」は増えています。
その背景には、次のような社会の変化があります。
① 少子化にともなう学校の再編や統合の進行
② 不登校や中退を経験した生徒に対応できる、柔軟な学びの場の必要性
③ 働きながら通う生徒の減少と、「昼に学びたい」層の広がり
文部科学省や各都道府県の教育委員会でも、「学び方の多様化」を積極的に進めています。
登校時間や在籍年数を自分で選べる学校が増え、より多くの生徒が無理なく通えるようになりました。



通うことはできるけれど、全日制は難しい
そんな生徒たちにとって、定時制高校は“もう一度学びたい”という思いを支える大切な場所になっています。
【徹底比較】定時制高校 vs 通信制高校|7つの違い
定時制高校と通信制高校は、どちらも“柔軟に学べる高校”です。
全日制のように毎日朝から夕方まで通う必要がなく、「自分のペースで学びたい」「学校を変えて再スタートしたい」と考える生徒に選ばれています。
ただし、通い方・授業スタイル・サポート体制などの仕組みは大きく異なります。
その違いを知っておくことで、「どちらなら無理なく続けられるか」「どんな学び方が合っているか」を判断するヒントになります
高校生活の過ごし方はもちろん、進学や将来の選択にも関わる大切なポイントです。
ここでは、生活リズム・授業スタイル・学費・サポート体制など、7つの視点から定時制と通信制の違いを整理してみましょう。
| 比較項目 | 定時制高校 | 通信制高校 |
| ① 通学ペース | 週4〜5日・毎日登校 | 週1〜5日・在宅+通学どちらも可 |
| ② 学習スタイル | 対面授業中心 | レポート+オンライン+通学授業(選択制) |
| ③ 時間割 | 固定制(学校が設定) | 自己設計型(生徒が選択) |
| ④ 人間関係 | クラス制で友人ができやすい | 個別・少人数中心。通学型では交流機会も多い |
| ⑤ 自己管理 | 学校がペースを支援 | 自己管理+担任のサポートあり |
| ⑥ 学費 | 公立中心で安い | 公立は安価・私立は通学頻度で変動 |
| ⑦ 進路サポート | 対面型・教員支援中心 | オンライン+個別面談中心(通学型は対面サポートも) |



定時制高校は、毎日通学しながら生活リズムを整えたい生徒に向いています。
一方で通信制高校は、「在宅型」か「通学型」かを選べる柔軟さがあり、体調や生活スタイルに合わせて学び方を調整できるのが特徴です。
通信制高校の「柔軟さ」や「学び方の自由度」については、こちらの記事でもデータをもとに詳しく解説しています。
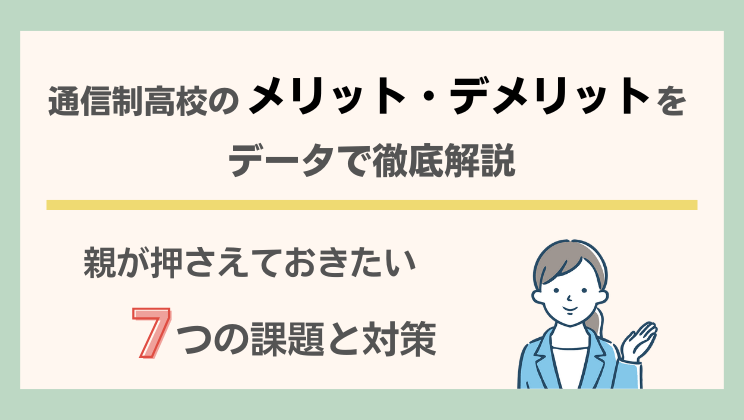
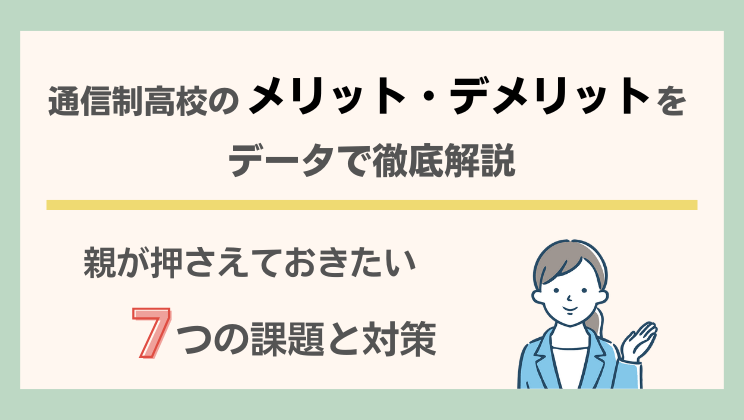
① 通学ペースと生活リズムの違い
- 定時制
-
毎日決まった時間に登校するため、生活リズムを整えやすく、登校の習慣も身につきます。
授業時間帯は昼・夕方・夜などから選べるため、生活スタイルに合わせて無理なく通えます。 - 通信制
-
登校回数を自由に設定でき、在宅学習を中心に学ぶのが基本です。
在宅型では自宅での学習と年数回〜月数回のスクーリングを組み合わせ、通学型では週1〜5日の登校で生活リズムを保ちながら学ぶことができます。
② 学習スタイルと授業形式の違い
- 定時制
-
先生が教室で教える対面授業が中心です。
その場で質問したり、友人と話し合ったりすることで、理解を深めやすい環境が整っています。 - 通信制
-
レポート提出やオンライン授業が中心で、自宅や登校日を活用して自分のペースで学べます。
在宅型は映像授業やeラーニングで学ぶスタイル、通学型では教室での少人数授業やゼミ形式の学びを取り入れる学校もあります。
③ 時間割と自由度の違い
- 定時制
-
学校が時間割を設定しており、登校時間や授業内容があらかじめ決まっています。
計画的に進めたい生徒にはわかりやすい仕組みです。 - 通信制
-
単位制を採用しており、科目や履修順序を自分で選択できます。
得意や関心のある教科を中心に進めるなど、自由度の高い学び方が可能です。
④ 人間関係と友人づくりの違い
- 定時制
-
毎日登校することで自然と顔なじみができ、少人数の中で深いつながりが生まれやすい環境です。
年齢や背景の異なる生徒同士が共に学ぶことで、多様な価値観に触れられるのも特徴です。 - 通信制
-
在宅型では交流の機会が少なく、孤立を感じやすい一面があります。
一方で通学型では、クラス授業や探究活動、学校行事などを通して友人関係を築くことができます。
また、オンラインコミュニティやチャットを活用したつながりの場を設けている学校も増えています。
⑤ 求められる自己管理能力の違い
- 定時制
-
出席や課題提出は学校が一括して管理してくれるため、先生のサポートを受けながら学習を進められます。
自己管理が苦手な生徒でも続けやすい環境が整っています。 - 通信制
-
レポートやスクーリングの進度を自分で計画・管理する必要があります。
ただし、通学型では登校ごとに先生が学習状況を確認してくれるため、在宅型よりもペースを維持しやすい傾向があります。
⑥ 学費と支援制度の違い
- 定時制
-
公立が中心で、年間3〜5万円程度+教科書代と比較的安価です。
「高等学校等就学支援金制度」などの公的支援が利用でき、経済的な負担が少ないのが特徴です。 - 通信制
-
公立で年間2〜4万円、私立では30〜80万円前後が目安です。
在宅型は授業料が比較的低く抑えられますが、通学型では施設費や交通費がかかります。
いずれも就学支援金制度の対象で、所得に応じて授業料の一部または全額が補助されます。
高等学校就学支援金についてはこちらをご覧ください。
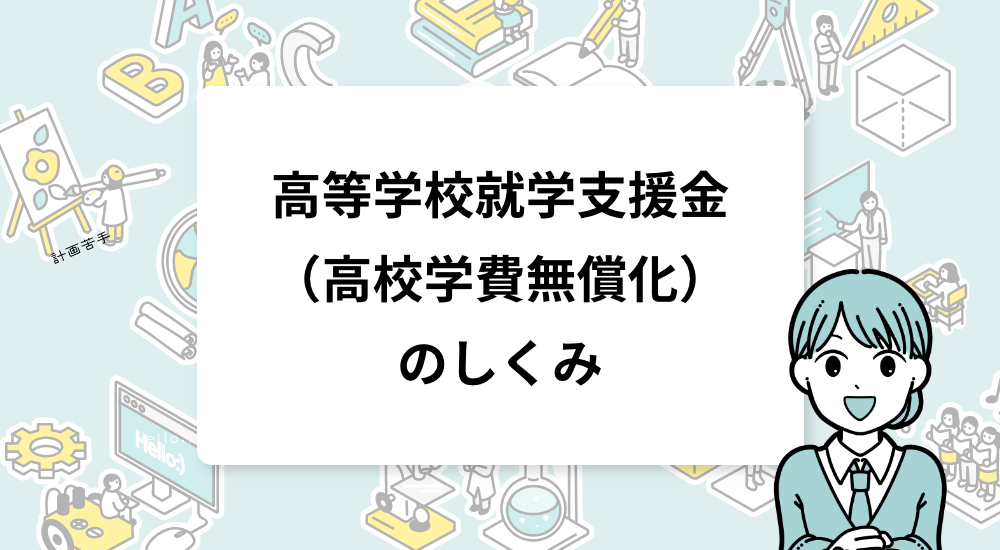
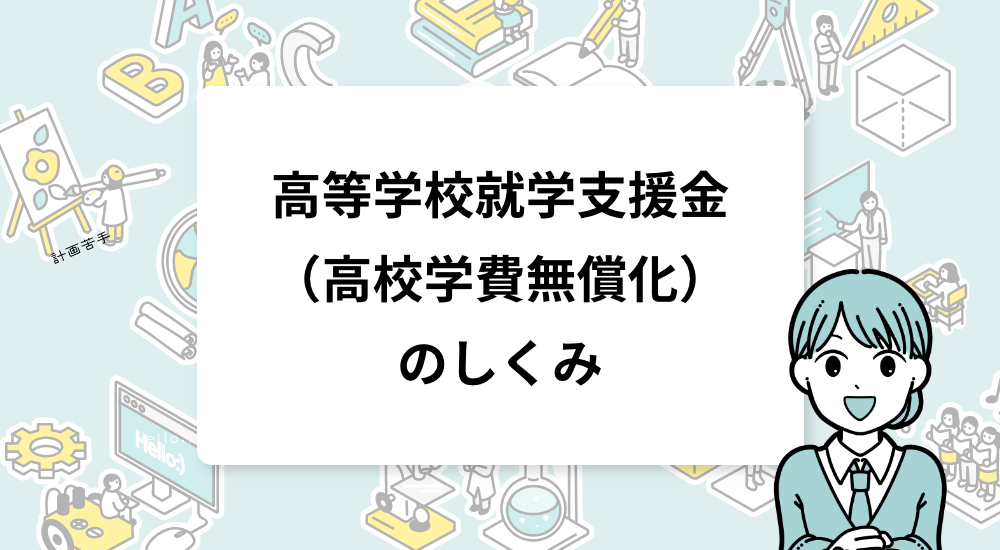
⑦ サポート体制と進路指導の違い
- 定時制
-
教員と対面で相談しやすく、少人数の中で一人ひとりに目が届きやすい環境です。
生活面や学習面の支援を通じて、生徒の成長を支えています。 - 通信制
-
在宅型ではオンライン面談やチャット相談を中心に、通学型では対面カウンセリングや個別面談が充実しています。
また、担任制やキャリアカウンセラーによる進路支援など、サポートの多様化が進んでいます。
どんな子に向いている?タイプ別で見る「定時制」「通信制」
定時制と通信制にはそれぞれの良さがあり、どちらが合うかはお子様の性格や生活リズムによって変わります。
ここでは、前の章での比較をもとに「どんな子に向いているか」を具体的に整理しました。
お子様の様子を思い浮かべながら、安心して続けられる学び方を考えるヒントにしてみてください。
定時制高校が向いているタイプ
毎日学校に通うことで、生活リズムを整えたい
一人で勉強するより、クラスのみんなと一緒に授業を受けたい
計画を立てるのは苦手なので、学校のペースに合わせて学びたい
学校行事や部活動などを通して、人との関わりを大切にしたい
少人数の環境で、先生とじっくり関わりながら学びたい
通信制高校が向いているタイプ
自分のペースで、得意なことや好きなことを深く学びたい
集団生活や大人数の授業が少し苦手で、落ち着いた環境で学びたい
仕事や芸能活動、療養など、学業以外に打ち込みたいことがある
通学日数や時間を自由に選びながら、生活と学習を両立したい
「自分で選んで決める」経験を通して、自立心や計画性を育てたい
通信制高校について、もう少し詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
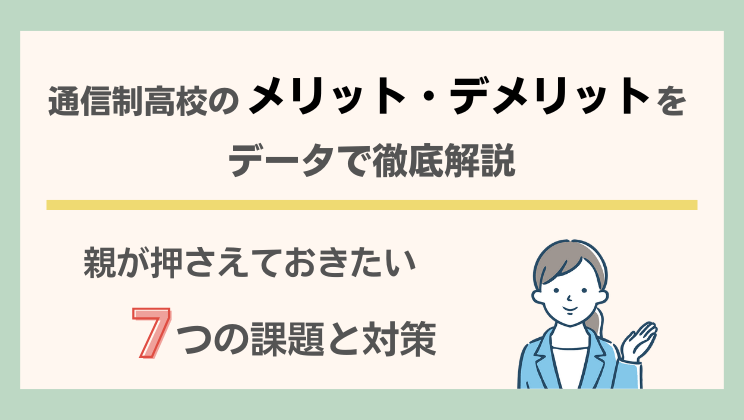
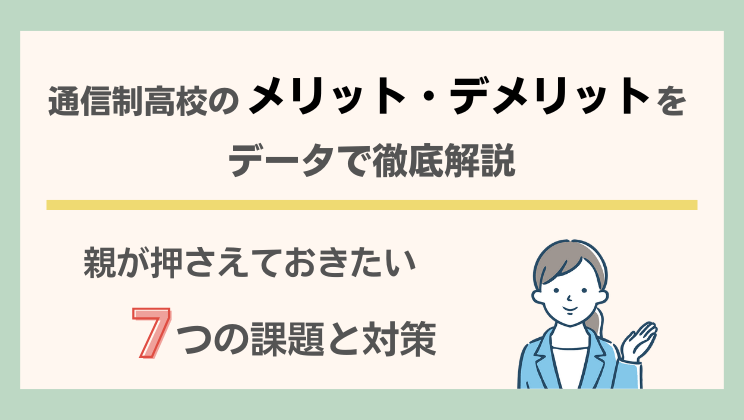
入学を考える前に確認しておきたい3つのポイント


定時制・通信制ともに、最も大切なのは「無理なく通い続けられるか」です。
制度や学費の違いも大事ですが、それ以上に「日常生活に合っているか」「安心して学べるか」を基準に選ぶことが、お子様の継続と成長につながります。
学校見学や説明会で、次の3つのポイントについて確認したかを振り返ってみましょう。
① 通学時間と通学方法
昼間定時制・夜間定時制・通信制通学コースなど、登校時間帯を比較した
通学手段や通学時間を確認し、「無理なく通える距離」かどうかを検討した
体調や家庭の事情に合わせて、通学回数を調整できる学校かを確認した
② サポート体制(担任・相談員の有無)
学習面だけでなく、メンタル面での相談先(担任・カウンセラー等)を確認した
オンライン・対面どちらのサポートが充実しているかを把握した
学校と家庭の連携(連絡の取りやすさ・報告の頻度)を確認した
③ 進路実績と支援内容
進学・就職など、卒業後の進路実績を確認した
どんなサポート(面談・ガイダンス・キャリア教育など)があるかを質問した
合格者数などの数字だけでなく、支援の中身や生徒の声もチェックした
Q&A|定時制高校に関するよくある質問
- 定時制高校は卒業までどれくらいかかりますか?
-
原則は4年間での卒業が基本です。
ただし、単位制を採用している学校では、修得した単位数によって3年での卒業も可能です。
一方で、体調や家庭の事情により在籍期間を延長することもできるため、自分のペースで学べる仕組みになっています。詳しくはこちらをご覧ください。
定時制高校の仕組みと特徴を知ろう - 夜間以外に通える定時制はありますか?
-
あります。
近年は夜間型だけでなく、昼間定時制や単位制定時制が全国的に増えています。
午前や午後に授業を受けられる学校も多く、「夜に通うのは難しい」という生徒でも安心して通えます。詳しくはこちらをご覧ください。
「夜の学校」だけじゃない、今の定時制高校 - 中学校の成績や内申点が低くても入れますか?
-
はい、入学できます。
定時制高校では、学力テストと面接を組み合わせた入試が一般的です。
ただし、学校によって実施内容は異なり、学力テストがない場合や作文を課す学校もあります。学力テストを行う場合でも、国語・数学・英語が中心で、全日制よりも難易度は高くありません。
多くの学校では、「これからどう学びたいか」という意欲や人柄を重視して選考を行っています。 - 定時制高校でも大学進学はできますか?
-
可能です。
定時制高校を卒業すれば、全日制や通信制と同じ高校卒業資格を得られます。
多くの学校で、授業時間外に補習や進学講座が設けられており、大学や短大への進学実績もあります。また、大学入試の仕組み(総合型選抜・学校推薦型・一般選抜など)は通信制高校と共通です。
入試制度の詳しい内容を知りたい方は、こちらの記事も参考になります。【公式】ID学園高等学校_生徒の個…
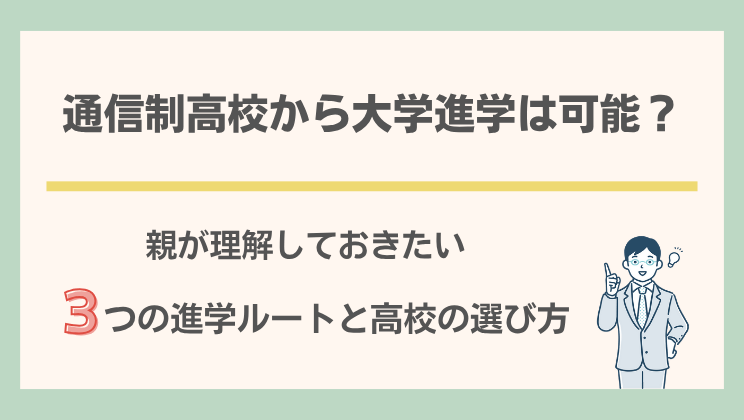 通信制高校から大学進学は可能?|親が理解しておきたい3つの進学ルートと高校の選び方 | 【公式】ID学園… 通信制高校からでも大学進学は十分に可能です。入試制度の仕組みや3つの進学ルート、学校・コース選びのポイントをわかりやすく解説。受験対策やサポート体制、先輩の実例…
通信制高校から大学進学は可能?|親が理解しておきたい3つの進学ルートと高校の選び方 | 【公式】ID学園… 通信制高校からでも大学進学は十分に可能です。入試制度の仕組みや3つの進学ルート、学校・コース選びのポイントをわかりやすく解説。受験対策やサポート体制、先輩の実例… - 定時制高校は不登校だった子にも合いますか?
-
合うケースが多いです。
少人数で先生との距離が近く、登校時間帯も選べるため、自分のペースで学校生活に慣れていけるのが定時制の良さです。
不登校経験のある生徒を受け入れる体制を整えている学校も多く、段階的に通学を増やすこともできます。安心して通い続けられるサポートがあるかどうか、学校説明会などで確認しておくと安心です。
- 学費の支援制度はありますか?
-
はい、あります。
定時制高校でも、「高等学校等就学支援金制度」をはじめとした国の学費補助制度が利用できます。
また、自治体独自の奨学金や、学校独自の授業料減免制度を設けている場合もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
⑥ 学費と支援制度の違い
まとめ|定時制と通信制、どちらも“自分らしく学べる選択肢”
定時制高校は、「毎日学校に通って学びたい」「生活リズムを整えたい」生徒に向いています。
一方で通信制高校は、「自分のペースで学びたい」「やりたいことと両立したい」という生徒にぴったりです。
どちらも、「学び直しの場」であると同時に、自分に合った学び方を選べる場所として注目されています。
かつては“通信制=再出発”、“定時制=リカバリー”といったイメージがありましたが、今ではその境界がゆるやかになり、
働きながら、通院しながら、スポーツや芸能活動に打ち込みながら学ぶなど、多様な目的に合わせて選べる時代になっています。
親御さんが大切にしたいのは、「どちらが良いか」ではなく、「どんな環境ならお子様が安心して学び続けられるか」という視点です。
お子様の性格や生活リズムに合った選択が、結果的に高校生活をより豊かなものにしてくれます。
【ID学園】自由×サポートで、“未来を描く力”を育てる
定時制のように「通いながら学びたい」生徒もいれば、通信制の仕組みを活かして「自分のペースで学びたい」生徒もいます。
ID学園は、通信制の柔軟さを活かしながら、キャリア教育と手厚いサポートを両立し、生徒が安心して学べる環境を整えています。
ID学園が大切にしているのは、単に「卒業すること」ではなく、自分の興味や得意を出発点に、“なりたい自分”から逆算して行動できる力=「未来を描く力」を育てることです。
そのためのカリキュラムが「夢活(ゆめかつ)」です。
夢活では
【STEP1】 自分らしさを見つける
【STEP2】 興味や関心から“夢”の種を見つける
【STEP3】 企業・地域との探究活動で“夢”を育てる
【STEP4】 自分の物語(マイストーリー)として未来にまとめる
というステップを通して、「夢を見つけ、一歩ずつ実現に向けて進む力」を育てていきます。


もしお子様にも、「自分らしい未来を描いていく高校生活」を体験させたいと感じたら、ぜひ一度、ID学園の学校説明会や個別相談に参加してみてください。
学校の雰囲気や先生との距離感、サポート体制を直接知ることで、「ここなら安心して通えそう」と感じられるヒントがきっと見つかります。