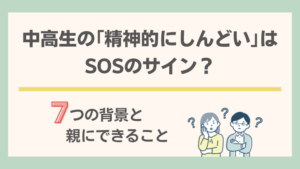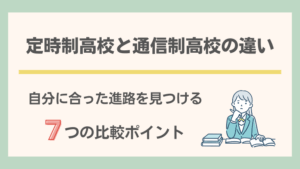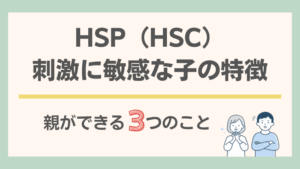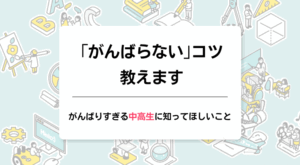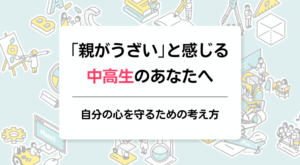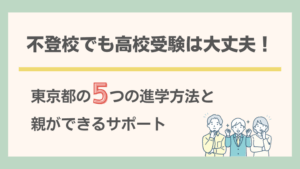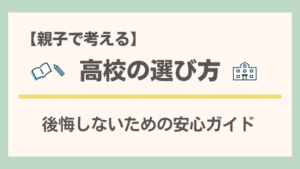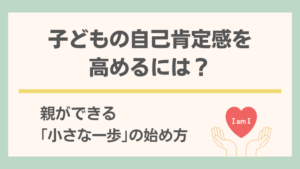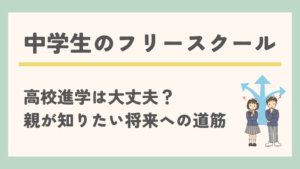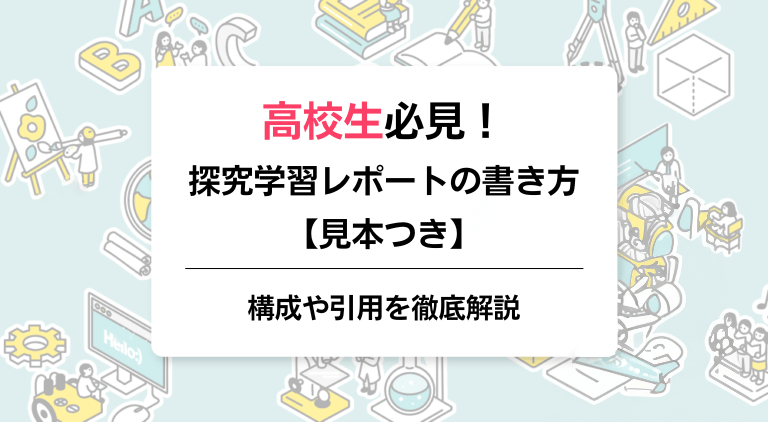
「探究学習のレポート、何からどう書けばいいんだろう…」
「調べたものをまとめて、最後にわかったことや感想を書けばいいの?」
「“レポートの流れ”を意識しろって言うけど、どういうこと?」
レポートの課題が出たとき、何から手をつければいいかわからないと、考えるだけで疲れてしまい、やる気もなくなってしまいますよね。
でも大丈夫。
この記事では、「何を書けばいいか分からない」をゼロにするために、序論・本論・結論それぞれの書き方をお手本つきで丁寧に解説しています。
あなたは、こちらの問いかけに答えていくだけ。
気づけば、自然とレポートが形になっていきます。
それでは、一緒にレポートを完成させていきましょう!
【この記事でできるようになること】
探究レポートの「型」に沿って書けるようになる(序論・本論・結論)
手本に沿って、スラスラ書き進められるようになる
正しい引用の仕方がわかり、著作権も意識できるようになる
テンプレートを使って、構成に悩まず書き出せるようになる
もう悩まない!「どう書けばいい?」は“真似”で解決
「レポートを書くのが苦手!」という人は多いですよね。
実際、いざ書こうとすると手が止まってしまう。
その一番の理由は、「どうやって完成させればいいのか」という具体的な手順がわからないことです。
「調べてまとめる」は何となくわかっても、どんな表現を使えばいいのか、何をどこまで書けばいいのか…。
書く前にイメージが湧かないからこそ、難しく感じてしまうんです。
そこでこの記事では、あなたが最後まで迷わず、楽しく学べるように、二人のナビゲーターを用意しました。
【登場人物の紹介】
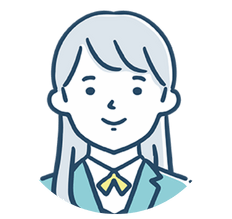
アカリ先輩(高校2年生)
昨年、探究学習を経験し、レポート作成のコツをつかんでいる高校2年生
難しい専門用語を、わかりやすく翻訳してくれる優しい先輩
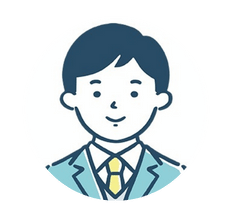
ユウキくん(高校1年生)
探究学習のレポート課題に頭を悩ませる、ごく普通の高校1年生
「何からやればいい?」「それってどういう意味?」という疑問を代弁してくれる
少しやる気がないように見えつつも、ちゃんとやり遂げたい気持ちはある
この記事では、ユウキくんがアカリ先輩に教わりながら、少しずつレポートの書き方をマスターしていきます。
あなたもユウキくんと一緒に、アカリ先輩からコツを教わっているような気持ちで、読み進めてみてください。
ではさっそく、レポート作成を始めましょう!
まずはこれだけ!レポートは「序論・本論・結論」の3段構造
 ユウキくん
ユウキくんアカリ先輩、よろしくお願いします!



…とは言ったものの、やっぱり何から手をつければいいのか…。
レポートって、そもそもどういう順番で書くものなんですか?
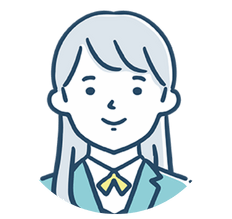
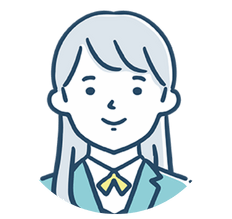
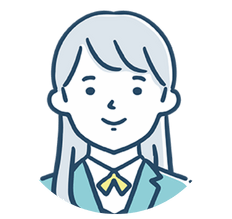
うんうん、そこからだよね!大丈夫、難しく考えなくてOK。



どんなに長くて立派なレポートも、実はたった3つのパーツでできてるんだ。それが、「序論・本論・結論」だよ。



序論・本論・結論…
よく聞く言葉ですけど、それぞれ何を書くんですか?



映画にたとえるとわかりやすいかな。
【序論】映画の「予告編」。これからどんな話が始まるのか、見どころを紹介するパート。
【本論】映画の「本編」そのもの。調査したことや、そこから考えたことをたっぷり書く、一番の見せ場。
【結論】映画の「結末」。結局、この話は何が言いたかったのかをまとめる、締めくくりのパート。



この3つの順番で書くのが、レポートの基本的な「型」なんだよ。
レポートは「序論・本論・結論」という型に沿って書くのが基本です。
これから各パーツの役割を詳しく見ていきますが、まずはこの「予告編→本編→結末」という大きな流れだけを、頭に入れておきましょう。
【お手本つき】一緒にレポートの書き方をマスターしよう!



この記事では、「序論・本論・結論」という3つのパーツの作り方を、お手本を見せながら一つひとつ解説していくから安心してね。



お手本、ですか?



うん!私たちでレポートを1本、今ここで作っていくよ。



テーマは、『タイパ(タイムパフォーマンス)を重視する高校生の意識とそのメリット・デメリット』。
動画の倍速視聴とか、ショート動画とか、みんなの身近にあるテーマだから、イメージしやすいでしょ?



タイパ!
確かに、自分もよく使ってる言葉です。
それなら、何となく考えられそうかも…。



でしょ?じゃあ早速、最初のパーツになる「序論(予告編)」の作り方から見ていこう!
ここから、二人が作る「タイパ」レポートが、あなたのお手本になります。
ぜひ、ご自身のテーマと照らし合わせながら、読み進めてみてください。
ステップ1【序論】レポートのつかみを書こう
ここからは、レポート作成の具体的なステップに入ります。
まずは最初のパーツである「序論」。
序論は、あなたのレポートを読者が最初に目にする、いわば「顔」の部分です。
ここで読者の心をつかむことで、この後の本論もスムーズに読み進めてもらえます。
序論は3つの部品で組み立てる



序論が「予告編」なのはわかったんですけど、じゃあ具体的に、予告編って何で構成すればいいんですか?
いきなり「このレポートの目的は…」って書き始めてもいいんですか?



良い質問だね!
いきなり目的から入ると、読者は「え、なんで急にその話?」ってなっちゃうんだ。



だから、序論はちゃんとした順番で作る必要があるの。
でも安心して。
序論もたった3つの部品でできてるから。
① 背景: なぜ今、このテーマを取り上げるのか?(現状や事実)
② 問題提起: その中で、どんな疑問や問題があるのか?(具体的な疑問)
③ 目的: このレポートで、何を明らかにしたいのか?(レポートのゴール)



へぇー、序論も分解できるんですね!



そうだよ!
この「背景→問題提起→目的」っていう順番は、レポートを論理的に見せるための黄金ルールなんだ。



この順番を守るだけで、「お、このレポートはちゃんとしてそうだな」って思ってもらえるから、絶対に覚えよう!
【実演】「タイパ」レポートの序論はこう書く!



なるほど…。
理屈はわかったんですけど、いざ自分のテーマで書くとなると、やっぱり難しそうです。



だよね。
じゃあ、さっそく私たちの「タイパ」レポートで実演してみよう!
このお手本を真似すれば、すぐに書けるようになるから。
① 背景



まずは、このテーマの「タイパ」が「最近、どうなっているか」という現状や事実を書くよ。
② 問題提起



次に、その状況を見て、「でも、それってどうなの?」っていう疑問がわいてきたら、それを投げかけよう。
③ 目的



最後に「だから、このレポートでこれを調べます!」って、ゴールをはっきり示そう!



おおっ…!
こうやって見本があると、めちゃくちゃイメージが湧きます!



3つの部品を順番に並べただけなのに、すごくちゃんとした文章に見える…!



でしょ?これが「型」の力なんだ。
【ワークシート】あなたのテーマで序論を書いてみよう
さあ、今度はあなたの番です。
お手本を参考に、ご自身のテーマで序論の内容を考えてみましょう!
難しく考えず、以下の3つの質問に、まずは短い文章で答えてみてください。
① あなたのテーマについて、最近の状況や一般的な事実を書いてみよう(背景)
ヒント:「近年、〇〇が問題になっている」「私たちの周りでは、〇〇が当たり前になっている」など
② その状況の中で、あなたが感じた疑問や「なぜ?」と思うことは何ですか?(問題提起)
ヒント:「しかし、〇〇という問題もあるのではないか」「なぜ、〇〇なのだろうか」など
③ このレポートで、何を明らかにしたいですか?(目的)
ヒント:「そこで本レポートでは、〇〇を明らかにすることを目的とする」など
この3つの質問への答えをつなぎ合わせるだけで、あなたのレポートの序論は、もうほとんど完成です。
ステップ2【本論】レポートのメインを書こう
序論でレポートの「顔」を整えたら、次はいよいよ「本論」の作成です。
本論は、あなたの探究活動で調べたことや、考えたことを具体的に示す、レポートで最もボリュームが大きくなるメインパート。
ここがしっかりしていると、レポート全体の説得力が格段にアップします。
何をどう調べる?|「調査・研究の方法」の書き方



いよいよ本論ですね!何から書けばいいんですか?



うん、本論もいくつかの部品に分かれてるんだ。
まず最初に書くべきなのは、「私は、こんな方法で調査・研究をしました」という宣言だよ。



調査の方法、ですか?
どうしてそんなのを先に書く必要があるんですか?



それはね、このレポートの「信頼性」を高めるためなんだ。
「この調査結果は、ちゃんとした手続きを踏んで得られたものですよ」と最初に示すことで、読者は安心してこの後の話を読み進められるんだよ。



アンケート、インタビュー、文献調査、実験…自分がやったことを正直に書けばOK!
客観的な事実を伝えよう!|「結果」の書き方



調査方法を書いたら、次はその調査で「何がわかったか」という事実を書く。
これが「結果」のパートだよ。



わかったことを書くんですね!



じゃあ、「こう調べてみたら、こうだということがわかって、すごいと思いました!」みたいな感じでいいんですか?



おっと、ユウキくん、ストップ!そこが一番大事なポイント。
「すごいと思いました!」っていうのは、ユウキくんの「意見」や「感想」だよね。



「結果」のパートに書くのは、誰が見ても変わらない「客観的な事実」だけなんだ。



事実だけ…ですか。



そう。例えばアンケートを取ったら、「『はい』と答えた人が〇〇人いた」という事実だけを書く。
そこに「この結果は驚きでした」みたいな自分の気持ちは、まだ入れちゃダメ。



事実と意見をしっかり分けるのが、良いレポートの鉄則だよ。
【見やすいグラフを作る3つのコツ】
アンケート結果などは、文章だけで説明するより、グラフを使うと一目でわかってすごく効果的だよ!
Excelやスプレッドシートで作ったグラフを載せるときは、この3つを意識してみてね。
① 必ずタイトルを入れる!
「図1:動画の倍速視聴の経験」のように、「このグラフが何を表しているか」を一言で示そう。
② デザインはシンプルに!
3Dやカラフルすぎる色は避け、伝えたい情報が一番目立つようにしよう。
③ グラフからわかることを一文添える!
グラフの下に「このグラフから、〇〇という傾向が読み取れる」と書き加えるだけで、読者の理解度は格段にアップするよ。
ここで差がつく!|「考察」の書き方



事実だけを書いた「結果」の後に、いよいよユウキくんの意見を書くパートがやってくる。
それが「考察」だよ。



ここでやっと、自分の考えを書いていいんですね!



その通り!
この考察こそが、ユウキくんのレポートの価値を決める、一番の見せ場なんだ。



「結果」で示した事実をもとにして、「この事実から、自分はこう考える。なぜなら…」と、自分なりの考えを論理的に展開していく。
ただの感想じゃなくて、「なぜそう言えるのか?」という根拠もセットで示すのがポイントだよ。
【実演】「タイパ」レポートの本論はこう書く!



事実と意見を分ける…。
頭では分かりますけど、やっぱり難しそう…。



大丈夫!これもお手本を見れば一発だよ。
「タイパ」レポートの本論を、実際に見てみよう。
調査・研究の方法
結果



ちなみに、質問の内容によってグラフも使い分けてるよ!



選択肢が多い「倍速視聴の頻度」は、棒グラフの方が比べやすいし、「はい/いいえ」のシンプルな問いには、円グラフが割合をパッと見せるのにぴったりなんだ。
考察



なるほど…!
「結果」は本当に「〇〇だった」という事実だけが書いてあって、「考察」で初めて「これは〇〇と考えられる」って意見を述べてるんですね!



こうやって分かれていると、すごく理解しやすいです。
【ワークシート】あなたのテーマで本論を書いてみよう
さあ、あなたも書いてみましょう!
レポートで最も重要な、この本論パートを組み立てていきます。
以下の質問に答える形で、情報を整理してみてください。
① あなたは、どんな方法で調査・研究をしましたか?(調査・研究の方法)
ヒント:「誰に」「いつ」「どんな方法で」調べたのかを具体的に書こう。
② その調査から、どんな事実やデータがわかりましたか?(結果)
ヒント:数字や具体的な事実を、箇条書きで3つほど挙げてみよう。ここでは自分の意見は入れないこと。
③ その事実から、「なぜそうなったんだろう?」「これはつまり、どういうことだろう?」と考えてみたことを書いてみよう(考察)
ヒント:「この結果から、〇〇ということが考えられる。その理由は…」という形で、根拠とセットで意見を述べよう。
ステップ3【結論】レポートの締めくくりを書こう
いよいよ最後のパーツ、「結論」です。
ここまで来れば、レポートの完成はもう目の前。
結論は、これまで書いてきた序論と本論の内容をまとめる、締めくくりの部分です。
このパーツで絶対にやってはいけないのは、新しい情報を付け加えること。
結論はあくまで「まとめ」なので、自信を持って、これまでの内容を整理することに集中しましょう。
結論は2つのパーツでOK!|「要約+課題」



ついに結論ですか!
結末って聞くと、なんだかすごいことを書かないといけない気がして、緊張します…。



大丈夫、大丈夫!
結論こそ、一番シンプルに考えればOKなんだよ。



実は、結論もたった2つの部品でできてるの。
① 研究の要約: このレポートで、結局何がわかったの?(本論のまとめ)
② 今後の課題: このレポートではわからなかったことは何?次に何を知りたい?(探究の未来)



え、それだけでいいんですか?



うん!特に大事なのは、①の要約が、序論で立てた「問い」や「目的」に、ちゃんと答える形になっていることなんだ。



「予告編(序論)」で投げかけた謎を、「結末(結論)」でしっかり回収してあげるイメージだね。
そうすれば、レポート全体に一本の筋が通って、すごくわかりやすくなるんだよ。
【実演】「タイパ」レポートの結論はこう書く!



序論へのアンサー、ですか。なるほど…。



早速「タイパ」レポートの結論を見てみよう。
すごくシンプルにまとめているから、注目してみて。
① 研究の要約
② 今後の課題



本当だ!
本論で書いてあったことが、すごく短くまとめられてるだけですね。



それに、「今後の課題」って、ただの反省文じゃなくて、「次にやりたいこと」を書くんですね!



その通り!
そう書くことで、ユウキくんの探究が「ここで終わりじゃないんだぞ」っていう未来への広がりを見せることができるんだ。
レポートを読み終わったときの印象が、ぐっと良くなるテクニックだよ。
【ワークシート】あなたのレポートを完成させよう
さあ、これが最後のワークシートです!
あなたのレポートを、あなた自身の言葉で締めくくりましょう。
① あなたの探究で、結局何が明らかになりましたか?(研究の要約)
ヒント:序論で立てた「問い」に、一言で答えてみよう。本論の「考察」で述べた、あなた自身の考えを短くまとめよう。
② 次に探究するとしたら、どんなことを調べてみたいですか?(今後の課題)
ヒント:「今回は〇〇だけだったが、次は△△も調査したい」という形で、今回の探究で足りなかったことと、次にできそうなことを書こう。
ここまで書き終えたら、レポートの土台はもう完成したも同然です!
レポートの質が一気にアップ!知っておきたい重要ルール&テクニック
これまでのステップで、レポートの基本的な「型」はマスターできましたね。
しかし、ここから紹介するルールやテクニックを知っていると、あなたのレポートの信頼性と完成度は、さらに何倍にもアップします。
他の人と差がつく、重要なポイントばかりです。
【超重要】盗作は絶対ダメ!「引用」と「参考文献」の正しい書き方



アカリ先輩、友達が「レポートはコピペでいいんだよ」って言ってたんですけど、本当ですか…?



ユウキくん、それだけは絶対にダメ!
それは「コピペ」じゃなくて、「盗作」っていう立派な不正行為なんだ。バレたら、そのレポートは0点になってしまう可能性もある、とても危険なことだよ。



えー!そうなんですか!
でも、本やネットの情報を参考にしちゃいけないってことですか?



もちろん、参考にするのはOK!
むしろ、たくさんの情報を参考にした方が、レポートの深みは増すよ。



大事なのは、「これは、私が考えた意見です」「これは、〇〇さんの本からお借りした意見です」という境界線を、はっきり読者に示すことなんだ。
そのためのルールが「引用」と「参考文献」だよ。



なるほど、勝手に使っちゃうのがダメなんですね。



その通り!
ちゃんとルールを守って情報を借りれば、それはユウキくんのレポートの信頼性を上げてくれる、強力な武器になるんだ。
【信頼できる情報源の見分け方】
引用する元の情報が「個人の感想」や「ウソ」だったら、レポートとして説得力がなくなっちゃうよね。
情報源を選ぶときは、この3つをチェックしてみよう。
① 誰が書いたかわかる?
大学の先生(.ac.jp)、政府や市役所(.go.jp)、有名な新聞社や研究機関の名前があるものは信頼度が高いよ。
② いつ書かれたかわかる?
特に科学や社会のテーマは情報が新しくないと意味がないことも。日付が明記されているものを選ぼう。
③ 根拠(データ)は示されている?
「〜だと思う」じゃなくて、「〇〇の調査によると〜」と、客観的なデータに基づいて書かれている記事は信頼できるよ。
図書館の司書さんに「〇〇について調べてるんですけど…」と相談するのも、最強の裏ワザだからね!



引用の具体的な書き方は、文の途中にカギカッコで入れたり、長い場合は段落全体を引用したり、いろいろな方法があるんだ。



そして、レポートの最後に「参考文献」というページを作って、参考にした本やWebサイトの情報を、リストにしてまとめて書くんだ。



なるほどー!こうやって書けば、ちゃんと敬意を払いつつ、自分のレポートの説得力も上げられるんですね!



でもアカリ先輩、参考文献のURLって、書くんですか?
なんだかすごく長くなるし、見た目がゴチャゴチャしちゃう気がして…



ユウキくん、良い質問だね!
そう感じるの、すごくよくわかるよ。



でもね、Webサイトを参考にした場合、URLは絶対に書かなくちゃダメなんだ。
むしろ、URLがないと参考文献の意味がなくなっちゃうくらい、大事なものだよ。



ええっ、そんなに大事なんですか!?



うん。考えてみて。
本の参考文献には「どの出版社から出た、何ていう本か」を書くでしょ?



WebサイトにとってのURLは、その「インターネット上の住所」みたいなものなんだ。



住所、ですか。



そう!この「住所」を書いておかないと、レポートを読んだ先生や友達が、「この情報、もっと詳しく知りたいな」と思っても、元のページにたどり着けないんだ。
それはすごく不親切だし、ユウキくんのレポートの信頼性もガクンと下がっちゃう。



そして、一緒に書いた「閲覧日」は、「私は、この日に、この住所で、この情報を見ました!」っていう、アリバイみたいなものかな。



URLは「住所」で、アクセス日は「アリバイ」!
そう考えると、絶対に必要だってことがよくわかりました!
【あるある】高校生がやりがちな「惜しいレポート」7つのパターン
ここでは、多くの高校生が陥りがちな「惜しい!」レポートのパターンを7つ紹介します。
これを知っておけば、あなたのレポートが「ただの調べ学習」で終わるのを防ぐことができます。
自分のレポートが当てはまっていないか、チェックリストとして使ってみてください。
パターン① テーマが壮大すぎる


惜しい例:「地球温暖化を解決する方法」
なぜ惜しい?
テーマが大きすぎて、何から調べればいいかわからず、結局ネットの受け売り情報をまとめただけで終わってしまう。
【改善策】
「私たちの学校でできるエコ活動の効果」のように、主語を「自分」や「自分の学校」にして、調査可能なサイズまでテーマを絞ろう!
パターン② 調べ学習で終わっている


惜しい例:事実の羅列だけで、書き手の意見や考え(考察)が全く見られない
なぜ惜しい?
先生が一番見たいのは、あなたが「どう考えたか」。事実だけでは評価が難しい。
【改善策】
「結果(事実)」と「考察(意見)」のパートをしっかり分け、「この事実から、自分はこう考える」という主張を、根拠と共に述べよう!
パターン③ 「問い」が「質問」になっている


惜しい例:「少子化は進んでいますか?」
なぜ惜しい?
Yes/Noで答えが出てしまい、探究が深まらない。
【改善策】
「なぜ少子化は進むのか?」「どうすれば若者が結婚したくなる社会になるか?」のように、「なぜ?」「どうすれば?」を使い、簡単に答えが出ない「問い」を立てよう!
パターン④ ただの感想文になっている


惜しい例:「〜を調べて、すごいと思いました」
なぜ惜しい?
「すごい」の根拠となる客観的なデータがなく、説得力に欠ける。
【改善策】
「アンケートで8割が支持したから、すごいと思った」のように、感情(すごい)と事実(データ)をセットで語る癖をつけよう!
パターン⑤ 図やグラフが不親切


惜しい例:タイトルや説明がなく、グラフだけがポツンと貼られている
なぜ惜しい?
読者が「このグラフは何を表しているの?」と混乱してしまう。
【改善策】
「図1:クラスの男女比」のようなタイトルと、「このグラフから〇〇がわかる」という短い説明文を必ず添えよう!
パターン⑥ 引用と参考文献のルールを無視している


惜しい例:出典を書かずに、ネットの文章をそのまま使っている
なぜ惜しい?
「盗作」という不正行為にあたる。レポートの信頼性もゼロになる。
【改善策】
他人の文章やデータを使った場合は、必ずルールに沿って「引用」し、レポートの最後に「参考文献」リストを載せよう!
パターン⑦ 「今後の課題」がただの反省文


惜しい例:「調査の時間が足りなくて、焦ってしまった」
なぜ惜しい?
個人の反省や感想で終わってしまっている。
【改善策】
「今回は〇〇だけだったが、次は△△も調査したい」のように、次の探究への「発展性」を示そう!
AIって使っていいの?|探究レポートでの活用法と注意点



そういえばアカリ先輩、最近よく聞くChatGPTみたいなAIって、レポート作成に使ってもいいんですか?
なんだか、ズルしてるみたいで…



良いところに目をつけたね!
結論から言うと、AIは「賢く使えば、最強の相棒になる」よ。



でも、使い方を間違えると、それこそ思考停止の「ズル」になっちゃう。



最強の相棒…!
どういうことですか?



例えば、AIに「レポートを全部書いて」と丸投げするのは、ただのズル。
ユウキくんの力には全くならない。



でも、AIを「自分だけの優秀な相談相手」や「壁打ちパートナー」として使うのは、すごく賢い活用法なんだ。
【AIを「相棒」にする、賢い使い方3選】
① アイデアの壁打ち相手として使う
「『タイパ』をテーマに探究したいんだけど、面白い切り口はない?」と相談すれば、自分では思いつかなかった視点を提案してくれるよ。
② 分かりにくい言葉の翻訳家として使う
難しい論文やニュース記事を貼り付けて、「この記事を、高校生にもわかるように要約して」と頼めば、教えてくれるよ。
③ 構成案のチェック役として使う
自分が考えたレポートの構成を見せて、「この構成で論理的に話が通じるか、アドバイスをください」と頼めば、客観的な視点で弱点を教えてくれるよ。



大事なのは、最終的に「考える」のは自分自身だっていうこと。
AIはあくまで、ユウキくんの考えを助けるための道具。
この距離感を間違えなければ、探究の質をぐっと高めてくれるよ!
コピペで使える!探究レポート構成テンプレート
お疲れ様でした!
これまでの解説で、レポートを構成する全てのパーツが揃いましたね。
ここでは、その集大成として、そのまま使える「レポート構成テンプレート」を用意しました。
以下のテンプレートを、WordやGoogleドキュメントに貼り付けて、カッコ内の指示に沿って文章を埋めていくだけで、あなたのレポートの土台が完成します。
何度も読み返したくなる、あなただけの「最強のガイドブック」として、ぜひ活用してください。
ID学園高等学校_コピペで使える!探究レポート構成テンプレート
▼▼▼ ここからコピー ▼▼▼
探究レポート
タイトル: (あなたのレポートのタイトルをここに書く)
氏名: 〇年〇組 氏名
1.序論(レポートの予告編)
【背景】
(ここに、あなたのテーマの現状や一般的な事実を書く。「近年、〇〇が当たり前になっている」など、読者が「なるほど、そういう状況なのか」と理解できる情報を提示しよう)
【問題提起】
(その現状の中で、あなたが「なぜ?」「どうして?」と感じた疑問を書く。「しかし、〇〇という問題点も指摘されている」「なぜ、〇〇なのだろうか」など、これから何を明らかにするのか、問題の大事なポイントを示そう)
【目的】
(このレポートで、何を明らかにするのか、ゴールをはっきり示す。「そこで本レポートでは、〇〇を調査・分析し、△△を明らかにすることを目的とする」という形が基本)
2. 本論(レポートの本編)
【調査・研究の方法】
(ここに、どんな方法で調べたのかを具体的に書く。「誰に」「いつ」「どんな方法で」調査したのかを明確に記述することで、レポートの信頼性がアップする)
【結果】
(ここに、調査から判明した、客観的な事実やデータだけを書く。あなたの意見や感想は、ここではまだ書かないこと。必要に応じて、図やグラフも活用しよう)
【考察】
(ここに、「結果」で出た事実をもとに、あなたが「どう考えたか」を筋道を立てて説明する。レポートの中でも、いちばん大事な部分。「この結果から〇〇だと考えられる。その理由は△△だからだ」というように、必ず「意見」と「根拠」をセットで述べよう)
3.結論(レポートの結末)
【研究の要約】
(このレポートで、最終的に何が明らかになったのかを短くまとめる。序論で立てた「問い」に、ここでズバリと答えよう。本論の考
察で述べた、あなた自身の考えを要約する)
【今後の課題】
(今回の探究で足りなかったことと、次にできそうなことを書く。「今回は〇〇しか調査できなかったため、今後は△△も調査する必要がある」のように、次に何を探究したいかを述べよう)
4.参考文献
(このレポートを書くにあたって参考にした本、論文、Webサイトなどの情報を、ルールに沿ってリストアップする)
1.(例)文部科学省(2023)『高等学校を中心とした「総合的な探究の時間」の指導の手引き』
(https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/20230522-mxt_kyouiku_soutantebiki02_1.pdf 2025年○月○○日閲覧)
2. …
▲▲▲ ここまでコピー ▲▲▲
【Q&A】探究レポートの「素朴なギモン」に答えます!
- レポートの適切な文字数はどれくらいですか?
-
まず、学校や先生からの指定がある場合は、必ずそれに従ってください。
特に指定がない場合、一般的には2,000〜4,000字程度(原稿用紙5〜10枚分)が目安となることが多いです。
しかし、最も重要なのは文字数を満たすことよりも、序論・本論・結論の各パートで必要な要素をしっかり記述できているかです。 - アンケート調査は何人くらいに実施すればいいですか?
-
テーマや目的によりますが、例えば、2、3人にしか聞いていないと、それは「あなたの友達の意見」であって、レポートの根拠にするには少し弱いですよね。
調査結果として説得力を持たせるためにも、「クラスの半分以上」など、比較や分析ができる人数を目指しましょう。
自分のクラス全員(30〜40人)を対象にするのは、比較もできておすすめです。 - 手書きで提出しても問題ないですか?
-
まずは学校のルールを確認しましょう。
もし選択できるのであれば、パソコンでの作成をおすすめします。文章の修正や構成の入れ替えが簡単で、図やグラフもきれいに挿入できるため、レポートの質がかなり向上します。
手書きの場合は、第三者が読みやすいよう、丁寧な字で書くことを何よりも優先してください。 - レポートを書いている途中に行き詰まったら、どうすればいいですか?
-
レポート作成で行き詰まるのは、誰にでもある、ごく普通のことです。
一人で抱え込まず、以下の対処法を試してみてください。人に話す: 先生や友達に現状を話すだけで、頭が整理されたり、思わぬアドバイスがもらえたりします。
一度離れる: 集中できないときは、思い切って1日休みましょう。リフレッシュすることで、新しい視点が生まれることがあります。
原点に戻る: 序論で立てた「問い」や「目的」を再確認し、「自分は一体何を明らかにしたかったんだっけ?」と立ち返ってみましょう。
- 締切まで時間がない!どう計画すればいいですか?
-
時間がないと焦りますよね。
そんなときは「締切から逆算」して、大まかな計画を立てるのがおすすめです。例えば、残り時間が4週間なら、以下のように時間配分を考えてみましょう。
【第1週】 テーマに関する情報収集と、レポート全体の計画づくり
【第2週】 レポートの執筆(序論・本論の結果まで)
【第3週】 考察をじっくり考え、結論を書く
【第4週】 全体を読み返し、推敲・修正と参考文献リストの作成「計画通りに進まなくても大丈夫!」と割り切って、まずは全体像をつかむことが大切です。
- レポートで最も評価されるのは、どんな点ですか?
-
先生が最も注目するのは、あなたが「どれだけ主体的に考え、試行錯誤したか」というプロセスです。
特に、調べた事実(結果)を踏まえて、自分なりの考え(考察)を筋道を立てて導き出そうと努力している部分が、最も重要な評価ポイントになります。
完璧な答えが出せなくても、粘り強く考え抜いた「足跡」を、レポートで示すことを意識しましょう。考察の書き方についてはこちら|考察
まとめ|「最後までやり遂げた経験」が一番の自信になる
この記事を読み終えて、少しはレポートが書けそうな気がしてきましたか?
読み始める前の「何から書けばいいか分からない」という不安は、少し軽くなったでしょうか?
レポートを書くには、たくさんのことを考える必要があるので、まだまだ完璧ではないかもしれません。
大変だったと思いますが、この「一つのことを最後までやり遂げようと試みた経験」は、とても価値があります。
筋道を立てて物事を考える力、情報を整理する力、そして計画的に作業を進める力。
これらはすべて、大学入試やその先の社会で必ず役立つスキルです。
難しいことにチャレンジした自分を、たくさん褒めてあげてくださいね。
【ID学園の夢活】仲間と学ぶリアルな体験
ID学園では、生徒が主体的に学ぶ『夢活』を開講しています。
この夢活は、アウトプット中心の活動を通して、社会で役立つ問題発見・解決能力を高めることを目的としています。
自分の興味や関心に合わせて研究テーマを設定し、仲間との議論や発表を重ねながら探究を深めていきます。
作成したレポートやプレゼン資料は、大学入試などで活用できる公式な活動履歴にすることも可能です。
また、同じ興味を持つ仲間と一緒に活動する中で、新しい視点を得たり、自然と交友関係を広げたりできるのも、大きな魅力です。
『夢活』の活動の様子や、先輩たちのリアルな声は、学校説明会で直接お話ししています。
少しでも「面白そう!」と感じたら、気軽に説明会に参加してみてくださいね。


【お役立ちリンク】もっと詳しく知りたいなら、ここもチェック!
レポートの書き方について、「もっと本格的に知りたい」という人は、以下のページも参考にしてみてください。
NHK高校講座「高校生・先生のための探究ガイドブック」
https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tanq/assets/20_tanq_guide.pdf
理数教育研究所「レポートの書き方」
https://www.rimse.or.jp/research/pdf/report_chukou.pdf